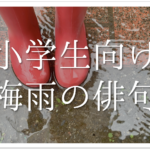梅雨時を代表する花である「紫陽花(アジサイ)」。
大きな毬状の見た目とバリエーション豊かな色合いが魅力的なお花です!そんな紫陽花を俳句に詠んでみませんか?
【紫陽花】
紫陽花の毬はずませる下校の子
紫陽花の一花に触れる散歩道#haiku #kigo pic.twitter.com/5ThBpHxxqf
— とんぼ (@tonbo_yu_yu) June 11, 2018
【紫陽花】
あぢさゐのふくらみに雨やはらかし#haiku #kigo pic.twitter.com/KuyugM6Eh1
— とんぼ (@tonbo_yu_yu) June 11, 2018
今回は、紫陽花の俳句の作り方についてわかりやすく解説していきます。

目次
俳句を作る前に知っておきたい!紫陽花の特徴

紫陽花は日本原産の花で、昔から日本人に親しまれてきました。
紫陽花の名所となっているお寺なども、全国各地にあります。

(あじさいに燕 出典:Wikipedia)
花びらのように見える4枚の萼の中心に細かい粒のような花があることから、「四葩(よひら)」とも呼ばれます。
また、花色は酸性の土壌で青色に、アルカリ性の土壌では赤紫色になります。

紫陽花の俳句の作り方

(1)五七五の十七音で構成する
まずは俳句の基本的なルールを確認しましょう。
俳句といえば、五・七・五のリズムが特徴です。
【例】作者:正岡子規
柿食えば(五音) 鐘が鳴るなり(七音) 法隆寺(五音)
字余り・字足らずの句や自由律俳句という技法もありますが、それらは緻密な意図をもって作らなければ効果が出ません。

(2)正しい表記をする
俳句を紙に書いている人もいれば、スマホのメモ帳などに打ち込んでいる人もいると思います。
どちらにしても表記は正しくしましょう。
五七五の間を空けず、1行で書くのが正しい表記です。
【例】
◯ 大輪の紫陽花に葉の大きさよ
× 大輪の 紫陽花に葉の 大きさよ
× 大輪の
紫陽花に葉の
大きさよ

(3)一句に一季語
俳句には季語を一つ入れるようにしましょう。
1つの句に季語がいくつも入っていると、それぞれの季語の力が打ち消し合ってしまい、季語の魅力が伝わらなくなってしまします。
【例】
◯ 大輪の紫陽花に葉の大きさよ 季語「紫陽花」
× 梅雨時に紫陽花見つつビール飲む 季語「梅雨」「紫陽花」「ビール」

今回題材にする「紫陽花」は夏の季語ですので、他の季語は考えません。
(4)俳句の型を知る
俳句には「一物仕立て」と「取り合わせ」という2つの型があります。
一物仕立ては季語についてのみ詠むもの、取り合わせは季語と季語以外の要素を組み合わせて詠むものという違いがあります。
【例】
- 大輪の紫陽花に葉の大きさよ……季語の紫陽花について描写する一物仕立て
- 紫陽花や単身赴任まで三日……単身赴任という季語以外の要素が入っている取り合わせ
一般的に、一物仕立ての句を作るのは難しいと言われています。季語について描写しようと思うとどうしても発想が似通ってしまい、オリジナリティのある句が詠みづらいのです。
今回の紫陽花でいえば、雨粒に濡れて綺麗だとか、毬のような形だとか、そういったありふれた描写で俳句を作ってしまうことになります。少し新鮮さに欠けますよね。

(5)季語に取り合わせるものを考える
季語である紫陽花は4音なので、残りの13音で他のものを描写します。
13音が難しければ、切れ字を使って「紫陽花や」として12音で描写するのも良いでしょう。
まずは季語の紫陽花について情報を整理しましょう。
紫陽花はどこにありますか。庭に植えてありますか。花瓶に生けてリビングにありますか。お寺に群生している紫陽花ですか。
場所が整理できたら紫陽花以外のものに目を向けてみてください。
何がありますか。どんな匂いがしますか。どんな触り心地のものがありますか。誰が何をしていますか。

【例】
リボンして 紫陽花届く 2DK (作:中原忽胡)
(6)心情語は入れない
季語以外の情報を表現するとき、「うれしい」「悲しい」などの心情語は入れない方が魅力的な句になります。
心情は季語に託すのが、成功の鍵です。
【例】
◯ 紫陽花や単身赴任まで三日
× 紫陽花は雨にうたれて綺麗だな
季語以外の情報が明るい感じであれば鮮やかな紫陽花を、悲しい感じであれば萎れていたり雨に打たれてしっとりとしていたりする紫陽花を読み手は思い浮かべるでしょう。
このように季語と季語以外の情報が組み合わさって読み手の想像を膨らませることが大切なのです。

俳句作りの参考になる!紫陽花の有名俳句【5選】

【NO.1】正岡子規
『 紫陽花や 昨日の誠 今日の嘘 』
季語:紫陽花(夏)
現代語訳:紫陽花が咲いているなぁ。昨日の色が紫陽花の本当の色だと思ったのに、今日は変わっていて嘘の色になっている。

紫陽花は咲いている途中でも花の色を変えていくめずらしい花です。そのため、昨日見た色と変わっていた紫陽花の花の色を「誠」「嘘」と表現し、どの色が本当なのだろうと考え込んでいます。
【NO.2】加賀千代女
『 紫陽花に 雫あつめて 朝日かな 』
季語:紫陽花(夏)
現代語訳:紫陽花に朝露の雫が集まっている中で、朝日が輝いているなぁ。

朝露が紫陽花の花や葉にたまっているところに朝日が差し込み、輝いている様子を詠んだ句です。「輝く」といった雫や紫陽花の描写を直接詠まずに「朝日」という単語で情景を表現している美しい構成になっています。
【NO.3】松尾芭蕉
『 紫陽花や 帷子(かたびら)時の 薄浅黄 』
季語:紫陽花(夏)
現代語訳:紫陽花が咲いているなぁ。もう帷子を出す頃だと、薄い浅黄色の花を見て感じる。

「帷子」とは夏用の一重の着物のことで、ここでは「帷子時」と詠むことで衣替えの季節だということを表しています。「薄浅黄」は「黄」が入っているため勘違いされやすいですが、薄い水色のことです。紫陽花の花の色以外にも薄い夏用の着物としても想像しやすい色で、夏の始まりらしい爽やかな陽気を詠んでいる一句です。
【NO.4】松本たかし
『 紫陽花の 大きな毬(まり)の 皆褪せし 』
季語:紫陽花(夏)
現代語訳:紫陽花の大きな鞠のような花はみんな褪せた色をしている。

紫陽花は丸くボールのように咲きます。その様子を鞠に例えた上で、紫陽花の季節が終わり色褪せていく様子を残念そうに詠んでいるのが特徴です。遠くから見た紫陽花の花たちが皆一斉に色褪せ、暑い夏が始まる予兆を詠んでいます。
【NO.5】原石鼎
『 紫陽花の 白とは云へど 移る色 』
季語:紫陽花(夏)
現代語訳:この紫陽花の花は白だが、いずれほかの色に移っていくのだろう。

紫陽花は咲いている間に色を変えたり、近くに植えていても違う色の花を咲かせたりとさまざまな色を楽しめる花です。今目の前にある紫陽花は白い色をしているけれど、きっとこの花もほかの色に変わっていくのだろうという感慨を詠んでいます。
うまい!紫陽花の一般おすすめ俳句作品【5選】

【NO.1】
『 幼子の 四葩の精の ごとき舞 』
季語:四葩(よひら)(夏)
現代語訳:幼い子どもが紫陽花の妖精のように舞っている

【NO.2】
『 街を出る 日や紫陽花の 浅みどり 』
季語:紫陽花(夏)
現代語訳:住み慣れたこの街を出る今日という日よ。ふと目についた紫陽花は薄い緑色をしている

【NO.3】
『 日本間は 移民の郷愁 濃あじさい 』
季語:あじさい(夏)
現代語訳:外国に住む者にとって、家の日本間は故郷を懐かしむものだ。そこには濃い色の紫陽花が生けてある

【NO.4】
『 千段を 下る水音 濃あじさい 』
季語:あじさい(夏)
現代語訳:雨水が千の階段を下る音がする。そこには濃い紫陽花が咲いている

【NO.5】
『 一枝の あぢさゐ初恋 の重さ 』
季語:あぢさゐ(夏)
現代語訳:一つの枝に咲いている紫陽花。その重さは初恋と同じだ

さいごに

今回は紫陽花の俳句の作り方について説明してきました。
面白い取り合わせは浮かびましたか?
いろいろな組み合わせを試し、紫陽花という季語の生きる素敵な句を作ってみてくださいね。