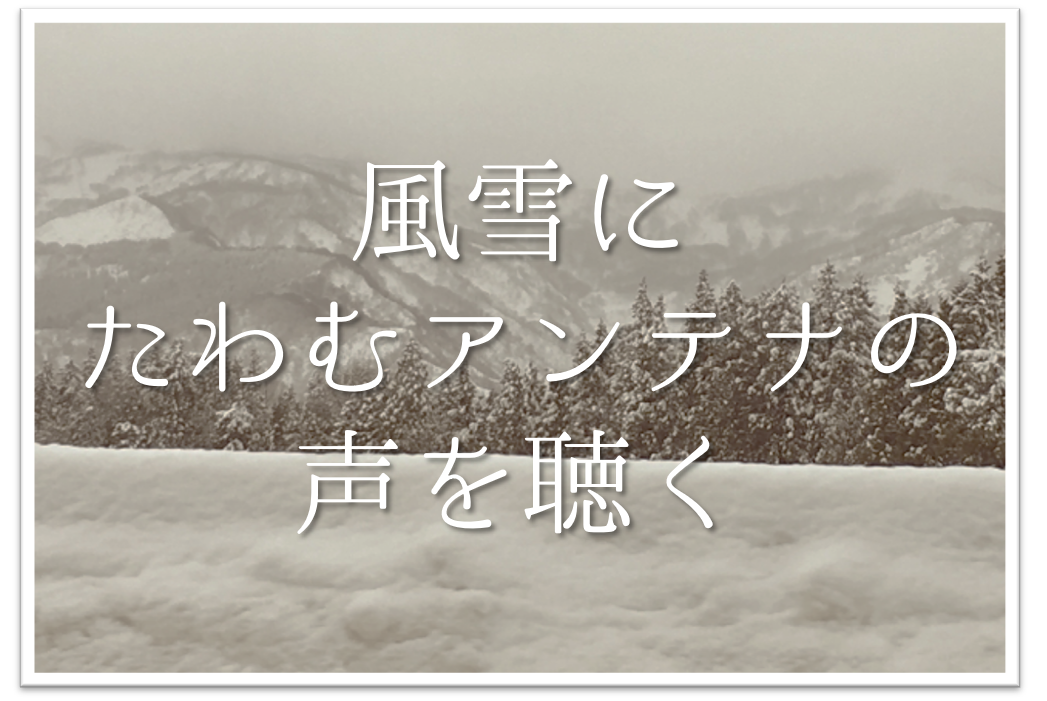
俳句が今日まで詠み継がれてきたのは、十七音で様々な事象を表現しているからだと言われています。
今回は数ある名句の中から「風雪にたわむアンテナの声を聴く」という山口誓子の句を紹介していきます。
風雪に
たわむアンテナの
声を聞く#谷村PA#山口誓子 pic.twitter.com/0OoiypSu5L
— ChokerJokers (@chokerjokers) March 13, 2024
この句には作者のどういった思いが詰まっているのでしょうか?
本記事では、「風雪にたわむアンテナの声を聴く」の季語や意味・表現技法・作者など徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「風雪にたわむアンテナの声を聴く」の季語や意味・詠まれた背景

風雪に たわむアンテナの 声を聴く
(読み方:ふうせつに たわむあんてなの こえをきく)
この句の作者は「山口誓子(やまぐちせいし)」です。
(山口誓子 出典:Wikipedia)
作者である誓子は、主に昭和期に活躍し、写生を得意とする俳人です。
初期の誓子は叙情的な俳句を好んでいましたが、後に近代的、都会的なものを題材に俳句を詠むようになります。

また、「や」「かな」といった切れ字を用いるのではなく、動詞の終止形・連体形による止めや口語の使用を定着させました。
季語
こちらの句の季語は「風雪」で、季節は「冬」を表します。
風雪は言い換えれば吹雪のことで、強風を伴う降雪のことを指します。
吹雪は他の天候と比べて特に視界が悪く、先が見えないことから、吹雪の中で外出すると遭難や雪による凍傷などが起こる危険もあります。

吹雪のある地方では、吹雪の間は外出しないことが鉄則となっています。
意味
この句を現代語訳すると・・・
「吹雪がアンテナをたわませているのだろう。アンテナから話し声のように音が聴こえる。」
という意味になります。
この句が詠まれた背景
この句は誓子が阿蘇山測候所を訪れた際に詠んだ句と言われています。
(※阿蘇山測候所は、その後に名称を阿蘇山特別地域気象観測所に変更。現在は廃止されています)
測候所とは天気や風向きなどを観測する場所で、観測所の屋根には様々な計器を取り付けられています。
この句が詠まれた阿蘇山測候所は、九州で最も標高が高い所として有名です。
特に冬は過酷で、九州の最低気温を記録するだけでなく、風が強く大雪になる厳しい環境であることが知られており、ここで吹雪に見舞われると外に出られず、身動きがとれなくなります。
誓子が訪れたときも吹雪で身動き取れなかった状態でした。

そんな中、測候所にいる誓子は外から聞こえる「たわむアンテナの音」を自らの耳で聞き、句に表現したのです。
「風雪にたわむアンテナの声を聴く」の表現技法

擬人法
擬人法とは、物事を人間の動作に例える技法のことを言います。
人間に例えることでまるで物事が生きているような印象になり、読み手に状況が伝わりやすくなります。
今回はアンテナから音が出ていることを人間の声に例えて表現しています。

声ですから、どこかから聞こえる会話のような絶え間ない音だと連想させています。
「風雪にたわむアンテナの声を聴く」の鑑賞文

【風雪にたわむアンテナの声を聴く】は、自然の猛威と機械を合わせることで、耳で聴く冬の厳しさを鮮明に表現しています。
周囲の状況は吹雪のため外に出られず、視界も悪い悪天候でした。つまり、誓子はアンテナの様子を直接見て詠むことは難しかったと考えられます。
しかし激しい吹雪の中、じっと耳を澄ますと話し声のような音が絶えず聴こえてきます。
風がアンテナをたわませて、風切り音がしていると誓子は想像できました。この句はその様子を全く違う二つの物質を並べて、読み手に鮮明に伝えています。
自然である吹雪と機械であるアンテナを合わせて、読み手に耳から目へと想像の幅を広げさせています。
何も太刀打ちできない自然の力強さと、それに呼応するように音を立てる機械とじっとする人間という対比です。

自然の厳しい情景が言葉巧みに詠まれています。
「風雪にたわむアンテナの声を聴く」の補足情報

阿蘇山と阿蘇山測候所
阿蘇山は標高1,592mの活火山で、日本の九州中央部・熊本県阿蘇地方に位置していて、冬には氷点下15℃になることもあります。
冬の訪れは九州としてはかなり早く、11月初頭から中旬頃にかけて初雪を観測し、12月以降は本格的な冬になります。真冬になると気温は-10℃未満の日もめずらしくはありませんが、積雪は多くても100cmを超えることは無く、豪雪地帯には指定されていません。
この句で詠まれている「阿蘇山測候所」は、1931年11月1日に熊本測候所の支所として開設されました。

(阿蘇山測候所 出典:阿蘇ぺディア)
この年に県内で行われた陸軍大演習の後予定されていた、昭和天皇の阿蘇火山への登山に備えるために設立されていて、火山活動の状態を観測するために造られています。
最初は木造であった庁舎も、1958年の爆発で被害を受けたため、翌年に鉄筋コンクリート造になっています。
平成10年(1998)3月からは、阿蘇山測候所の業務を阿蘇町黒川にある基地事務所に統合されました。
作者が阿蘇山測候所に滞在した正確な時期は分かりませんが、1936年に書かれた水原秋桜子の『現代俳句の理念』に「阿蘇山で大作を詠んでいる」とあるため、この当時の阿蘇山測候所は木造だったと考えられます。
常に強風が吹き荒れている場所では無いものの、「風雪」という言い方から強い吹雪の日だったのでしょう。

吹雪に対して少し頼りない木造の測候所とアンテナがギシギシと音を立てる中で、息を潜めて嵐が去るのを待つしか無かったと考えられます。
ほかの阿蘇山に関する俳句
作者には阿蘇山について詠んだ俳句がまだあり、その中にはこの句と状況が似ているものもあります。
「風速器 阿蘇荒天の 雪に舞ふ」
(訳:風速器が阿蘇山の荒天の雪に舞っているようだ。)
この句は阿蘇山の荒天、風速器という観測器具などが共通しているため、同時期に詠まれたものでしょう。
ほかにも冬の阿蘇山についていくつか俳句を残しています。
「鳴り動む(とよむ) 阿蘇にはあらず 雪に荒る」
(訳:鳴って騒いでいるのは火山である阿蘇山ではなく荒々しく降る雪だ。)
「雪嶺を 連ねて阿蘇の 火山系」
(訳:雪の積もる嶺を重ねて阿蘇の火山系はできている。)

雪の激しい阿蘇山を多く詠んでいるため、この句と同じ時期に作られた句を前述の『現代俳句の理念』で「山口誓子の作った阿蘇山の大作」と称していたのかもしれません。
作者「山口誓子」の生涯を簡単にご紹介!
(山口誓子 出典:Wikipedia)
山口誓子(やまぐち せいし)本名新比古(ちかひこ)は、大正から昭和、平成の初期にかけて活躍した俳人です。
生まれは明治34年(1901年)で、京都府出身です。幼いころに祖父に引き取られ、樺太(からふと:現在のロシアのサハリン島)で数年を過ごしました。
帰郷して京都の学校に進んだ大正9年(1920年)に、京大三高俳句会に出席し、句作に腰を入れるようになりました。
俳句雑誌「ホトトギス」へ投句を行い、昭和の初期には水原秋桜子(みずはらしゅうおうし)、高野素十(たかのすじゅう)、阿波野青畝(あわのせいほ)らとともに、ホトトギス派の四Sと呼ばれるに至りました。
しかし、ホトトギス派とは創作の方向性にずれが生じ、ホトトギス派から離脱。やがてホトトギス派から離れた水原秋桜子らと新興俳句をすすめていく運動に力を入れるようになりました。
その後も数多くの名句を生み出し、平成6年(1994年)92歳で亡くなりました。
山口誓子の作風は定型俳句に叙情性を盛り込む「万葉調」で詠まれたものや、現代的な季語、連作俳句などチャレンジ精神旺盛だったことが知られています。
山口誓子のそのほかの俳句

( 摂津峡にある句碑 出典:Wikipedia)
- 学問のさびしさに堪へ炭をつぐ
- 突き抜けて天上の紺曼珠沙華
- 匙なめて童たのしも夏氷
- ほのかなる少女のひげの汗ばめる
- 夏草に機缶車の車輪来て止まる
- 海に出て木枯らし帰るところなし
- 夏の河赤き鉄鎖のはし浸る
- 炎天の遠き帆やわがこころの帆
- ピストルがプールの硬き面にひびき
- 流氷や宗谷の門波荒れやまず
- かりかりと蟷螂蜂のかほを食む















