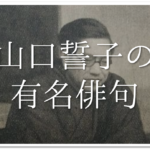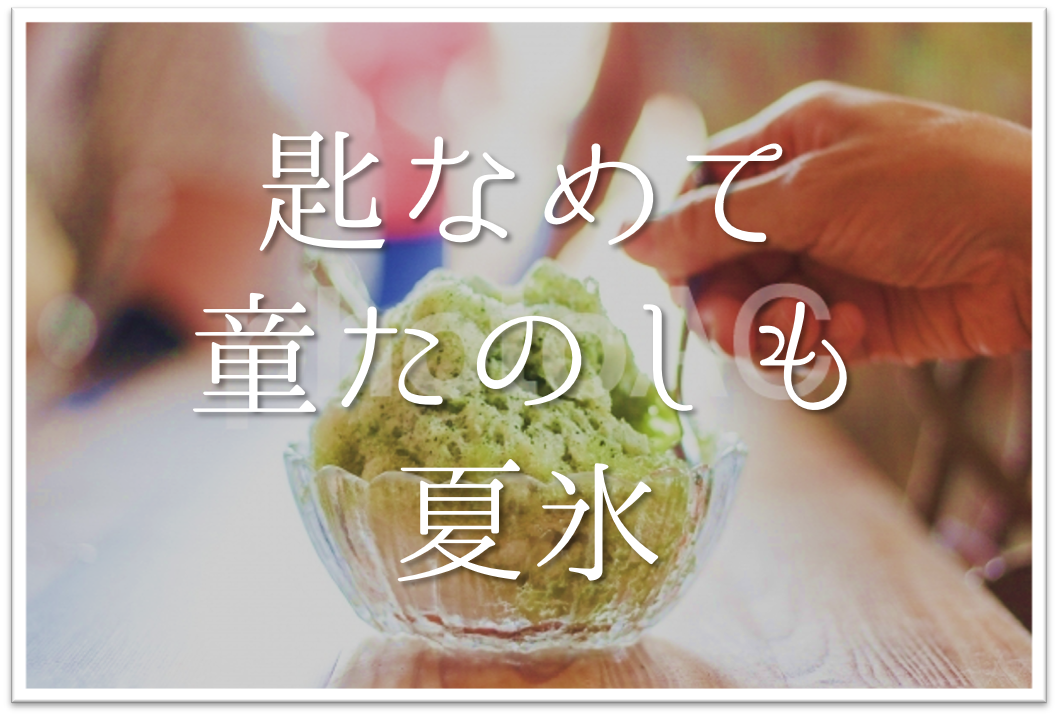
この世に存在する最も短い詩「俳句」。
わずか17音で物語つづる俳句は日本を飛び出し、今や世界中の人々から愛される芸術の一つです。
今回は数多くある名句の中でも「匙なめて童たのしも夏氷」という山口誓子の句を紹介していきます。
匙なめて童たのしも夏氷 山口誓子
童じゃありません。おっさんです。はい。 pic.twitter.com/XqxL2X0Muv
— 熊沢 透 (@kumat1968) August 13, 2014
本記事では「匙なめて童たのしも夏氷」の季語や意味・表現技法・作者など徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「匙なめて童たのしも夏氷」の作者や季語・意味

匙なめて 童たのしも 夏氷
(読み方:さじなめて わらべたのしも なつごおり)
こちらの句の作者は「山口誓子」です。
山口誓子が夏の風景を詠んだもので、1932年に発行された誓子の句集「凍港」に収録されています。
季語
こちらの句の季語は「夏氷」で、季節は「夏」を示します。
夏氷とは、一般的に言えばかき氷のことを指します。
俳句ではかき氷を指す「氷水」、あるいはかき氷店を指す「氷店」などが季語として使われています。
かき氷自体は平安時代から存在し、清少納言の「枕草子」にも「氷を削ってシロップをかけたもの」として登場しています。当時は氷の保存技術はないため、上流階級の人々しか口にすることのできない高級品でした。
一般に普及したのは明治初期のことで、氷水店の登場や人工氷の普及がきっかけでした。

そのため、夏氷(氷水・氷店など)は主に明治期以降から題材に見られ、現代的な題材です。
意味
この句を現代語訳すると・・・
「小さい子どもがひとさじごとにスプーンをなめて楽しんでいるな。かき氷を食べているのか。素敵な光景だ。」
という意味になります。
「匙なめて童たのしも夏氷」が詠まれた背景

こちらの句は、山口誓子が夏の風景を詠んだもので、1932年に発行された誓子の句集「凍港」に収録されています。
誓子が活躍した頃の俳句について知ると、この句がいかに斬新な句であったかが分かります。
この俳句が詠まれたころの主流は写生句と呼ばれる「物事をそのまま切り取って詠むスタイル」が一般的でした。
自分の思いを直接伝わらないようにし、読み手に考えて感じてもらう狙いがあります。題材も昔から詠み継がれてきたものが多い傾向があります。
しかし、誓子は句に叙情を持ち込み、題材も都会的な内容を使っています。
自分の思いを入れ込み、今までにない題材を扱うことで俳句の可能性を広げようという狙いがありました。
今回の句はそういった趣向を凝らし作られた句になります。
誓子は従来とは異なる表現で夏の風物詩を詠むことで、読み手が豊かに感じられるようになっています。

誓子による挑戦の句と捉えることができます。
「匙なめて童たのしも夏氷」の表現技法

詠嘆の終助詞「も」
この句では、「匙なめて童たのしも」の部分で意味が切れます。
一見「楽しもう」の「う」がないようですが、「楽しい」という形容詞に詠嘆の終助詞「も」が使われています。
(※詠嘆とは作者が強く心を動かされたこと)
ここを訳せば「匙をなめているなんて子供はなんて楽しそうにしていることだ」という意味になります。
この技法は主に短歌や古典文学で見られる技法です。
体言止め「夏氷」
最後の「夏氷」は名詞で終わる体言止めという技法を使っています。
利用法としては、体言止めは強調や余韻の効果を持たせることが多いです。
物事がどのような様子だったのか、どのようになったのかといった詳細を省くことで、読み手に続きを連想させます。
今回は夏氷と締めることで、読み手にかき氷に視点があたり、夏の風情を沸き上がらせる効果があります。
二句切れ
今回は詠嘆の終助詞「も」によって五・七・五の七で句の意味が切れます。
これを「二句切れ」と呼びます。
ただ、細かい部分を見ると句末も「夏氷」と名詞で終わっているため、上記で述べた通り体言止めが用いられています。
この体言止めは意味の切れを示すため、最後の五の部分で切れる場合は「句切れなし」と解釈されます。
一見、2か所の句切れがあるように思われます。
しかし、一般的に句切れとしては先に来た方、つまり今回は二句切れのほうが優先されます。

特に今回は終助詞という意味切れを持つ言葉を使用している点も二句切れを優先する理由になります。
「匙なめて童たのしも夏氷」の鑑賞文

【匙なめて童たのしも夏氷】は、新しい手法で日常を描くことで、誓子のほっこりとした気持ちが伝わってくる句となっています。
前半の「匙なめて童たのしも」ではひと匙ずつなめている様子がわかります。
しかし、この時点ではあまり様子がわかりません。季節はいつなのか、何を食べているのか、どのように楽しそうなのかなどはっきりしません。ぼんやりとした一連の動きと雰囲気だけが伝わってきます。
しかし、最後に夏氷と加えることで一気に様子が異なります。夏の暑い時期に少しずつ解けるかき氷をおいしそうに、でももったいなさそうに食べている様子が伝わります。
当時のかき氷はいつでも食べるものでもありませんし、どちらかというと都会で見られる光景です。
今まで詠まれることの少なかった夏氷をあえて詠むことで、夏の様子が伝わってきます。
また、ぼんやりとした情景から夏氷へ視点を絞ることで、誓子がほほえましく様子を見ていた理由がより鮮やかになります。

読み手に「子どもが食べていたのはかき氷だから、さぞかし幸せな顔でかわいいだろう」という印象を残します。
日本におけるかき氷の歴史

起源は平安時代
日本におけるかき氷の歴史は古く、その起源は今から千年以上前の平安時代にまで遡ります。
夏の風物詩として現代の私たちに親しまれているかき氷は、かつては貴族階級だけが享受できる、大変貴重で雅やかな存在でした。
その最古の記録は、上記のとおり清少納言が著した随筆『枕草子』に見ることができます。
「あてなるもの(上品なもの)」の段で、「削り氷(けずりひ)にあまづら入れて、新しき金鋺(かなまり)に入れたる」と記されており、削った氷に甘葛という蔦の樹液から作られた甘い蜜をかけ、真新しい金属製のお椀で食していた様子が描かれています。
当時は製氷技術がなく、冬の間にできた天然の氷を「氷室」と呼ばれる貯蔵庫で夏まで大切に保管していました。

このため、夏の氷は極めて希少価値が高く、かき氷は特権階級の贅沢品だったのです。
庶民への普及は明治時代から
時代が下り江戸時代末期になると、船による輸送技術が発達し、北国の氷を江戸まで大量に運ぶことが可能になりました。
これにより、氷は以前よりも少し身近な存在となり、一部の庶民も口にすることができるようになりましたが、依然として高級品であることに変わりはありませんでした。
かき氷が庶民の間に広く普及する転機となったのは、明治時代です。
文明開化とともに、日本の食文化は大きな変革期を迎えました。1869年(明治2年)には、横浜の馬車道で日本初となる氷水店が開業します。
当初はまだ天然氷が主流でしたが、明治時代に入ると製氷技術が発展し、人工的に氷を製造できるようになりました。
明治16年(1883)には東京製氷株式会社が設立され、安価で衛生的な氷の安定供給が可能となったのです。
さらに、現在のような細かく削られた氷を誰もが楽しめるようになった背景には、かき氷機の発明がありました。

明治20年代には、かき氷は夏の風物詩として庶民の間に定着し、多くの人々に涼を提供しました。
日本の夏に欠かせない文化へ
昭和に入ると、かき氷は夏の楽しみとして完全に国民的な存在となり、街角のかき氷屋は子供から大人まで多くの人で賑わいました。
千年の時を超え、雅な貴族の楽しみから庶民の涼、そして現代の創作スイーツへと姿を変えながら、かき氷は日本の夏に欠かせない文化として、今もなお人々を魅了し続けているのです。
この句に詠まれている子供は、そんな歴史は知ったことでは無いと言わんばかりに美味しそうにかき氷を食べています。

かつての高級品が、子供が喜ぶ夏の風物詩に変わっていく様子を、作者はじっと見つめているのです。
作者「山口誓子」の生涯を簡単にご紹介!
(山口誓子 出典:Wikipedia)
山口誓子(1901~1994年)。誓子は「せいし」と読み、本名は山口新比古(ちかひこ)。京都府出身。
ペンネームの由来は本名の「ちかひこ」から「誓い子」にもじったものです。
誓子の幼少期は複雑で、1908年に外祖父に預けられ日本を転々とします。
1911年に母が亡くなると、翌年に外祖父のいる樺太(現在のロシア東部の島)に移住し、1917年に日本へ帰郷します。
この樺太の頃を詠んだ句は誓子最初の句集「凍港」に収録されています。
1919年に第三高等学校(現在の京都大学)に入学すると、本格的に俳諧の道へ入ります。
写生重視の「ホトトギス」から新興俳句運動の「馬酔木」と移り活動しました。
肺の病と闘いながら、戦後は自らの句誌「天狼」を創刊し、亡くなる半年前まで主宰を務めました。
山口誓子のそのほかの俳句

( 摂津峡にある句碑 出典:Wikipedia)
- 突き抜けて天上の紺曼珠沙華
- 学問のさびしさに堪へ炭をつぐ
- かりかりと蟷螂蜂の皃(かほ)を食む
- ほのかなる少女のひげの汗ばめる
- 夏草に機缶車の車輪来て止まる
- 海に出て木枯らし帰るところなし
- 夏の河赤き鉄鎖のはし浸る
- 炎天の遠き帆やわがこころの帆
- ピストルがプールの硬き面にひびき