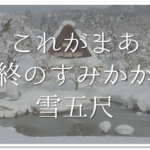「江戸の三代俳人」として活躍した「小林一茶」。
彼の作る俳句は、子供やかえる・すずめなど小さな生き物を句材にしたものが多く、親しみやすい句風は「一茶調」と呼ばれました。
一茶が生涯で残した数は約2万句にものぼるといわれていますが、その中から『雪とけて村いっぱいの子どもかな』という句を紹介していきます。
「雪とけて
村いっぱいの
子どもかな」小林一茶 pic.twitter.com/izTXitymuc
— krispy potato @ CHROM FESTIVAL (@ikaripoid) March 11, 2020
一茶がこの句に込めた情景や心情とはどのようなものだったのでしょうか。
本記事では、【雪とけて村いっぱいの子どもかな】の季語や意味・表現技法・作者など徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「雪とけて村いっぱいの子どもかな」の作者や季語・意味・詠まれた背景

雪とけて 村いっぱいの 子どもかな
(読み方:ゆきとけて むらいっぱいの こどもかな)
この句の作者は「小林一茶(こばやしいっさ)」です。
一茶の句は子どもや小動物を詠んだものが多く、松尾芭蕉や与謝蕪村の作品とは違った魅力に溢れています。
まるで童謡の世界を描いたかのようなほのぼのとした句は、今日まで多くの人々に受け入れられてきました。

この句は48歳から56歳までの9年間にわたる句日記『七番日記』に収められています。
季語
この句に含まれている季語は「雪とけて(=雪どけ)」で、季節は「春」を表します。
もし「雪」だけだとするなら季節は冬になりますが、この句の場合は「雪とけて」までが季語になります。
ゆきどけとは、春の日差しや雨で冬の間に降り積もった雪がとけていくことを意味しています。
ゆきどけを「雪融」と表記する場合もありますが、俳句では主に「雪解」が用いられてきました。

なぜならゆきどけには、雪国における積雪の不便さからの解放感も込められているからです。
意味
こちらの句を現代語訳すると・・・
「雪解けの季節を迎えて、待ちかねていたかのように子供たちが外へ飛び出し、村中で遊んでいることだ」
という意味になります。
この句が詠まれた背景
一茶がこの句を詠んだのは52歳にして結婚を目前に控えた、文化11年の早春の頃です。
それまでは江戸で暮らしていましたが、50歳で永住を覚悟し故郷に帰ってきました。
故郷である信濃国柏原(現在の長野県信濃町)は日本でも有数の豪雪地帯であり、冬になると大人でさえもすっぽりと雪に埋もれてしまうほどでした。
一茶は柏原の雪について「これがまあ終の栖か雪五尺」という句を残しています。
現代語訳すると「(五尺(※約150cm)にもなる深い雪、この地が自分の最期のすみかとなるのかと思うと、深いため息がわいてくるなぁ」となり、どれほど雪深い地域であったかがわかります。
おそらく江戸では見られなかったであろう、雪国ならではの懐かしい光景に、思わず一句詠みたくなったのでしょう。
また現代と違い、かつての山間部での生活は厳しいものでした。冬を迎えるとまともなタンパク質が摂取できず、栄養失調や飢え、寒さによって多くの子ども達が命を落としていた時代です。

そんな中でも無事に春を迎え、元気な子供たちが大勢いることに、一茶はよりいっそう心を打たれたのではないでしょうか。
「雪とけて村いっぱいの子どもかな」の表現技法

「子どもかな」の切れ字(句切れなし)
切れ字には「かな」「けり」「や」などの語があり、句の流れを断ち切り、作者の感動の中心を効果的に表します。
この句では「子どもかな」に、感動や詠嘆の意を表す「かな」が用いられています。
「かな」はもっぱらに句の最後で使われ、「子ども」のように名詞のあとにつけれらるられることが多い切れ字です。
また切れ字が含まれる句、または句点「。」がつく場所を句切れといいます。この句だと句の末尾に「かな」がついているので、「句切れなし」と呼びます。
「子どもかな」と詠むことで、「村の中はどこもかしこも、元気に遊ぶ子どもたちでいっぱいだなぁ」と詠嘆の意味が込められています。

待ちに待った遅い春への喜びが、子ども達の明るい笑顔や笑い転げる賑やかな様子で表現されています。
「雪とけて村いっぱいの子どもかな」の鑑賞文

暦の上では春を迎えていても、雪国ではまだまだ寒い日が続きます。降り積もった雪が少しずつ解けはじめて、ようやく春の気配を感じることができました。
冬の間、子どもたちは外で遊ぶこともできず、それまで我慢強く家の中で春を待ち続けていました。まだ寒さは残るものの、久しぶりに見た土の上で、思いっきり体を動かせるのは何にも変えがたい喜びだったことでしょう。
あちらこちらから子ども達が飛び出し、今までどこにこんなのたくさんの子どもがいたのかと驚くほどでした。春の明るい日差しをあびて、村中が活気に満ちてくる様子がありありと感じとれます。
風流を愛でるこの時代、春の訪れを草木の芽吹きなどに詠みこむ句は数多くありましたが、いっせいに外に飛び出してきた「子ども」の姿で表現しているところがいかにも一茶らしい句だといえます。

一茶は木の芽や花よりも、雪国で元気に暮らす子ども達にこそ感銘を受けたのでしょう。子どもに向ける一茶の優しさが伝わってきます。
「雪とけて村いっぱいの子どもかな」の補足情報

一茶の故郷と雪
この句は文化11年(1814年)に一茶の故郷で詠まれた俳句です。
一茶の故郷は現在の長野県信濃町柏原です。柏原は現在でも豪雪地帯として知られており、2月下旬に170cmを超える積雪があったことでも知られています。
「雪とけて」の句で、雪解けを迎えて喜んで走っていく子供たちの様子を理解するには、この地が豪雪地帯であったことを念頭に置く必要があるのです。
また、文化14年の柏原の記録も残っており、702名が住んでいたことがわかっています。

そのうちの何人が子供だったのか、どのくらいの子供たちが「雪とけて」の句で走っていったのか、想像してみるとおもしろいですね。
「雪解け」に込められた想い
ここで詠まれている「雪解け」は、上述の通り雪深い故郷に春が訪れた喜びの象徴でしょう。
しかし、詠まれた文化11年という年代にも意味が隠されていると考える説があります。
一茶は10年以上もの長い間、継母と弟を相手に遺産分割を原因とした争いを抱えていたことで知られています。
父の死の6年後から本格的に遺産分割の協議を始めていますが、弟側は断固拒否の構えを貫いていました。
一茶自身が老いを感じていたこともあり、俳人としての生活よりも地に足をつけた生活をするために、遺産が必須だったためと考えられます。
一茶は当時江戸に住んでいましたが、故郷である柏原で起きていた裁判沙汰のサポートを積極的に行っていました。
このことで故郷の有力者とのパイプを作り、最終的に文化10年にようやく長い遺産争いし終止符を打ち、文化11年2月に遺産の分割が実現しました。
「雪とけて」の句が詠まれたのは、まさにその文化11年の春です。このことから、「雪解け」は春の訪れを表すとともに、長い弟との争いを終え、地に足がついた生活を送ることができるようになった喜びを詠んだものとも考えられます。
因みに、「村いっぱいのこども」の中に一茶が自分の子を見ていたという解釈もありますが、この時は一茶はまだ子供がいません。

一茶に第1子が誕生するのは2年後の文化13年以降なので、俳句の解釈をする際は詠まれた時と場所、状況を調べておきましょう。
作者「小林一茶」の生涯を簡単にご紹介!

(小林一茶の肖像 出典:Wikipedia)
小林一茶(1763-1827年)は本名を小林弥太郎といい、信濃国(現在の長野県)の農家に生まれました。
一茶が3歳の頃生母が亡くなり、5年後父の再婚で迎えた継母とはうまく馴染めませんでした。
その後唯一の味方であった祖母も他界し、15歳で長男にもかかわらず江戸へ奉公に出されました。
この継母との確執は、一茶の性格や句へも大きな影響を与えたといわれています。
奉公先で俳諧に出会い、二六庵小林竹阿や今日庵森田元夢らに師事して俳句を学びます。非常に苦しい生活のため、この期間の記録はほとんど残されていません。
29歳の頃14年ぶりに故郷に帰った一茶は、倒れた父親の最後を看取ります。父は財産を一茶と弟達で二分するよう遺言を残しますが、継母たちが反対したため遺産相続争いは12年もの間続きました。
その後、継母たちと和解し故郷に定住することになった一茶は、52歳にして初婚を迎えます。
その後二度結婚し子供を5人授かりますが、最後に生まれた娘を除き、全て幼いうちになくなっています。家庭にも恵まれず、65歳で亡くなる数ヶ月前には自宅が火事で焼失するなど、生涯を通して不遇ともいえる人生を送りました。

このような人生の苦闘を経験してきた一茶はだからこそ、「花鳥風月」よりも「生」をテーマとして写実的な句を詠みつづけました。
小林一茶のそのほかの俳句