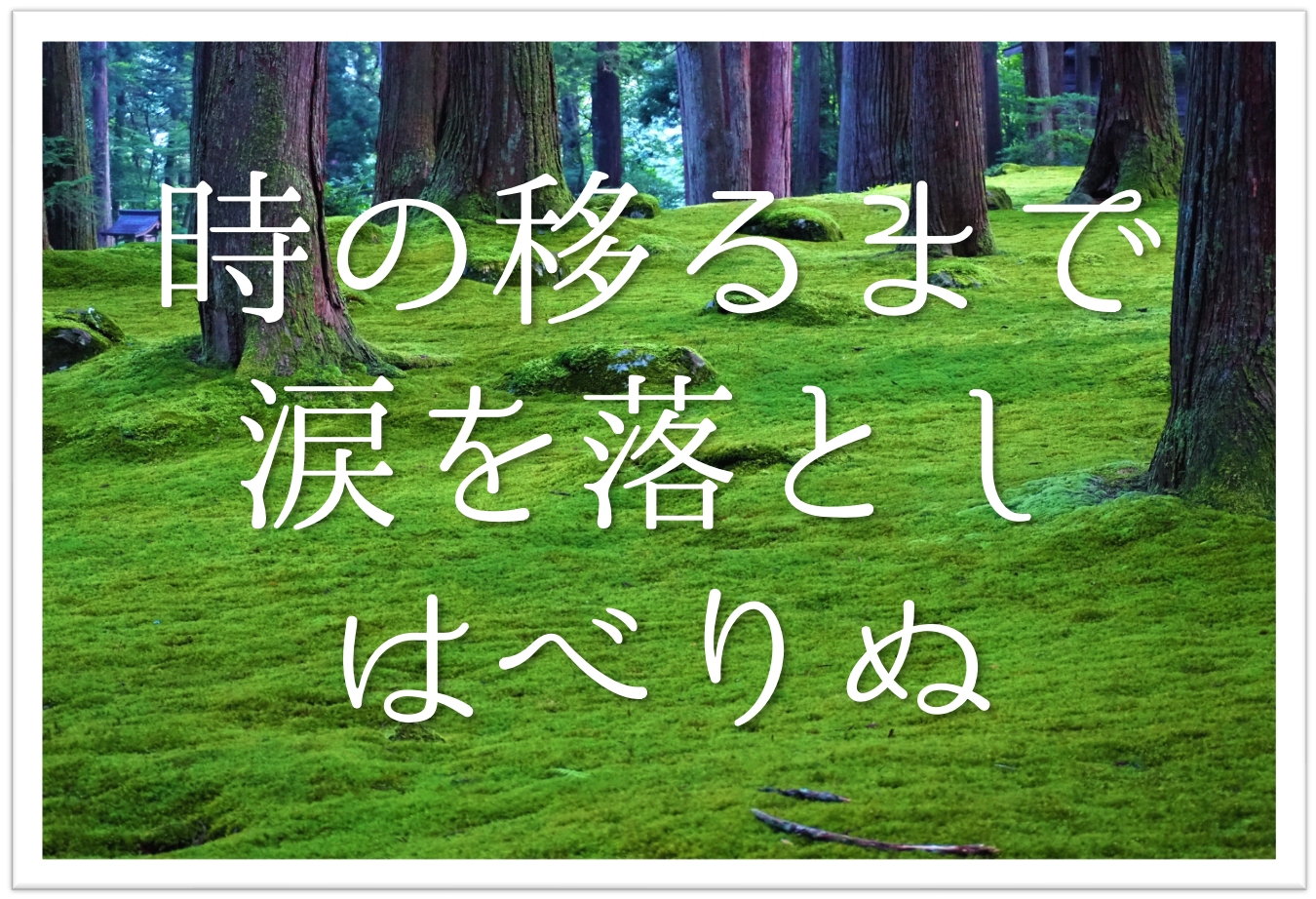
「古池や蛙飛び込む水の音」など、数々の優れた俳句を残した人物として有名な松尾芭蕉。
松尾芭蕉は、俳句以外にも『奥の細道』などの有名な作品も残しています。
そこで今回は、『奥の細道』に出てくる有名なフレーズ「時の移るまで涙を落としはべりぬ」の意味や背景などを徹底解説していきます。
ここで時の移るまで涙を落とし侍りぬ pic.twitter.com/CQMTUJ0cqy
— あやつじ (@ayqtsuji) December 23, 2014
目次
「時の移るまで涙を落としはべりぬ」は紀行文『奥の細道』をの有名フレーズ!

(奥の細道行脚之図 芭蕉"左"と曾良"右" 出典:Wikipedia)
「時の移るまで涙を落としはべりぬ」という有名なフレーズは、松尾芭蕉の『奥の細道』という作品の中で出てきます。
『奥の細道』は紀行文というジャンルの作品で、旅の記録をつづった文章です。
元禄2年(1689)、松尾芭蕉が46歳の時、門人の河合曾良と共に江戸を出発し、奥州、北陸道を約150日間かけて巡りました。この「旅の様子」や「旅先で詠んだ俳句」が『奥の細道』にはつづられています。
松尾芭蕉と門人の曾良は、敬愛していた歌人の西行や能因がたどった名所や旧跡を巡りながら、多くの俳句を詠みました。
「時の移るまで涙を落としはべりぬ」の意味や背景

【奥の細道/有名なフレーズ】
時の移るまで涙を落としはべりぬ
(読み方 : ときのうつるまでなみだをおとしはべりぬ)
意味
こちらのフレーズを現代語訳すると…
「時が移るまで涙を落としてしまった。」
となります。
「時が移る」は「時間が経つ」、「涙を落とす」は「涙を流す」ということを表していると考えられます。よって、このフレーズは「誰かがしばらくの間涙を流した」ということやその様子を意味するものということになります。
いったい誰が、なぜ、泣いているのでしょうか。
背景

(写真:平泉の覆堂)
「時の移るまで涙を落としはべりぬ」というフレーズは、松尾芭蕉と門人の曾良が「平泉(ひらいずみ)」という場所を訪れた際の様子がつづられた部分に出てきます。
平泉は岩手県南部にある土地で、平安時代に奥州藤原氏一族が治めた地でした。
特に藤原清衡、基衡、秀衡の親子3代の時に最盛期を迎えました。しかし、その栄華は長くは続かず、藤原秀衡は源頼朝に滅ぼされてしまいました。
奥州藤原氏ゆかりの土地である平泉に訪れた松尾芭蕉と門人の曾良。平泉を巡りながら二人は俳句を詠みますが、松尾芭蕉は思わず涙を流してしまったのです。

(奥州藤原氏三代像 出典:Wikipedia)
松尾芭蕉の涙の理由は?

松尾芭蕉が涙を流した理由には、平泉という場所が深く関わっています。
かつては奥州藤原氏が栄華を極め、治めていた平泉。しかし、松尾芭蕉と門人の曾良が訪れた時の平泉は草が青々と生い茂り、かつて栄えていた場所とは思えないような景色が広がっていました。松
尾芭蕉はこの景色から、中国の詩人である杜甫が「人間の栄華の儚さ」について詠んだ漢詩を思い起こします。
この時の様子が『奥の細道』には次のようにつづられています。
「国破れて山河あり、城春にして草青みたりと、笠うち敷きて、時のうつるまで涙を落としはべりぬ」
松尾芭蕉は、「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」という杜甫の漢詩の冒頭を思い起こし、旅の笠を脱ぎ置いて、しばらく涙を流しました。
松尾芭蕉は平泉の景色を見て、杜甫と同じように人間や人間の社会の儚さを強く感じて涙を流したのです。
『奥の細道』の旅で詠まれた俳句

松尾芭蕉は『奥の細道』の旅の中で、多くの俳句を詠んでいます。
「時の移るまで涙を落としはべりぬ」というフレーズが出てくる平泉を訪れた際には、「夏草や兵どもが夢の跡」という俳句を詠みました。
この俳句は、かつて奥州藤原氏が栄華を極めた平泉が今では「草が生い茂る場所=夢の跡」となってしまったことを詠んだ句です。松尾芭蕉は平泉で人間の儚さを感じずにはいられませんでした。
また、松尾芭蕉と共に旅をした門人の曾良は、平泉で「卯の花に兼房見ゆる白毛かな」という俳句を詠んでいます。
「兼房」は増尾兼房のことで、源義経の家臣であり、老齢でありながら主君のために忠義を尽くしたとされる人物です。曾良は、白髪を振り乱して藤原氏一族と戦った兼房の姿を、真っ白な卯の花に重ねて詠んだのです。
松尾芭蕉は、平泉以外の場所では次のような俳句を詠んでいます。
- 「行く春や鳥啼き魚の目は泪」
- 「閑かさや岩にしみいる蝉の声」
- 「五月雨を集めて早し最上川」
- 「あかあかと日はつれなくも秋の風」
- 「雪の峰いくつ崩れて月の山」
松尾芭蕉について簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)
松尾芭蕉は、江戸時代の俳諧師です。
19歳の時に北村季吟の門人となり、俳諧の道へ進みました。そして、のちに俳諧の芸術性を高め、「蕉風俳諧」を確立しました。
なお、俳諧とは江戸時代に栄えた「俳諧連歌」のことで、一首の短歌の上の句(五・七・五)と下の句(七・七)を二人以上で詠み合い、繋げていくものでした。よって、松尾芭蕉が詠んでいたのは、正確には「俳句」ではなく「発句」という俳諧連歌の最初の一句目(五・七・五)です。
「俳句」が生まれたのは明治時代であり、歌人の正岡子規が「発句は文学なり」と主張し、五・七・五だけで表現する「発句」を「俳句」と呼ぶようになりました。「俳句」という言葉が生まれたのは明治時代ですが、五・七・五だけで情景や心情を詠むということを松尾芭蕉は江戸時代から行っていました。
松尾芭蕉は、『奥の細道』以外にも、『野ざらし紀行』『鹿島詣』『更科紀行』などの紀行文を書いており、多くの旅をしています。松尾芭蕉は旅を愛した人でした。
『奥の細道』の序文には、以下の言葉がつづられています。
「月日は百代の過客にして、行かふ年もまた旅人なり。」
(=月日は永遠の時間を旅する旅人のようなもので、やって来ては去って行く年月もやはり旅のようなものだ)
「予もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて、漂泊の思ひやまず、」
(=私もいつの年からか、ちぎれ雲を吹き漂わせる風に誘われるように、あてもなく旅をしたい気持ちが抑えられず、)
松尾芭蕉は「人生は旅」という風に考えており、実際に多くの旅をしました。
『奥の細道』の旅に出たのは松尾芭蕉が46歳の時であり、当時としてはかなり高齢でもあったことから、松尾芭蕉は「もう戻ることはないかもしれない」という気持ちで住んでいた家を人に譲り、命がけの旅に出たのでした。
旅を愛し、日本各地を歩き回って様々な風景を見てきた松尾芭蕉だからこそ、多くの優れた俳句を詠むことができたのです。



















