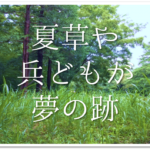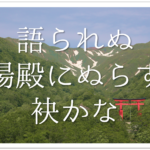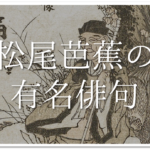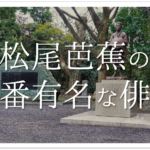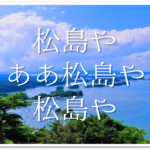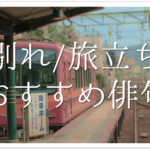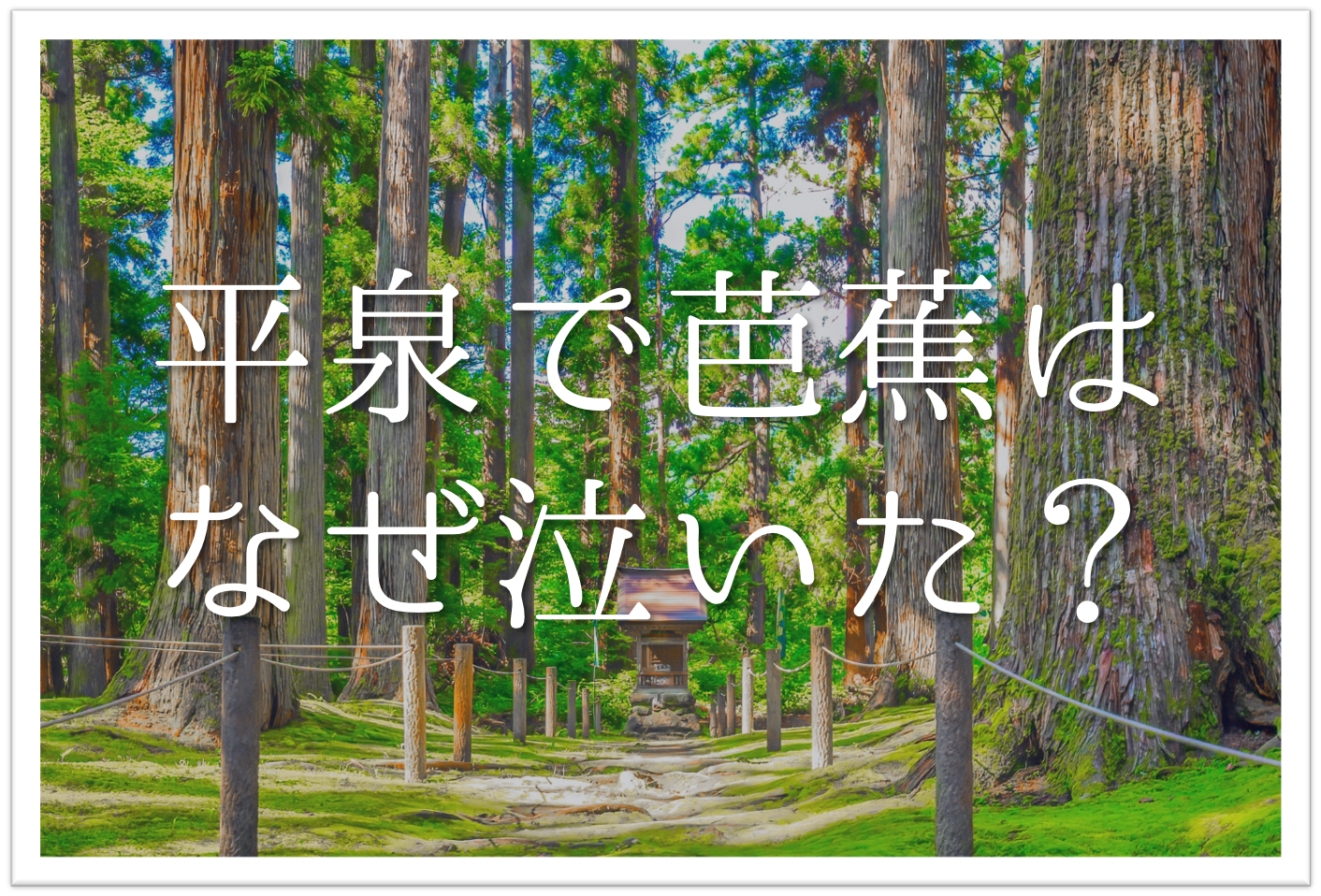
俳句は、五・七・五の短い音で詠み手の感動や意図を伝えることができます。
詠み手がどういった背景で、その句を詠んだのか想像してみることも楽しみの一つです。
本記事では、平泉で芭蕉はなぜ泣いたのか、そして「おくのほそ道」に出てくる松尾芭蕉のエピソードを簡単にわかりやすく解説していきます。
3月の東北旅行の最終目的地は平泉・中尊寺
おくのほそ道の旅においてここを訪れ涙を流したという芭蕉に思いを馳せながら回りました
なんといっても金色堂は圧巻でした pic.twitter.com/nYfcsHDY28— こへ@写真垢 (@thinceller_pic) May 2, 2015

ぜひ参考にしてみてください。
目次
奥の細道の平泉で芭蕉はなぜ泣いた?

(「奥の細道行脚之図」の芭蕉と曾良)
【回答】松尾芭蕉は、「源義経・義経を守るために戦った家臣たちへの無念さ」「藤原家の栄枯盛衰」へ思いをはせ、平泉で涙を流しつづけた。
松尾芭蕉は、俳句を芸術の域にまで高めた江戸時代の俳諧師の一人です。
小林一茶や、与謝蕪村などと並び日本で最も有名な俳諧師の一人とされています。代表作は「おくのほそ道」です。
そもそも奥の細道とは

中学校の国語の教科書でもおなじみの「おくのほそ道」ですが、どういった作品か簡単にご紹介します。
「おくのほそ道」は松尾芭蕉が46歳の頃に、弟子の河合曾良(そら)を伴い江戸を発ち、5か月かけて東北から北陸を経て美濃国の大垣まで、行程2400㎞の旅を記した紀行文です。
ちなみに、弟子の河合曾良も旅において旅の詳細をつづった「曾良旅日記」を記しています。
「おくのほそ道」は奥州の「奥」であり、東北地方をさします。
奥州は陸奥やみちのく、つまり道の奥で、この国の遠い果ての地だと考えられていました。
そのような地方へ、たよりにならないような細い道を旅していく、ということから「おくのほそ道」と名付けられています。

松尾芭蕉が生きている時代は、現在のように通信、医療、インフラなどが整備されておらず、旅は命がけで出かけるものでした。
それでも芭蕉がこの旅に行きたい目的は、日本三景のひとつである「松島」や藤原三代の都であった「平泉」を訪ねることでした。
特に平泉の地は、松尾芭蕉が尊敬している西行法師が人生で2度も訪れた土地とあり、旅の大きな目的地でした。
旅の大きな目的地・藤原三代の都「平泉」

(毛越寺の浄土庭園 出典:Wikipedia)
松尾芭蕉があこがれた地、平泉とはどのような場所だったのでしょうか。
1094年に藤原清衡(きよひら)が居城を建築してから、約100年にわたって2代基衡(もとひら)、3代秀衡(ひでひら)が治め平泉文化として栄えました。

(奥州藤原氏三代像 出典:Wikipedia)
藤原家は京都の都と非常に関係が深く、馬や平泉で採掘がされていたとされる金を朝廷に献上していました。
平泉文化は京風の文化であったといわれています。
平安末期、鎌倉幕府を開いた源頼朝から追われた源義経が潜伏しましたが、1189年、4代泰衡(やすひら)は義経を大将とするようにという秀衡の遺言にもかかわらず、義経を自害に追い込みます。
その後、義経をかくまったとして源頼朝軍が奥州を攻め、藤原家は滅亡してしまいます。

平泉には、中尊寺をはじめとした建築物が残されており、2011年に世界文化遺産に登録されました。
松尾芭蕉が涙を流した理由

松尾芭蕉は、平泉に到着すると源義経が居城を構えていた高館にのぼりました。
高館は、義経が最期を迎えた場所です。
約500年後に芭蕉が訪れたときには、見渡しても田畑や青々と草の茂る野原が広がっており、藤原家の栄華をきわめた痕跡は、なくなってしまっていました。
奥のほそ道の原文は・・・
「さても義臣すぐつて此城にこもり、功名一時の叢となる。「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と笠打敷て、泪を落とし侍りぬ」
と書かれています。
源義経は弁慶などのわずかな家臣を選び、この高館の城にたてこもり、最後の戦いを繰り広げました。弁慶などの義経に仕えた家臣たちは忠義をつくして懸命に戦いましたが、敗れ散っていきました。
ここで、芭蕉は中国人の杜甫の詩「春望」の一節「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と口ずさんでいます。
(※意味:国が滅びても山河は昔のままであり、城跡にも春になると青草が生い茂っている。)

芭蕉は、時間の流れ去るのもかまわず、笠を置いたまま栄枯盛衰へ思いをはせ、涙を流しつづけました。
松尾芭蕉は、義経、そして義経を守るために戦った家臣たちを思い、その無念さや、藤原家の滅亡など数々の命が栄え、そして消えていったことを思ったかもしれません。
高館からは、北上川の流れが見え、青草が茂り、人々の痕跡は消え去っても雄大な自然は昔と変わらなかったのではないでしょうか。

人の世の無常に思いをはせて涙を流した様子が想像できます。
「夏草や兵どもが夢のあと」に込められた思い

松尾芭蕉はこの地で「夏草や兵どもが夢のあと」という句を詠んでいます。
この句は、「今や夏草が生い茂るばかりだが、かつて、武士たちが奮戦した跡地である。昔のことはひとときの夢となってしまった。」という意味です。
義経を一生懸命に守るために戦った家臣たち、最後には源頼朝に滅ぼされる藤原家、繰り広げられた数々の戦いも長い歴史のなかでは、あとかたもなく消え去り、はかない夢のあとにはただ夏草が茂っているという様子です。
散っていった命を思いながら、夏草は武将たちがいた昔と変わらずに青々と生い茂っている、人のはかなさ・むなしさと対比して変わらない雄大な自然の姿も詠んだ、芭蕉の代表作の一つです。
芭蕉が涙(泪)を流した回数は「5回」

『おくのほそ道』では、平泉の項目以外にも何箇所か芭蕉が涙を流す場所が出てきます。
全部で5回出てきていて、そのうちの一つが平泉です。

ほかは、どのような場面で涙を流しているのか見ていきましょう。
①旅立ち
深川にある芭蕉庵から旅立ち、見送りに着いてきてくれていた人たちと千住の渡しで別れた時に最初の涙を流しています。
「千住といふ所にて舟をあがれば、前途三千里のおもひ胸にふさがりて、幻の巷に離別の涙をそそぐ。」
(訳:千住という所で舟から降りれば、前途三千里もあるだろうという思いに胸が塞がって、この世との別れのように離別の涙が浮かんでくる。)
②飯塚の里
藤原秀衡に仕えた佐藤庄司の旧跡があると聞き、寄り道をしています。
今はただの丸山という小さな山になった旧跡に、大手門の跡や石碑などの往時痕跡を見つけて涙する様子は、平泉の項目と近い印象です。
「これ庄司が旧館也。麓に大手の跡など人の教ふるに任せて泪をおとし、又かたはらの古寺に一家の石碑を残す。」
(訳:これが佐藤庄司の館の跡だ。麓に大手門の跡があるなど人に教えられて涙を流し、また傍らにある古寺に佐藤家の石碑が残っている。)
③壺の碑
多賀城市には、「壺の碑」という聖武天皇の頃に作られた碑があり、古くからの歌枕になっていました。
この碑を見た芭蕉は、「千歳の形見である」と涙を流していて、同じ言葉を使った中尊寺金色堂では淡々と綴っていたのとは全く違う反応をしています。
「行脚の一徳存命の悦び、羇旅の労を忘れて泪も落つるばかりなり。」
(訳:旅をすればこその果報であり、生きていればこその喜びである。旅の苦労も忘れて涙も落ちそうになる。)
④出羽三山
出羽三山では、湯殿山詣での時に涙を流しています。
湯殿山詣では現在でも詳細を話してはいけない、写真を撮ってはいけないなど戒律の厳しい場所で、詳しいことは書かずに尊さに涙したとだけ詠んだ場所です。
「語られぬ 湯殿にぬらす 袂かな」
(訳:語ることはできないが、湯殿山の尊さに袂を涙でぬらしているなぁ。)
⑤金沢
金沢では、唯一人の死に涙を流す句を詠んでいます。
門弟に会うことを楽しみにしていたところ、既に亡くなってしまったことを知り、追悼の句を詠んでいるシーンです。
「塚も動け 我が泣く声は 秋の風」
(訳:塚も動いてくれ。私が泣く声は秋の風にのって響いている。)

以上、上記の5つの場面で松尾芭蕉は涙を流しています。
作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)
松尾芭蕉は1644年伊賀国上野、現在の三重県伊賀市に生まれました。
本名は松尾忠右衛門、のち宗房(むねふさ)といいます。
13歳のときに父親を亡くし、藤堂家に仕え10代後半の頃から京都の北村季吟に弟子入りし俳諧を始めました。
俳人として一生を過ごすことを決意した芭蕉は、28歳になる頃には北村季吟より卒業を意味する俳諧作法書「俳諧埋木」を伝授されます。
若手俳人として頭角をあらわした芭蕉は、江戸へと下りさらに修行を積みました。40歳を過ぎる頃には日本各地を旅するようになり、行く先々で俳句を残しています。
46歳の時に弟子の河合曾良(そら)を伴い江戸を発ち、東北から北陸を経て美濃国の大垣までを巡った旅を記した紀行文『奥のほそ道』が特に有名です。
150日間で行程2400㎞を旅したことや、生まれが伊賀であったことから、忍者ではなかったかという説が出たこともあります。
芭蕉は「おくのほそ道」の旅から戻り、大津、京都、故郷の伊賀上野などあちこちに住みました。
そして1694年、旅の途中大阪にて体調を崩し51歳にて死去しました。
さいごに

松尾芭蕉は、人生最後の旅となるかもしれないという思いで、「奥の細道」の旅へのぞみました。
今回、スポットをあてた「平泉」は奥の細道のなかでもクライマックスの一つとされています。平泉は2011年には世界文化遺産に登録されています。
松尾芭蕉が思いをはせ、涙を流した場所を、時を経て現代の私たちが旅をしてみるのもいかがでしょうか。