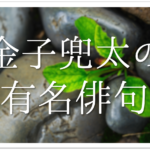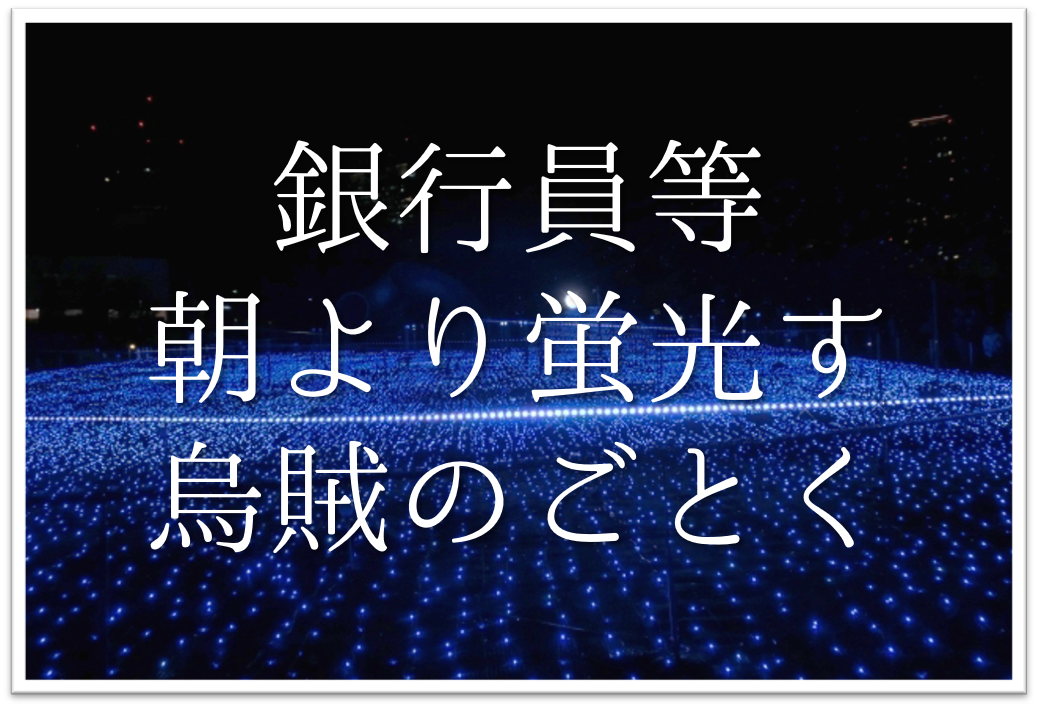
わずか17音で描かれる世界観が美しい「俳句」。
日本が生み出した芸術ですが、今や世界中の人々から愛され親しまれています。
今回は、日常生活の情景を詠んだ句「銀行員等朝より蛍光す烏賊のごとく」という句を紹介していきます。
おはようございます🍁#勤労感謝の日
『銀行員等朝より蛍光す烏賊のごとく』
金子兜太今となっては懐かしい昭和のエリート銀行員の朝からパリッとして意気揚々と働く姿
元々収穫した五穀などを神に供えて感謝ニャー😸
良い日になりますようにブヒ🐗 pic.twitter.com/v3PwbnVkku
— とりあん (@torian48) November 22, 2019
本記事では、「銀行員等朝より蛍光す烏賊のごとく」の季語や意味・表現技法・鑑賞・作者について解説させていただきます。

目次
「銀行員等朝より蛍光す烏賊のごとく」の作者や季語・意味

銀行員等 朝より蛍光す 烏賊のごとく
(読み方 : ぎんこういんら あさよりけいこうす いかのごとく)
この句の作者は、「金子兜太(かねこ こうた)」です。
兜太氏は、昭和から平成にかけて活躍した前衛俳句の俳人です。
意味
こちらの句を現代語訳すると・・・
「銀行員たちが朝より蛍光している。まるでイカのようだ。」
となります。
この作品が詠まれる前日に作者は家族と足を運んだ尾道の水族館にて、蛍イカを見学しています。

季語
こちらの作品は自由律俳句となりますので、季語はありません。
五・七・五の音律や季語にとらわれず、作者が見たままの情景をストレートに詠んでいます。

解釈
作者は、かつて日本銀行に勤めていた銀行員であり、朝職場に出勤した時の様子を詠んだ作品です。
「蛍光灯の光が働いている職員に反射し、その姿はまるで蛍イカのようである」と作品を通じて伝えています。
さらに深く解釈すると、「朝出勤してみると暗い室内の中で銀行員達が、今日も頑張るぞと仕事に燃えている。その後ろ姿には蛍光灯の灯りが反射し、その様子は自ら光を発光する蛍イカのようである。」とも読み取れます。
「銀行員等朝より蛍光す烏賊のごとく」の表現技法

(身投げしたホタルイカ 出典:Wikipedia)
比喩(直喩法)「烏賊のごとく」
こちらの作品では、直喩法と呼ばれる比喩技法が使われています。
直喩法とは「ーごとく」「ーごとし」「ーようだ」という風に「AをBに例えて」、「まるで●●のようだ」と表現する技法です。
直喩法を使用することによってイメージしやすくなり、作者が意図することが伝わりやすくなります。
こちらの作品では、蛍光灯の灯りの中で仕事をしている銀行員の姿が、まるで蛍イカのようだと例えており、その場の情景が読み手に伝えわりやすいようになっています。
自由律俳句
こちらの作品は、自由律俳句です。
自由律俳句とは、俳句の定型「5・7・5」の形に捉われずに、自由なスタイルで自分の心情をストレートに読む技法です。また、自由律俳句は季語を入れる必要がないという点もポイントです。
この句は五・七・五の音律から外れており、季語も含まれていません。
作者が見たままの情景をストレートに詠んでおり、どのような職場の風景であるかがダイレクトに伝わってきます。
「銀行員等朝より蛍光す烏賊のごとく」の鑑賞文

家族で休日を水族館で過ごした日の翌日出勤すると、いつもとは違う光景が広がっています。
デスクに向かい、一生懸命仕事をする銀行員の背中には蛍光灯の光が反射し、まるで昨日見た蛍イカが光を放っています。
そんな異様な雰囲気を作者は感じ取り、私たち読み手にわかりやすく伝えています。
一見すると読み手側は「不気味な風景」と感じますが、同僚達を蛍いかに例える趣向にはユーモアが感じられます。
また、小さな体で力強く光を発効する蛍イカは、エネルギッシュで力強い生き物です。

「銀行員等朝より蛍光す烏賊のごとく」の補足情報

外はどれだけ暗かったのか?
この句の一番のポイントは、「まだ薄暗い中、蛍光灯をつけて仕事をしている同僚がホタルイカに見えた」という点で、どのくらいの暗さの中で蛍光灯が輝いていたかでしょう。
暗い中で煌々と明かりが輝いていればホタルイカのほのかな輝きには見えず、完全に日が昇ってしまえば、蛍光灯の明かりが目立たなくなります。
そうなると日の出前後ですが、4月から5月の日の出の時刻は5時頃から4時半とどんどん早くなっています。
外との明るさの対比を考えると遅くとも5時半頃となり、作者もかなり早い時間帯に出勤していることがわかる一句です。

蛍光灯の色はどんな色だった?
現在ではLEDが主流で、蛍光灯をあまり見た事がない人も多いのではないでしょうか。
蛍光灯は、放電により飛び出した電子がガラス管内に封入された水銀の原子に衝突することで発生した紫外線を、ガラス管内面に塗布した蛍光体に当てて光に変換するものです。
色も蛍光灯によって少しずつ違っています。
- 青みが強く、晴天の正午の日光の色に例えられる【昼光色】。
- 晴天の正午をはさんだ時間帯の日光の色に例えられる【昼白色】。
- 薄い黄緑色にも見える日の出2時間後の日光の色とされる【白色】。
- 夕方の日光の色のような【温白色】。

作者と日本銀行
1949年から翌年末にかけて、日本銀行労働組合の専従初代事務局長を務め、1950年末に福島支店、1953年に神戸支店、1958年に長崎支店へ転勤ののち、1960年に東京の本店に戻っています。
「窓際族ではなく、窓奥。1日2-3回開けるだけの本店の金庫番」と評しつつ、1974年の定年まで勤めました。

作者「金子兜太」の生涯を簡単にご紹介!

(金子兜太 出典:Wikipedia)
金子兜太は、1919年9月23日に埼玉県比企郡小川町の母の実家にて生まれました。
父は開業医かつ俳人であり、水原秋桜子が主宰の「馬酔木」に所属。また秩父音頭の復興者です。
兜太は、高校時代に俳句に目覚め、勢力的に句作に励みました。
1941年に東京帝国大学に進学し、加藤楸邨主宰の指導を受けます。
卒業後は日本銀行へ入行し、戦後の1947年に塩谷皆子と結婚。沢木欣一主宰の「風」に参加し、社会性俳句運動に共鳴して活動します。
『俳句誌』にて自らの持論『俳句造型論』を展開。1958年には新俳句人連盟の中央委員長に就任し、1960年からは前衛俳句の普及に貢献。その後は上武大学教授、現代俳句協会名誉会長、日本芸術院会員を務めます。2018年2月6日に享年100歳にて逝去します。
銀行員等朝より蛍光す烏賊のごとく
即物性とリリシズムが同居したような句風が好きでした。天寿を全うされました。ご冥福をお祈り申し上げます …
訃報:金子兜太さん98歳=俳人 前衛俳句、戦後をリード - 毎日新聞 https://t.co/aGvtmqER6T— ゼロワン (@seasidebound01) February 20, 2018
金子兜太のそのほかの俳句

- 彎曲し火傷(かしょう)し爆心地のマラソン
- 湾曲し火傷し爆心地のマラソン
- 暗黒や関東平野に火事一つ
- 水脈(みお)の果(はて)炎天の墓碑を置きて去る
- 人体冷えて東北白い花盛り
- 霧の村石を投(ほう)らば父母散らん
- 梅咲いて庭中に青鮫が来ている
- おおかみに蛍が一つ付いていた
- 夏の山国母いてわれを与太という