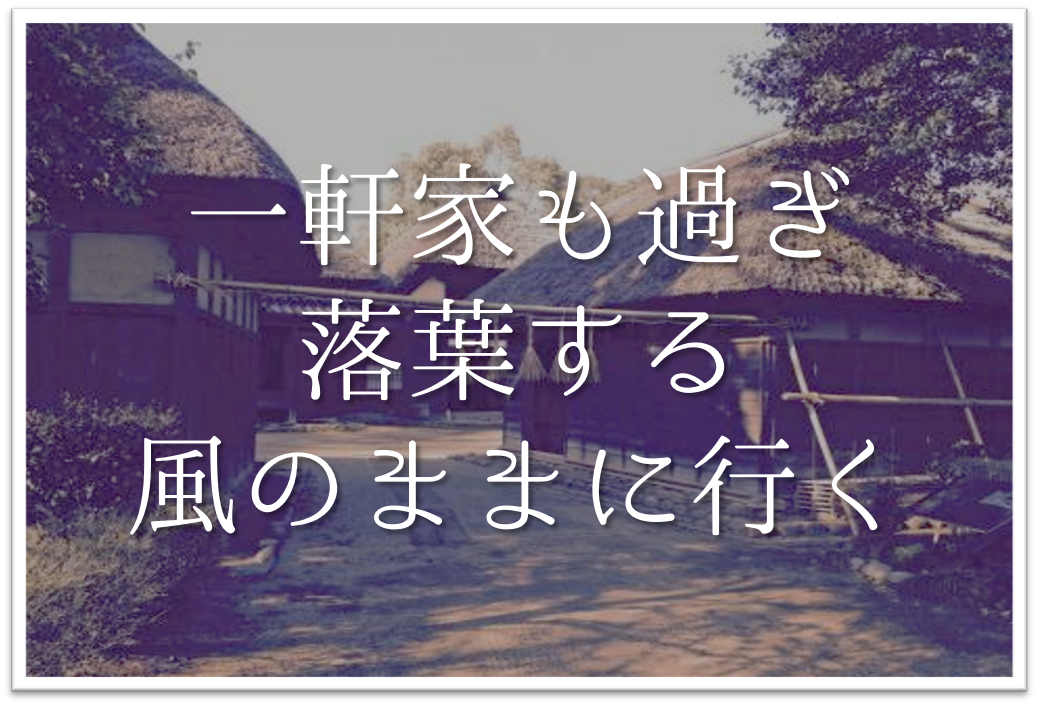
俳句と言えば、五・七・五の十七音で作られ、季語を入れ「かな」「や」「けり」などの言葉がつくもの、というイメージが強いと思います。
もちろん多くの句は有季定型句といい、季語を持ち五・七・五のリズムを基本として自然美などを情感豊かに詠みあげるものです。
しかし、一部の俳人は自由な形の俳句「自由律俳句」を模索しました。自由律俳句は季語にこだわらず、定型にもこだわらず、感情の動きを自由な言葉で表す俳句です。口語で詠まれることも多いです。
今回はそんな自由律俳句の中から「一軒家も過ぎ落葉する風のままに行く」という河東碧梧桐の句をご紹介します。
一日一言 2/1
今日は、河東碧梧桐 (かわひがし へきごとう、1873-1937)が死んだ日です。本名:秉五郎(へいごろう)。俳人・随筆家。正岡子規に俳句を学び、高浜虚子と共に「子規門下の双璧」と呼ばれました。
河東碧梧桐https://t.co/fIFlxqocix#一日一言 #河東碧梧桐 pic.twitter.com/vgsIGbQ0KE
— さびたん33 (@jawakahiko) January 31, 2018
本記事では、「一軒家も過ぎ落葉する風のままに行く」の季語や意味・表現技法・作者について徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
「一軒家も過ぎ落葉する風のままに行く」の作者や季語・意味・詠まれた背景

一軒家も過ぎ 落葉する 風のままに行く
(読み方:いっけんやもすぎ おちばする かぜのままにゆく)
こちらの句の作者は「河東碧梧桐」です。
季題、音数にとらわれることのない、ルールに縛られない「無季自由律の俳句」になります。
明治時代、日本の文学の在り方も変わろうとする中、和歌や俳句といった韻文の変革の活動をした正岡子規の高弟です。
子規の死後、俳句の新しい可能性を常に追い求め、新傾向の俳句の第一人者となりました。
季語
俳句のセオリーでいえば「落葉」が冬の季語になります。
詰まりのこの句は冬の光景を詠みこんだ句なのです。
しかし、この句は「自由律俳句」。作者によって季語を意識して詠まれているわけではありません。
意味
こちらの句を現代語訳すると・・・
「集落のはずれの一軒家すらも、もはや通り過ぎてしまい、落ち葉舞を舞わせる風と共にすすんでいくことだ。」
という意味になります。
俳句が詠まれた背景
こちらの句は、大正13年ころ(1924年ころ)に詠まれた句です。
正岡子規の弟子であった河東碧梧桐ですが、明治35年(1902年)に子規が没して後、新傾向俳句に傾倒するようになります。
季語にとらわれず、生活の中でわいてくる感情を詠みこもうとし、全国を旅して新傾向の俳句を広めました。
一時期は、碧梧桐ら新傾向俳句の俳人が俳壇を席巻。伝統的な俳句を守ろうとし、竹馬の友でもあった高浜虚子と距離を置く一方、新傾向俳句を作る萩原井泉水らと雑誌「層雲」を創刊、自由律俳句が生まれていきます。
しかし、大正4年(1915年)井泉水とも意見をたがえ、道を分かちます。
この句を作ったころ、碧梧桐は50代。様々な邂逅と別離を繰り返しつつ、俳句の道を歩んでいました。
旅もよくし、紀行文も上梓していた碧梧桐。この句も、孤独に旅を続ける旅人の姿がえがかれているようです。
「一軒家も過ぎ落葉する風のままに行く」の表現技法

こちらの句は、「これが技法だ!」という表現技法が用いられているとは言えません。
あえていえば、有季定型俳句でいうところの、「句切れなし」と似たような語感の句です。
句切れとは、一句の中でリズムや意味で大きくきれるところのことです。普通の文でいえば句点「。」をつけるような場所、「かな」、「や」、「けり」といった切れ字のあるところできれます。
この句は、無季自由律俳句ですから、句切れといったルールからも逸脱しています。
そのため、句切れなしの句であるという言い方は正確ではありませんが、「句切れなし」の句のように、どこかで一拍切れることなく、一息に読むことでこの句の持つ世界観に近づけるといえます。
「一軒家も過ぎ落葉する風のままに行く」の鑑賞文

【一軒家も過ぎ落葉する風のままに行く】の句は、人里から離れ落葉が舞う冬の野原を進んでいく、寂しげなイメージを持つ句です。
「一軒家も」という言葉から、「ぽつんと立っている一軒家さえも」というニュアンスがくみ取れます。
集落の中心部は家もまとまってあったのでしょう。
「集落をぬけてきて少し離れたところにポツンとあった一軒家がその集落のはずれ、その一軒家さえも通り過ぎてきた」ということです。
人の気配は途絶え、動くものと言えば冬の風にさらされ散る落葉のみ。そこを黙々と風に吹かれて進んでいく孤独な旅人が浮かんできます。
冷たい風の音や落葉の乾いた音まで聞こえてくるようです。
作者「河東碧梧桐」の生涯を簡単にご紹介!
河東碧梧桐は1873年(明治6年)2月26日 、現在の愛媛県松山市に生まれました。
本名は秉五郎(へいごろう)。1937年(昭和12年)2月1日)に65歳で没しました。
赤い椿 白い椿と 落ちにけり..
昭和12年(1937年)の2月1日は 河東碧梧桐が腸チフスから敗血症となって死んだ日(享年63)。。 pic.twitter.com/xatF2pCu2d— 【 緊縛方 】真田縄幸【 GAG方 】 (@EsemShibaristJr) February 1, 2017
若い頃は正岡子規の高弟のひとりとして名をはせた俳人であり、随筆家です。明治期から昭和初期にかけて活躍しました。
文学の道を志したころの河東碧梧桐は、高浜虚子とともに、子規の弟子の双璧と並び称され、俳句革新運動を推進した。
しかし、子規の死後、二人の弟子碧梧桐と高浜虚子には方向性の違いが出てきます。
河東碧梧桐はより自由で新しい作風を追い求め、新傾向俳句を唱えます。この運動が後に誕生する自由律俳句を生み出すことにもなりました。
一方の高浜虚子は伝統を重んじ、季語を用いて守旧派として保守的なスタイルで句を詠み続けました。
二人は時に文壇で対立しながら、それぞれの道を歩みました。
昭和十二年(1937年)河東碧梧桐の逝去ののち、高浜虚子は、「碧梧桐とはよく親しみよく争ひたり」(碧梧桐とは、よく親しみもし、よく争いもした)という前書きをつけて、「たとふれば独楽(こま)のはぢける如くなり」という句を詠みました。
これは、「碧梧桐と己の二人をたとえてみれば、回り続けるコマが時に近寄り、しかしお互いはじき合ってしまうようなものである」といったような意味です。
同郷に生まれ、青春時代を共にし、いつしかライバル関係にあったこの二人には確かな絆も存在していました。
河東碧梧桐のそのほかの俳句
(大蓮寺にある碧梧桐の碑 出典:Wikipedia)
- 「蕎麦白き 道すがらなり 観音寺」
- 「赤い椿 白い椿と 落ちにけり」
- 「相撲乗せし 便船のなど 時化(しけ)となり」
- 「雪チラチラ 岩手颪(おろし)に ならで止む」
- 「ミモーザを 活けて一日留守にした ベットの白く」
- 「曳かれる牛が 辻でずっと見回した 秋空だ」















