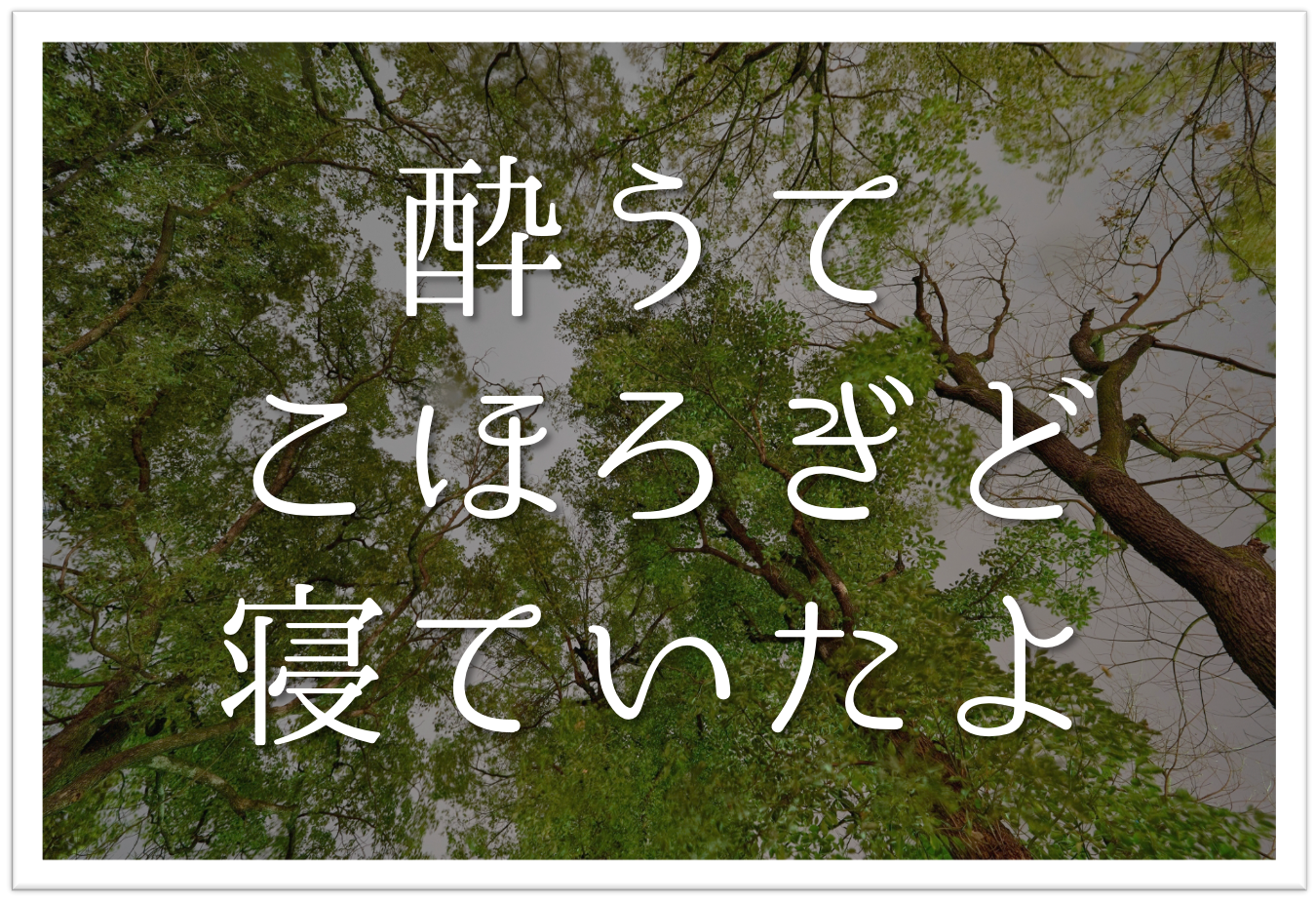
日本の伝統文化「俳句」。
俳句には、五七五の定型を守る「定型俳句」と、自由な言葉の流れで作る「自由律俳句」があります。
「自由律俳句」は決まったリズムがなく、読み手が自由に俳句を想像し楽めることも魅力です。「自由律俳句」の代表といえば、種田山頭火をご存じの方も多いでしょう。
今回は、種田山頭火の有名な句の一つ「酔うてこほろぎと寝ていたよ」という句をご紹介します。
酔うてこおろぎといっしょに寝ていたよ
種田山頭火🎵
心の赴くままに( ´∀`)我後悔せず pic.twitter.com/f1ZCW2VTYL— 妖怪ぬらり~👻 (@RrhHzSdXdsSpGxe) February 5, 2017
本記事では、「酔うてこほろぎと寝ていたよ」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
「酔うてこほろぎと寝ていたよ」の俳句の季語や意味・詠まれた背景

酔うてこほろぎと寝ていたよ
(読み方:ようてこおろぎとねていたよ)
この句の作者は、「種田 山頭火(たねだ さんとうか)」です。
種田山頭火は、明治から昭和にかけて活躍した、「漂泊の俳人」と呼ばれる人物です。
酒と旅に浸る暮らしの中で自由律俳句を極め、八万句以上の句を残しました。自由で温かみのある句風で、現在でも人気の高い俳人です。
季語
この句の季語は「こほろぎ」、季節は「秋」です。
「こほろぎ」は「蟋蟀」とも書きます。黒褐色のものが多い秋の虫です。鳴くのはオスだけで、秋の夜に鳴く声はしみじみとした風情を感じさせます。

「こほろぎ」の鳴き声を文字化すると、「コロコロコロ」「リリリリ」など様々で、聞く人の感覚によってとらえかたがうことがわかります。
しかし、こちらの俳句は自由律俳句のため、季語なしの「無季句」と考える説が一般的です。
山頭火自身が歩んで来た俳句人生を考えると、季節にとらわれずに自分の思いを自由に表現したと考えられます。以上の理由から、こちらの俳句は季語を持たない「無季句」であると言えます。
意味
こちらの句を現代語訳すると…
「酒に酔いつぶれ野宿をしていたときにふと目を覚ますと、こおろぎが耳元で鳴いていたよ」
となります。
かなり泥酔して野に寝てしまった山頭火の様子が目に浮かびます。
この句が詠まれた背景

この句は「酔中野宿」と前書きし、昭和五年十月九日の日記に記されています。
山頭火が宮崎県日南にいた際に作られた句で、昭和六年一月号の『層雲』に掲載されました。
実家が倒産、妻と離婚し出家した山頭火は、四十三歳の頃に単身で行乞行脚(ぎょうこつあんぎゃ)の旅を始め、この句も漂泊の旅の中で作られたものです。
かなりの酒豪であった山頭火は、自身の泥酔への過程を「まず、ほろほろ、それから、ふらふら、そして、ぐでぐで、ぼろぼろ、どろどろ」と述べています。
また、「肉体に酒、心に句、酒は肉体の句で、句は心の酒だ」とも語っていることから、山頭火にとって酒と句は切っても切れない関係であったといえます。
この句でも、かなり泥酔して野に寝てしまった山頭火の様子を知ることができます。
「酔うてこほろぎと寝ていたよ」の表現技法

自由律俳句
この句は十三文字で作られており、俳句の基本的な五七五(十七文字)の定型と離れた自由律俳句です。
俳句には、伝統的な五七五の定型を守り花鳥諷詠の美学をもつ「定型俳句」と、字数・季題にとらわれずにことばの調べによって作られる「自由律俳句」があります。
自由律俳句は、無駄を全て除いた「一行詩」として、世界で最も短い詩形であるとされています。
自由律俳句の特徴には、切れ字や、文語、季語にこだわらず口語で作られることが多いという点があげられます。
自由律俳句は荻原井泉水が提唱したもので、弟子である種田山頭火はその代表といえる俳人なのです。
句切れなし
俳句の「句切れ」とは、句中で意味が一度切れる場所のことをいいます。
この句では、「寝ていたよ」で終助詞「よ」が使われており、「句切れなし」の俳句となっています。
終助詞「よ」
終助詞とは、文末につく助詞のことで、文を完結させる働きがあります。
この句では、終助詞「よ」を使うことで句の語気を強め、読み手に呼びかけや感動を伝える効果を生んでいるのです。
「酔うてこほろぎと寝ていたよ」の鑑賞文

この句は、山頭火が宮崎県を行乞行脚(ぎょうこつあんぎゃ)していた時に作られたものです。
泥酔し野宿をしていた山頭火は、ふと「こほろぎ」の音に目を覚まします。
暗い夜中、一人野原で孤独に寝る山頭火にとって、「こほろぎ」の声が優しく耳元で響いたのでしょう。
夜の静けさの中で、「こほろぎ」の声と山頭火の「孤独感」が鮮明に読み手に浮かび上がってくる句です。
作者「種田山頭火」の生涯を簡単にご紹介!

(種田山頭火像 出典:Wikipedia)
種田山頭火は、1882年(明治十五年)山口県西佐波令村(にしさばりょうむら)、現在の防府市で、大地主であった種田竹次郎の長男として生まれました。本名は正一(しょういち)といいます。
正一が十一歳の頃、夫の女癖に悩んだ正一の母は古井戸に身を投げ自死してしまったため、祖母の手で育てられました。
母親の死体を正一は目にしてしまい、そのことが正一の人生に暗い影を落としたともいわれています。
十五歳の頃に、俳句を開始します。旧制中学卒業後、早稲田大学へ進学し優秀な成績を修めるも神経病を患い中退。その後故郷へ戻り、父の酒造業の手伝いを始めました。父親の放蕩癖は以前として続き、正一自身も文学と酒に浸るようになります。その後、明治四十二年に結婚し、翌年長男が誕生しました。
そして自由律俳句を提唱した、荻原井泉水(おぎわらせいせんすい)に師事します。井泉水主宰の俳句雑誌『層雲』に「山頭火」の俳号で投稿したことがきっかけとなり、世間の注目を浴びるようになりました。
大正五年、種田家は破産。山頭火は妻子を連れ熊本で店を始めた後、山頭火単身で上京し職を転々とする中で、夫婦仲もうまくいかなくなり離婚してしまいます。
大正十三年酒に酔い、電車に身を投げ自殺未遂を起こした山頭火は、出家。大正十五年、四十三歳の頃に単身で行乞行脚(ぎょうこつあんぎゃ)の旅を始めました。九州、四国、中国と漂泊の旅の中で、多くの句を作り『層雲』に発表しました。
昭和六年に熊本に戻った山頭火は個人雑誌『三八九(さんぱく)』を発行しますが、定住することなく再び漂泊の旅に出ます。その後、山口県小郡町の「其中庵(きちゅうあん)」で笠を脱ぎ、山口県湯田温泉の「風来居」に暮らしを移しました。
昭和十四年、山口県を去り四国遍路に向かった山頭火は、翌年愛媛県松山市の「一草庵」にて五十七歳で酒と放浪と俳句の生涯を終えました。
種田山頭火のそのほかの俳句

(種田山頭火生家跡 出典:Wikipedia)
- 分け入っても分け入っても青い山
- うしろすがたのしぐれてゆくか
- しぐるるやしぐるる山へ歩み入る
- どうしようもない私が歩いている
- まつすぐな道でさみしい
- 夕立やお地蔵さんもわたしもずぶぬれ
- 焼き捨てて日記の灰のこれだけか
- あるけばかつこういそげばかつこう
- 鴉啼いてわたしも一人
- 笠にとんぼをとまらせてあるく
- こころすなほに御飯がふいた
- 笠も漏り出したか
- 水音の絶えずして御仏とあり
- 濁れる水の流れつつ澄む
- 酔うてこほろぎと寝ていたよ
- けふもいちにち風を歩いてきた
- 鈴をふりふりお四国の土になるべく
- また一枚脱ぎ捨てる旅から旅
- 生まれた家はあとかたもないほうたる
- ゆうぜんとしてほろ酔へば雑草そよぐ
- また見ることもない山が遠ざかる
- ふるさとはあの山なみの雪のかがやく
- すべつてころんで山がひつそり
- 生死の中の雪ふりしきる
- 松はみな枝垂れて南無観是音
- 鉄鉢の中へも霰
- 霧島は霧にかくれて赤とんぼ
- ほろほろほろびゆくわたくしの秋















