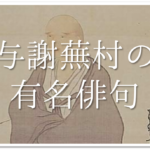「俳句」は、わずか17音という短さが最大の特徴であり魅力です。
最近では「Haiku」として日本語以外の言葉でも詠まれるなど、世界中の人々から愛されています。
今回は、江戸時代中期に活躍した俳人・与謝蕪村の作「鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分かな」という句をご紹介します。
鳥羽殿へ 五六騎いそぐ 野分かな(与謝蕪村) #俳句 pic.twitter.com/sORB7tr2Zz
— iTo (@itoudoor) September 2, 2013
本記事では、「鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分かな」の季語や意味・表現技法・鑑賞などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分かな」の作者や季語・意味・詠まれた背景

鳥羽殿へ 五六騎いそぐ 野分かな
(読み方:とばどのへ ごろくきいそぐ のわきかな)
この句の作者は「与謝蕪村(よさぶそん)」です。
与謝蕪村は江戸時代の中期に活躍した俳人です。この歌は平安時代末期に勃発した保元の乱に思いを馳せて詠んだ句です。
季語
こちらの句の季語は「野分」で、季節は「秋(9月上旬頃)」を表します。
「野分」とは、秋草の野をふき分ける強い風のことです。

台風の風を指すともいわれ、日本人にとって秋の台風は昔から避けられない災害であるとともに秋の到来とともにやって来る年中行事みたいなものだったことが伺えます。
意味
この句を現代語訳すると・・・
「野分が吹き荒れる中を、五、六騎の武士たちが、鳥羽殿を目指して慌ただしく過ぎて行くことよ。」
といった意味になります。
この句は実際に目の当たりにしている風景を詠んだものではなく、保元の乱に想を得たとされています。
この句が詠まれた背景
保元の乱に想を得て詠まれた句「鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分かな」は、与謝蕪村が句会に参加したときに詠んだものです
鳥羽殿とは鳥羽上皇を指し、何らかの事件が起こり(鳥羽上皇の死)、洛中から洛外の鳥羽殿へ武士たちが折からの強風の中、馬を走らせているただならぬ様子が描かれています。
こちらの句は、蕪村が得意とした時代俳句(時代小説の俳句版)の一つであるといえます。

ちなみに、与謝蕪村が参加した句会の記録は、『蕪村全集』第3巻に「句会稿」として集められています。
「鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分かな」の表現技法

(保元・平治の乱合戦図屏風絵 出典:Wikipedia)
切れ字「かな」(句切れなし)
切れ字とは、句の切れ目に用いられ、強調や余韻を表す効果があります。特に「や・かな・けり」の三語は、詠嘆の意味が強く込められており、切れ字の代表ともいえます。
この句の切れ字は、下五「野分かな」の「かな」です。
吹き荒れる野分と鳥羽殿へ急ぐ武士たちのただならぬ様子を「かな」を用いて表現しています。
なお、切れ字は最後の句にあり、文に切れ目はありませんので、「句切れなし」となります。
「鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分かな」の鑑賞

この句は、保元の乱が勃発する前夜の緊迫した情景を詠んだ句として知られています。
野分が吹き荒れる中、疾駆する武士の姿が実際に見えてくるような絵画的な句です。「写生句」といっても違和感がないほどの緊迫感があります。
鳥羽殿は、鳥羽離宮・鳥羽上皇のことを指しますが、この時代はちょうど平安の貴族政治から武家政治へと移行する過渡期にあたり、鳥羽上皇はその中心となる人物でした。
というのも、この鳥羽上皇の死が、崇徳院(鳥羽院の第一子)と後白河天皇(鳥羽院の第四子)との間の皇位継承争い「保元の乱」の引き金になるからです。
蕪村は、鳥羽殿へ向かって疾走する武士たちの姿を思い浮かべ、何か異変があったのに違いない…そんな緊迫した雰囲気が「野分」を掛け合わせることで一層高まります。
この句を詠んでいる時代から遠い昔を回想するのではなく、その世界に足を踏み入れて詠んでいるところが、この句の最大のポイントでしょう。
「鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分かな」の補足情報

保元の乱の前日譚
保元の乱は、鳥羽上皇の崩御後に後白河天皇と崇徳上皇の間で起きた勢力争いです。
鳥羽上皇は直接的にこの乱に関わってはいませんが、その死によって朝廷のパワーバランスが崩れたことがきっかけになっています。対立の軸として、鳥羽上皇と崇徳上皇、摂関家の内紛と2つの勢力争いがありました。
発端となったのは、鳥羽上皇が崇徳上皇を退位させ、寵妃である藤原得子の息子の近衛天皇を立てたことから始まります。院政が出来なくなった崇徳上皇は鳥羽上皇のことを恨み、得子一派と政治的に対立します。
ここに摂関家の内紛も絡み、朝廷内の対立は避けられないものとなりました。鳥羽上皇の院政下であるため武力を伴った攻撃はありませんでしたが、関白と藤原家の当主の間でも権力争いが続いています。
そんな中で近衛天皇がわずか15歳で崩御し、勢力を盛り返したい崇徳上皇と権力を維持したい鳥羽上皇の間で再び争いが勃発。鳥羽上皇の勢力は崇徳上皇の院政を阻止するべく、崇徳上皇の第一皇子である重仁親王ではなく、当時はまだ親王のままであった雅仁親王(後の後白河天皇)の子供の守仁親王の即位を狙います。
父である雅仁親王を飛ばして即位することの是非や、守仁親王がまだ幼かったことから、父親の後白河天皇が先んじて即位しました。摂関家の内紛も未だに続いていて、鳥羽上皇側の勢力が情報を遮断したことで、近衛天皇の呪殺の疑いをかけられた崇徳上皇側の勢力は劣勢に立たされていきます。
そのような情勢下で鳥羽上皇という圧倒的な権力者が崩御したことで、後白河天皇と崇徳上皇の権力闘争として保元の乱が起きるのです。

鳥羽法皇の崩御は7月2日、保元の乱の発端が7月5日と3日しか間が空いていないことから、戦乱の火種は鳥羽法皇の存命時から既にあったことが伺えます。
保元の乱の例えとしての野分
このような背景を考えると、「鳥羽殿へ 五六騎いそぐ 野分かな」という俳句の緊迫感がより強く伝わってくるのではないでしょうか。
つまり、嵐の前の静けさのような気迫が「野分」という台風に込められていることがわかります。
崇徳上皇側の謀反を討てという命令が発せられたのが8日、両軍の挙兵が10日、11日に激突し、その日の正午頃に決着と鳥羽上皇の死からわずか一週間ほどで勝敗が決し、台風のように展開の早い結末になりました。
台風といえば被害が付き物ですが、保元の乱では初めて朝廷の争いに武士が参入した事件になります。

この事件をきっかけに武士の発言力が強くなり、後の武家政権への礎になる歴史の転換点となっていくため、この俳句は歴史的に見ても台風のような大事件が起きる直前の様子を詠んでいるのです。
作者「与謝蕪村」の生涯を簡単にご紹介!

(与謝蕪村 出典:Wikipedia)
与謝蕪村(1716年~1784年)は江戸時代中期に活躍した俳人・画家であり、俳句と絵画を織り交ぜた「俳画」の創始者であることでも知られています。
本姓は谷口(あるいは「谷」)、「蕪村」は俳号で用いていました。摂津国東成郡毛馬村(現在の大阪市都島区毛馬町)に生まれ、10代半ばで両親を失います。孤独の身となった逆境を跳ね除け、江戸を目指した蕪村は松尾芭蕉の孫弟子であった早野巴人に弟子入りし、俳諧を学び始めます。
師の没後は、自らが尊敬する俳聖・松尾芭蕉の足跡を辿る旅に出発します。両親、そして師匠と、立て続けに身近な人物の死に直面した蕪村は、「人はいつ死ぬかわからない」そんな思いを抱えて北関東から東北地方にかけて10年ほど放浪の旅に出ます。
1751年、旅から戻った蕪村は絵画の勉強や制作の方にも力を入れていきます。
そして45歳のときに結婚すると、子宝にも恵まれ、俳人としても画家としても精力的に活動するようになります。
55歳の頃の作品である『奥の細道図屏風』(松尾芭蕉の『奥の細道』原文を書写し、そこへ絵画を入れたもの)は重要文化財にも指定されています。
若いころに大事な人を失った経験や旅で培った感性、自らが課した修行の日々が晩年になってすべて繋がり、実を結んだといえます。
しかし、蕪村の作品が評価されるようになったのは、実は蕪村の死後ずっと後になってからのことでした。正岡子規が明治29年(1896年)に残した『俳人蕪村』という著作によって、ようやく蕪村は世間に知られるようになったといわれています。
与謝蕪村のそのほかの俳句

(与謝蕪村の生誕地・句碑 出典:Wikipedia)
- 夕立や草葉をつかむむら雀
- 寒月や門なき寺の天高し
- 菜の花や月は東に日は西に
- 春の海終日(ひねもす)のたりのたりかな
- 夏河を越すうれしさよ手に草履
- 斧入れて香におどろくや冬立木
- ゆく春やおもたき琵琶の抱心
- 花いばら故郷の路に似たるかな
- さみだれや大河を前に家二軒
- 笛の音に波もよりくる須磨の秋
- 涼しさや鐘をはなるゝかねの声
- 稲妻や波もてゆへる秋津しま
- 不二ひとつうづみのこして若葉かな
- 御火焚や霜うつくしき京の町
- 古庭に茶筌花さく椿かな
- ちりて後おもかげにたつぼたん哉
- あま酒の地獄もちかし箱根山