
「俳句」と聞くと何やら難しく、高尚なイメージを持つ方もいらっしゃるでしょう。
しかし、もともと「俳句」は庶民の生活に密着し、とても身近にたしなまれていた文芸の一つです。
今回は、親近感を感じる句を多く生み出している正岡子規の作品「ずんずんと夏を流すや最上川」という句をご紹介します。
正岡先生の句で好きなのは「ずんずんと夏を流すや最上川」です。本当に好き。この季節青空を見るとこの句を思い出す。
— けーいち (@k1inpixiv) June 14, 2017
本記事では、「ずんずんと夏を流すや最上川」の季語や意味・表現技法・鑑賞などについて徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
「ずんずんと夏を流すや最上川」の季語や意味・詠まれた背景
(最上川 出典:Wikipedia)
ずんずんと 夏を流すや 最上川
(読み方:ずんずんと なつをながすや もがみがわ)
この句の作者は「正岡子規」です。
子規は明治時代の俳句という言葉を定着させた偉大な俳人の一人です。
季語
こちらの句の季語は「夏」です。
夏とは、立夏(現行歴で5月5日または6日)から立秋(現行暦で8月7日または8日)の前日までの約3ヶ月の季節をいいます。
意味
この句の現代語訳は・・・
「この時期の最上川の水量は圧倒されるものがある。夏という季節を乗せ、勢いよく流れているようだなぁ。」
といった意味になります。
この句が詠まれた背景
この句は1893年、「正岡子規」が26歳のときに奥州旅行の途中、大石田で詠んだ句といわれています。
松尾芭蕉の「おくのほそ道」の足跡を訪ねる旅行の途中、連日の疲労で歩行の限界に達したとき、眼に映った最上川の圧倒される勢いで流れる様子を詠んだ句です。
子規の紀行文『はて知らずの記』では、大石田を訪れたときのことを下記のように記しています。
「晴れて熱し。殊に前日の疲れ全く直らねば歩行困難を感ず。」
この句を詠んだ当日は晴天で気温が高く、前日の疲労からか、これ以上の歩行はもはや困難だと感じていたことがわかります。
また、下記の文章も残されています。
「三里の道を半日にたどりてやうやうに大石田に着きしは正午の頃なり。最上川に沿ふたる一村落にして昔より川舩の出し場と見えたり。舩便は朝なりといふにこゝに宿る。」
つまり、三里の道を半日かけて歩き正午頃にようやく大石田に辿り着いたが、酒田に下る船便が翌朝とのことから、この最上川沿いの集落である大石田に一泊することとなったということです。
「ずんずんと夏を流すや最上川」の表現技法

この句で使われている表現技法は・・・
- 切れ字「や」(二句切れ)
- 擬音語「ずんずん」
- 体言止め
になります。
切れ字「や」(二句切れ)
「切れ字」は俳句でよく使われる技法で、感動の中心を表します。代表的な「切れ字」には、「かな」「けり」「ぞ」「や」などがあり、意味としては、いずれも「…だなぁ(感嘆)」といった感じで訳されることが多いです。
この句は「夏を流すや」の「や」が切れ字に当たります。夏という季節を流す勢いで流れる最上川の水量と水勢に圧倒されている気持ちを表現しています。
また、この句は中七「夏を流すや」に切れ字「や」がついていることから、「二句切れ」の句となります。
擬音語「ずんずん」
この句では、最上川の水が勢いよく流れていく様子を「ずんずん」という擬音語を使って表現しています。
「ずんずんと」という形容は、この句の感動のポイントである「夏を流すや」と呼応し、読み手の五感を刺激する効果があります。
「ずんずん」という言葉を使うことによって、夏という季節自体を流してしまうほど、激しい水の勢いが感じられます。
体言止め
体言止めとは、文末を名詞や代名詞などの体言で止める技法の事を指します。
文末を体言止めにする事で、文章全体のイメージが強調され読者に伝わりやすくなり、また、句にリズムを持たせる効果もあります。
この句は、語尾を「最上川」で締めくくることによって読み手にイメージを委ね、最上川の水量や水勢、いつまでも耳に残る急流の音…などを想像しやすくなっています。
「ずんずんと夏を流すや最上川」の鑑賞文
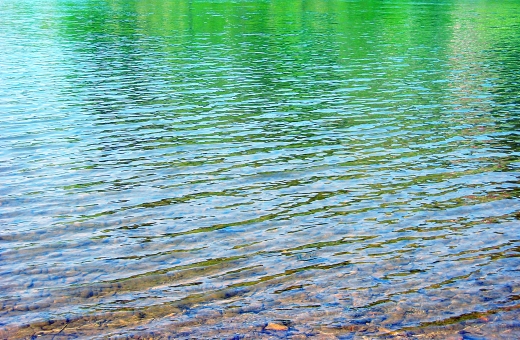
「ずんずんと夏を流すや最上川」は正岡子規が26歳のときに詠んだ句で、自らが尊敬してやまない松尾芭蕉の足跡を訪ね、奥羽へ長旅をした際の紀行文『はて知らずの記』に収録されています。
子規の詠んだこの句の発想の契機は芭蕉の「五月雨を集めて早し最上川」にあると言われています。
また、夏という季節自体を流してしまうほどの勢いで流れる最上川。その様子を「ずんずん」という音で表現することで、読み手に新鮮な印象を与えています。
「ずんずん」という擬音語を使うことで区全体に美しいリズムが生じ、子規の俳人としてのエネルギーが感じられる一句です。
また、連日の疲労で歩行の限界に達したとき、眼に映った最上川の流れる勢いは目だけでなく、心までも焼き尽くす素晴らしい光景だったことでしょう。
作者「正岡子規」の生涯を簡単にご紹介!

(正岡子規 出典:Wikipedia)
正岡子規(1867年~1902年)は本名を常規(つねのり)といい、日本の近代文学に多大な影響を及ぼした文学者です。
伊予国温泉郡藤原新町(現愛媛県松山市花園町)の松山藩士の家庭に生まれた子規は、幼いころから漢詩や戯作、書画などに親しんでいたといわれています。
「ずんずんと夏を流すや最上川」を詠んだ1893年に『獺祭書屋俳話(だっさいしょおくはいわ)』の連載をはじめ、俳句の革新運動を開始しました。
1895年、日清戦争の従軍記者として遼東半島に渡ったものの、喀血して重態に陥ります。「鳴いて血を吐く」といわれているホトトギスと自分の境遇を重ね、ホトトギスの漢字表記「子規」を自らの俳号とすることに決めました。
1897年、俳句雑誌『ホトトギス』を創刊し、俳句の世界に大きく貢献しました。短歌においても、古今集を否定し、万葉集を高く評価。江戸時代までの形式にとらわれた和歌を非難しつつ、短歌の革新につとめた功労者として知られています。
やがて病いに臥せるようになり、1902年9月19日、享年35歳でその生涯を終えました。
正岡子規のそのほかの俳句

(前列右が正岡子規 出典:Wikipedia)
- 柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺
- 紫陽花や昨日の誠今日の嘘
- 赤とんぼ 筑波に雲も なかりけり
- 夏嵐机上の白紙飛び尽す
- 牡丹画いて絵の具は皿に残りけり
- 山吹も菜の花も咲く小庭哉
- 毎年よ彼岸の入りに寒いのは
- 雪残る頂ひとつ国境
- いくたびも雪の深さを尋ねけり
- 柿くふも今年ばかりと思ひけり
- 鶏頭の十四五本もありぬべし
















