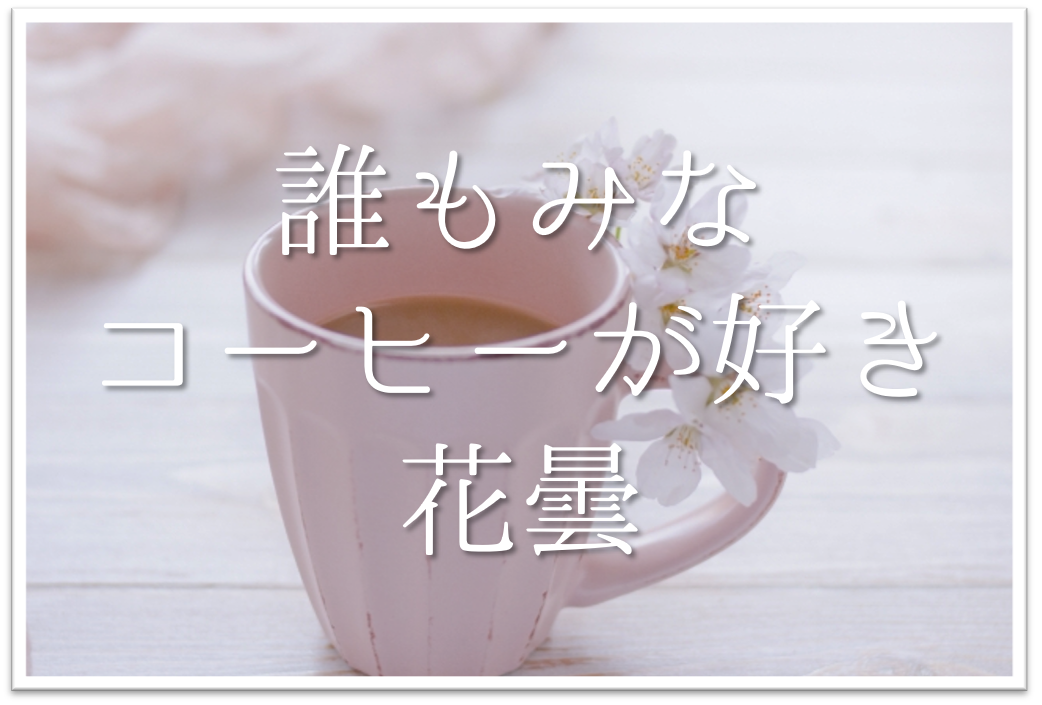
日本には、近現代になって詠まれた作品が数多くあります。
それらの作品の中には、何気ない日常をテーマにした俳句も多いです。
今回はそんな何気ない日常を詠んだ句の一つ「誰もみなコーヒーが好き花曇」という星野立子の句を紹介していきます。
おはようございます。
Mr. Coffee Beenだよ。
It’s the coffee time !☕️☕️誰もみなコーヒーが好き花曇
星野立子初の女性主宰誌「玉藻」を創刊
高浜虚子の次女(1903-1984)
コーヒーが好みだったのですね。困ったときに登場します…f^_^; pic.twitter.com/PCRgz9B7EG
— あづき (@kakichazuke) April 2, 2022
本記事は、「誰もみなコーヒーが好き花曇」の季語や意味・表現技法・鑑賞・作者について詳しく解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「誰もみなコーヒーが好き花曇」の季語や意味・詠まれた背景

誰もみな コーヒーが好き 花曇
(読み方 : だれもみな コーヒーがすき はなぐもり)
こちらの句の作者は、「星野立子(ほしの たつこ)」です。
星野立子はあの有名な俳人・高浜虚子の次女で、昭和期に活躍した女性俳人です。
星野 立子1984年(昭和59年)3月3日没、昭和期の俳人。高浜虚子の次女。虚子の一族でも特に評価の高い人物の一人である。女流では中村汀女、橋本多佳子、三橋鷹女とともに四Tと称された。
学童の 顔浸し居る
春の川 pic.twitter.com/cTfmwGBn0c— 久延毘古⛩陶 皇紀2680年令和弐年睦月 (@amtr1117) March 2, 2014

それでは、早速こちらの俳句について詳しく紹介していきます。
季語
こちらの句の季語は「花曇」で、季節は「春」を示します。
参考までに「花曇」は、桜が咲く頃の明るい曇り空を表現する言葉のことです。

桜の花と似たような色をした空であるため、桜の美しさが満喫できないという意味で使用されることがあります。
意味
こちらの句の現代語訳はそのまま・・・
「誰もがみんなコーヒーが好きだよ花曇の空よ。」
となります。
こちらの作品は、「花曇」とあるのでお花見または桜を見物しながら詠まれた作品であるとわかります。

季節の移り変わりの激しい季節だけあり、どことなく淀んだような空でまだ寒さが厳しいであろうと推察できます。
この句が詠まれた背景
この作品は、桜のお花見の席で詠まれた俳句です。
「せっかく桜を見ようと仲間で集まったのに、空は残念なことに曇り空。お花見を満喫しようにも、パッとしない空。でもコーヒー好きのみんなが集まれば、話が盛り上がり時間が経つのはあっという間だった。お天気やお花見も忘れて、楽しいひと時を過ごせたわ」という心情が詠まれています。
また、季節的には桜が咲く頃は、上着が手放せない肌寒いシーズンです。

そんな寒い季節だからこそ「誰もがみんな温かいコーヒーが恋しくなる」という意味合いにも読み取れます。
「誰もみなコーヒーが好き花曇」の表現技法

「花曇」の部分の体現止め
「体言止め」とは、文末を名詞で結ぶ表現技法です。
体言止めを使用することにより、文章全体のインパクトが強まり、作者が何を伝えたいのかをイメージしやすくなります。
こちらでは「花曇」と結ぶことで、
- せっかくの桜も花曇の空で台無しだよ
- コーヒーが恋しくなるほど、薄寒い曇った空だよ
という状況が伝わってきます。
こちらの作品は誰にでも分かりやすいだけに、「花曇」と置くことで文章全体がグーンと引き締まって見えます。

【誰もみなコーヒーが好き花曇】からは、コーヒーのいい香りが漂って来るような、ほんわかとした作品に感じます。
「コーヒーが大好きな仲間達が集まって、お花見をしようと思ったのに、そんな気持ちに反して空は薄ぼんやりとした花曇で、せっかくの桜もいまいち…。
ガッカリしつつも、温かいコーヒーを飲みながら話に花が咲いて、お花見のことなんて忘れてしまうほど楽しいひと時だったわ。
コーヒーを飲んで身も心もほっこりと温まって、とても楽しい時間だった。」という風に汲み取れます。
「誰もみなコーヒーが好き花曇」の補足情報

コーヒーは季語にはならない?
「新茶」や「ビール」「熱燗」など、飲み物で季語になっているものが多い一方で、「コーヒー」は季節が特定できないため季語にはなりません。
ただし、「アイスコーヒー」は夏の季語として認められています。

この句でも「アイスコーヒーが好き」となっていた場合は、少し蒸し暑い日を想像してしまいますよね。
日本のコーヒー文化は明治時代から
コーヒーは、17世紀末から18世紀頃にオランダ人によって日本にもたらされた飲料で、明治時代の19世紀後半以降になってから一般化し、太平洋戦争後に全国的に普及しました。
その中でもアイスコーヒーやコーヒーゼリーの普及など、独特なコーヒー文化が発達しています。
夏の季語になっているアイスコーヒーは「冷やし珈琲」とも呼ばれる日本発祥の飲み方です。
この「冷やし珈琲」は1907年の料理本に既に載っており、早い段階で日本人の夏の飲み物となっていたことがわかります。
その料理本には以下のように書かれています。
「これは夏の飲料にはごくよろしいもので、宅では何時もこれを拵え氷箱の中へ冷して置きます。炎天を歩いて来て之を飲みますと実に美味しゅう御座います。この冷し珈琲は別段むずかしいことではありません。ただ珈琲を煎じ出して牛乳と砂糖を入れ、氷箱で冷して置くか、氷箱の無い御家なら冷水へ漬けて置けばよいのです。」

現在でいうコーヒー牛乳のようなものが明治40年には夏の風物詩として定着していたのでしょう。
「花曇」の気温はどのくらい?
「アイスコーヒー 」という季語を使わなかったことから肌寒いことが考えられますが、具体的にどの程度の気温だったのでしょうか。
仮に作者が存命だった1980年代の東京だとすると、桜の開花時期である3月下旬の平均気温は15℃前後になっています。
寒さを感じてホットコーヒーを飲んで一息付いていたなら、平均気温よりもう少し低い気温になるでしょうか。

寒さで花見どころではなく、作者はどこかのお店で熱いコーヒーで一息つきながらゆったりと桜の花を眺めたいという気持ちがよくわかる気温です。
作者「星野立子」の生涯を簡単にご紹介!
立子忌
高浜虚子の子で『玉藻』を主宰した俳人・星野立子の1984(昭和59)年の忌日。
「雛飾り
つゝふと命
惜しきかな」 pic.twitter.com/r7CI3zY1DE— 久延毘古⛩陶 皇紀2680年令和弐年睦月 (@amtr1117) March 2, 2019
星野立子は、1903年(明治36年)に現在の東京都千代田区(旧麹町区)に、高浜虚子の次女として生まれました。虚子に師事し、同時期に活躍した女性俳人四丁の1人。
1924年に東京女子大学を卒業後の翌年、鎌倉彫職人の星野吉人と結婚しました。
『ホトトギス』発行所および文化学院に勤務し、1930年長女誕生。同年初の女子主宰誌『玉藻』を創刊します。
政府文化使節使としても活躍し、各国を訪問。その後、勲四等宝冠賞受賞。1984年直腸癌により死去しました。

没後に鎌倉虚子立子記念館が開館。その他星野立子賞が設立されています。
星野立子のそのほかの俳句

- 昃(ひかげ)れば春水の心あともどり
- ままごとの飯もおさいも土筆かな
- 囀をこぼさじと抱く大樹かな
- 朴の葉の落ちをり朴の木はいづこ
- 父がつけしわが名立子や月を仰ぐ
- しんしんと寒さがたのし歩みゆく
- 美しき緑走れり夏料理
- 雛飾りつゝふと命惜しきかな














