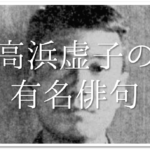明治から大正、昭和を活躍した俳人「高浜虚子」。
彼は、明治~江戸時代までの俳諧や連句から近代文学としての俳句を確立しようとした「正岡子規」の高弟にして、子規亡き後師の遺志をつぎ、日本の俳壇の中心人物として活躍した人物です。
今回はそんな高浜虚子の「白牡丹といふといへども紅ほのか」という句を紹介していきます。
紅がほのかに息づいている寒牡丹。虚子の句のような。
白牡丹といふといへども紅ほのか#上野東照宮 pic.twitter.com/uwxF6CmK2p
— 高橋和志 (@K5Takahashi) January 8, 2018
本記事では、「白牡丹といふといへども紅ほのか」の季語や意味・表現技法・鑑賞文・作者について徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「白牡丹といふといへども紅ほのか」の作者や季語・意味・詠まれた背景

白牡丹と いふといへども 紅ほのか
(読み方:はくぼたんと いうといえども こうほのか)
高浜虚子は明治時代から昭和時代にかけて、俳人そして小説家として活躍した人物です。
正岡子規に師事した虚子は、その一生を終えるまで忠実に子規の教えを貫き、自由律俳句を擁護する活動が高まりを見せるなかで、伝統俳句を守り続けました。
虚子の句風は「花鳥風体」と呼ばれており、写実的な表現を用いた句が特徴です。
季語
こちらの句の季語は「牡丹(ぼたん)」、初夏の季語です。
牡丹は中国から日本に渡来した植物で、中国では「花の王」ともよばれています。五月ころ花を咲かせる低木です。

牡丹は園芸品種も数多く、花色は白・赤・黄色、一重のものや八重のものなど様々な品種があります。
意味
こちらの句を現代語訳すると・・・
「白牡丹という名前の花だけれども、よくよく見るとほのかに紅色もさしていることよ。」
という意味になります。
「いふといへども」は「~というということだけれども、~という名前であるといっても」といった意味になります。
牡丹の花の様子をよく観察し、シンプルな言葉で特徴をとらえています。
"Blanca peonía",
decimos; y aun así,
es levemente rosa.
白牡丹といふといへども紅ほのか(Takahama Kyoshi) #haikudellunes pic.twitter.com/slYWfHFN5b
— Haiku Barcelona (@haikubarcelona) June 18, 2018
この句が生まれた背景
この句は「五百句」という句集に収録されています。
「大正十四年五月十七日 大阪にあり。毎日俳句大会。会衆八百。」という添え書きがあります。
大正14年(1925年)5月17日に行われた「大阪毎日新聞」の俳句大会での詠句であり、集まった人が800いたということです。
「五百句」の句集には・・・
「雨風に 任せて悼む 牡丹かな」
(意味:雨風にさらされ、花弁を散らし、花の命を終えていく牡丹があわれなことよ。)
という句も一緒にのっています。
「白牡丹といふといえども紅ほのか」の句は、高浜虚子の代表作としてあまりにも有名です。

この句はあでやかに今を盛りと咲き誇る花の様子を詠んでいる一方、同時に詠まれた「雨風に」の句は短い命を終えていく花の様子と異なった様子を詠んでいることが興味深く見て取れます。
「白牡丹といふといへども紅ほのか」の表現技法

こちらの句で用いられている表現技法は・・・
- 「白」と「紅」の対比
- 「紅ほのか」の省略
- 「白牡丹と」の字余り
になります。
「白」と「紅」の対比
対比とは、複数の異なるもの、または類似するものを並べて比べて見せることでそれぞれの持つ特性をより際立たせて印象付ける表現技法のことです。
この句では、「白」と「紅」の色彩的対比が印象的です。「紅白」の取り合わせです。
あくまでもこの句は「白牡丹」を詠んだ句です。作者の発見した「紅」は、牡丹の白さをより一層引き立てる方に回っています。
「紅ほのか」の省略
省略とは、文章の中の言葉を省き、読み手に推測させることで余韻を残す表現技法のことです。短い音数で内容を表現する俳句では、よく使われる技法です。
この句は「紅ほのか」で終わっていますが、これは「紅ほのかに色づけり(紅色にほのかに色づいている)」とか、「紅ほのかに見えにけり(紅がほのかに見えていることよ)」といったようなことでしょう。
「紅ほのか」で後の言葉を省略することで余韻を残しています。
「白牡丹と」の字余り
初句は、本来なら五音でおさまるところですが、「はくぼたんと」と六音になっています。
これを字余りといいます。五・七・五のリズムをあえて崩すことで雰囲気を作り、印象を強めます。
「白牡丹といふといへども紅ほのか」の鑑賞文

【白牡丹といふといへども紅ほのか】の句は、牡丹の花の様子をよく観察してシンプルな言葉で特徴をとらえた句です。
作者の目は、白牡丹に止まります。じっと白牡丹を見つめて観察していると、ほのかに紅色の帯びたところに気づいたのでしょう。
「いふといへども」というのは、「~というということだけれども、~という名前であるといっても」といったくらいの意味です。
基本的にたった十七音しかない俳句の中では、なんだかまだるっこしく、冗長な言い方にも思えますが、「といふといへども」とつぶやいている間に作者の視線は牡丹の花をよくよく見つめ、「紅ほのか(ほのかに紅色がさしている)」ことに気づくのです。
「といふといへども」の言葉が生み出すのは、カメラのレンズでズームアップして焦点が合うまでの間のような感じです。

「白牡丹と」の「は」、「いふといへども」の「ふ」「へ」、「紅ほのか」の「ほ」とハ行が多用されているところ、「と」「と」「ど」と同じ音が繰り返すところなど、リズム的にもテンポのよい俳句となっています。
「白牡丹といふといへども紅ほのか」の補足情報

句で詠まれているのは「春牡丹」
牡丹には春牡丹と寒牡丹、冬牡丹という咲く時期によって幾つか種類があります。
春牡丹は4 - 5月に開花する一般的な品種で、夏の季語となっているのはこの春牡丹です。
寒牡丹は春と秋に花をつける二季咲きの変種で、春にできる蕾を摘み取って、秋にできる蕾のみを残して10月下旬から1月に開花させます。冬牡丹は春牡丹と同じ品種を1 - 2月に開花するよう調整したものです。
寒牡丹と混同されることが多いですが、これは放置すると春咲きに戻ってしまうため、人為的に管理されています。
牡丹は品種改良が盛んに行われ、園芸品種が非常に多いのが特徴です。

白牡丹のほかにも花色も豊富で、花の形も多彩です。赤・赤紫・紫・薄紅・黄・白の色の花と、一重・八重・千重、大輪・中輪という花の形がほとんどです。
牡丹の用途は薬用から観賞用へ
牡丹は中国原産で、現在見られる品種改良された牡丹の大元になっている原産種が8種類ほどに留まるのに対し、品種改良が日本やアメリカ、フランスで行われ、1000種を超えるほど愛されています。
これらは当初薬用として栽培されていましたが、唐の時代から花として愛でられるようになりました。
5弁から8弁ほどだった花は品種改良により八重咲きの豪華な物が多くなり、牡丹と言われてぱっと思いつくような花に変化しています。
江戸時代には既に160種以上の品種改良された牡丹が流行っていて、「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」ということわざも江戸時代の中期に出現しています。

明治に入り、外国での品種改良も進んだことにより、現在は1000種を超える様々な色の牡丹の花が楽しめるようになりました。
作者が見た白牡丹の品種
牡丹には様々な品種があり、白牡丹と言っても色々な種類があります。
作者が見た白牡丹は「紅ほのか」とあるため、中心がほんのりと赤くなった牡丹だったのでしょう。
白牡丹は次のような品種が特に有名です。
- 【真っ白な花が咲く】「島根白雁」「扶桑司」「新扶桑司」「玉簾」「白雲竜」「白王獅子」など。
- 【中心部がほんのりとピンク色の花が咲く】「貴婦人」「玉天集」「国華」「白妙」「新八束」「新潟明石潟」「二上」など。

これらのうちどの牡丹を見たかはわかりませんが、紅ほのか、つまり中心部がピンク色になる後者の牡丹を見たのでしょう。
作者「高浜虚子」の生涯を簡単にご紹介!

(高浜虚子 出典:Wikipedia)
高浜虚子は、明治7年(1874年)に現在の愛媛県松山市で生まれました。本名は清(きよし)です。
近代俳句の祖であり、同郷人でもあった正岡子規に師事。一時は小説に傾倒していた時期もありましたが、明治期から昭和にかけて俳人として活動しました。
虚子という雅号は、師である正岡子規が本名の清(きよし)からつけたものです。
虚子は正岡子規の遺志をつぎ、正岡子規の流れをくむ俳句雑誌「ホトトギス」の主宰もつとめました。
長く日本の俳壇に君臨し、「花鳥諷詠」(花や鳥といった自然の美しさを詩歌に詠みこむこと)、「客観写生」(客観的に情景を写生するように表現しつつ、その奥に言葉で表しきれない光景や感情を潜ませる)を提唱しました。
俳句雑誌「ホトトギス」を通じて多くの俳人が世に出ることとなり、後進を育てた役割も偉大です。
昭和34年(1959年)神奈川県鎌倉市で85歳で没しました。
高浜虚子のそのほかの俳句

(虚子の句碑 出典:Wikipedia)