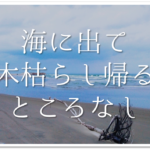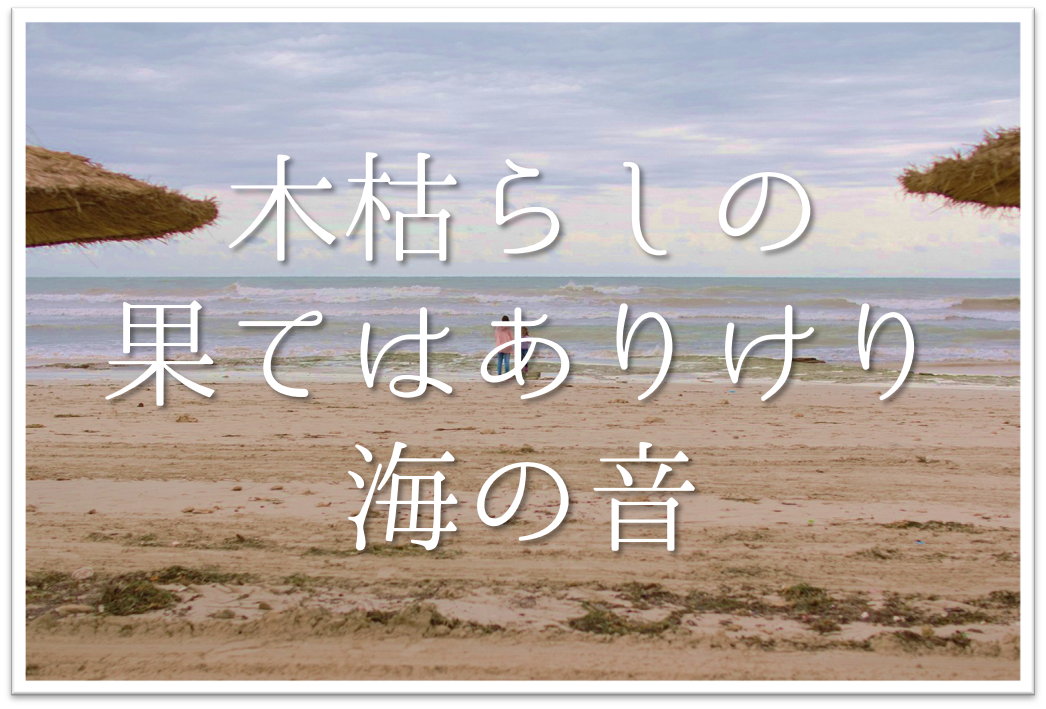
江戸時代前期の俳人「池西言水」。
彼は松尾芭蕉と同時代に活躍した俳人であり、江戸や京の都で活躍しました。
今回は彼の句から「木枯らしの果てはありけり海の音」という句を紹介していきます。
木枯の果てはありけり海の音
池西言水 pic.twitter.com/tJew2nQPgm
— hourin (@hmarble2001) January 6, 2016
本記事では、「木枯らしの果てはありけり海の音」の季語や意味・表現技法・鑑賞文・作者など徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「木枯らしの果てはありけり海の音」の季語や意味・詠まれた背景

木枯らしの 果てはありけり 海の音
(読み方:こがらしの はてはありけり うみのおと)
この句の作者は「池西言水(いけにし ごんすい)」です。
池西言水は江戸時代初期の俳人で、松尾芭蕉と同時代に活躍した人物になります。
季語
この句の季語は「木枯らし」で、季節は「冬」を示します。
「木枯らし」とは、日本の太平洋側地域において、晩秋から初冬の間に吹く風速8m/s以上の北よりの風のことで、冬型の気圧配置になったことを示します。
また、木の葉を落とし、枯れ木にしてしまうほどの風という意味もあります。

そのため、「木枯らし」という季語は冬になり木々は枯れ、葉も朽ちてしまっている寂しい冬の情景を表しています。
意味
この句を現代語訳すると・・・
「冬の野山を吹き荒らした木枯らしにも行き着く果てがあるのだなあ。海鳴りの音こそ、その果てなのだ。」
という意味になります。
この句は陸で吹いて木を枯らしてこその「木枯らし」を、木が全くない海で見つけたときの新鮮なおどろきを表現しています。

風には終点などありませんが、枯らす相手がなくなった海で海鳴りに吸い込まれたところで、作者は木枯らしの終わりを感じたのです。
この句が詠まれた背景
この句の作者である「池西言水」は27歳の頃、江戸へと移り、そこで「松尾芭蕉」と交流を重ねていきました。
そのなかで談林風の句作りを追いながらも蕉風に傾倒していきます。
やがて芭蕉一門の台頭の一翼を担ったとも言われますが、その後京へと移ります。
元々彼は機知にとんだ感受性豊かな句作りが特色と言われていましたが、京に移ったことでその独特の感性に京風の情緒が加わった佳句が見られるようになります。
「木枯らしの果てはありけり海の音」の句は京時代に詠まれた句で、彼の魅力が詰まった代表作となっています。

ちなみに、山口誓子はこの句を本歌として、「海に出て 木枯帰る ところなし」という句を詠んだとされています。
「木枯らしの果てはありけり海の音」の表現技法

切れ字「けり」(二句切れ)
切れ字とは、意味や内容、調子の切れ(終止)の働きをする字や言葉のことで、作者の感動の中心を指します。
代表的な切れ字には「や」「かな」「けり」などがあります。
今回の句は「果てはありけり」の「けり」の部分が切れ字に当たり、「行き着く果てがあるのだなあ…」と作者の感動を表しています。
また、二句目に切れ字が用いられていることから、この句は「二句切れ」となります。
体言止め
体言止めとは、下五語を名詞や代名詞で終わる技法のことで句に深みを与える効果があります。
ここでは「海の音」がそれに辺り、全てを枯らす風もやがて海と一体化するとしています。
体言止めを用いることで、勢いがあるものもやがて衰えて消えていくものだと印象づけられています。
「木枯らしの果てはありけり海の音」の鑑賞文

【木枯らしの果てはありけり海の音】の山から海へ吹く木枯らしは、海が終着点になりますが、単に「ゴールは海です」とは言わず、木枯らしの吹き荒れる音が海鳴りの音に掻き消されている情景と詠んでいます。
海は木枯らしの終着点よりも、音を掻き消されることから木枯らしの消失場所を表しています。
さらに木枯らしは水を含まない風なので、海に渡ることで水分を吸収し、木枯らしとは言えなくなります。
木枯らしは冬の訪れを告げる風で、実りのない一年の終末であり死を連想されます。

作者はこの情景にすべての物には終わりがあり、死が待っていると、儚いこの世に思いを馳せているのです。
「木枯らしの果てはありけり海の音」の補足情報

句の前詞
この句は当初連歌の発句として詠まれたものですが、のちに作者と真蹟と認められているものに「湖水眺望」という前詞がつけられています。
ここで言う「湖」とは琵琶湖のことで、琵琶湖の広大さを海に例えたという説が一般的です。

しかし、もうひとつの説として、「琵琶湖」を大きな琵琶に見立て、木枯らしによって音がかきたてられている様子を詠んだのでは無いかという説もあります。
「凩の」の付句
付句とは、「五七五」の発句のあとに付けられる「七七」で、発句がどのように解釈されたかを知る手がかりになります。
「凩の」あとの付句は「漂泠(みお)の火きえて さむき明星」です。
「凩の 果てはありけり 海の音」
「漂泠の火きえて さむき明星」
「澪泠」とは「澪標(みおつくし)」のことで、「川の河口などに港が開かれている場合、比較的水深が深く航行可能な場所である澪との境界に並べて設置され、航路を示す」ものです。

この一連の歌からは、澪標の火すらも消えている寒い早朝に明けの明星が輝く中で、木枯らしを追いかけて海までやってきた旅人の様子が浮かんできますね。
謡曲「東北」からのインスピレーション
謡曲「東北」からは、「果てはありけり」というフレーズを参考にしています。
謡曲「東北」では次のように扱われていました。
「春立つや 霞の関を今朝越えて 霞の関を今朝越えて
果てはありけり武蔵野を 分け暮らしつつ 跡遠き
山また山の雲を経て 都の空も近づくや
旅までのどけかる覧 旅までのどけかる覧」
(訳:立春の時期になった。江戸の霞の関を今朝越えて、霞の関を今朝越えて、
広大に思えた果てがあった武蔵野を、分けて暮らしていた跡は遠く、
山また山の雲を経て、都の空も近づいてくるようだ。
旅までのどかな事であろう。旅までのどかな事であろう。)
テンポの良い繰り返し言葉が多い中で、「果はありけり武蔵野」だけは繰り返されていません。
これは広大な関東平野にも果てはあったのだという感嘆を込めたものであり、「凩の」の句に使われた「果てはありけり」と同じ気持ちで書かれたものでしょう。

終着点を示す言葉は多くありますが、あえて「果てはありけり」と使うことで、謡曲「東北」を知っている人に風景を分かりやすくしていたのではないでしょうか。
作者「池西言水」の生涯を簡単にご紹介
「池西言水」は江戸時代初期の「松尾芭蕉」と同時代の俳人で、16歳で法体して俳諧に専念したと伝えられています。
言水忌
俳人・池西言水の1722(享保7)年9月24日の忌日。
高根より 礫うち見ん 夏の湖 pic.twitter.com/YAfUMt9exB
— 久延毘古⛩陶 皇紀2679年令和元年師走 (@amtr1117) September 23, 2019
27歳の頃、江戸へと渡り「松尾芭蕉」と親交を深めていくことになるのです。
やがて彼は京へと移り住み、彼のもつ感性は研ぎ澄まされ、更なる発展を遂げていきます。
「木枯らしの果てはありけり海の音」の句を詠んだことで評判となり「凩の言水」と呼ばれるようになります。
一流俳人たちと鋭角的に交わりながら、常に第一線で意欲的な活動を続けていくことになるのです。
池西言水のそのほかの俳句

- 菜の花や淀も桂も忘れ水
- 高根より礫うち見ん夏の湖
- 高根より礫うち見ん夏の海
- 大年の富士見てくらす隠居かな
- 歯固やとは云ひさして水の恩
- 鏡餅多門は鉾とあれ鼠
- 伊勢参りみやこみかへせ花曇り
- から井戸の御法待らん雨蛙