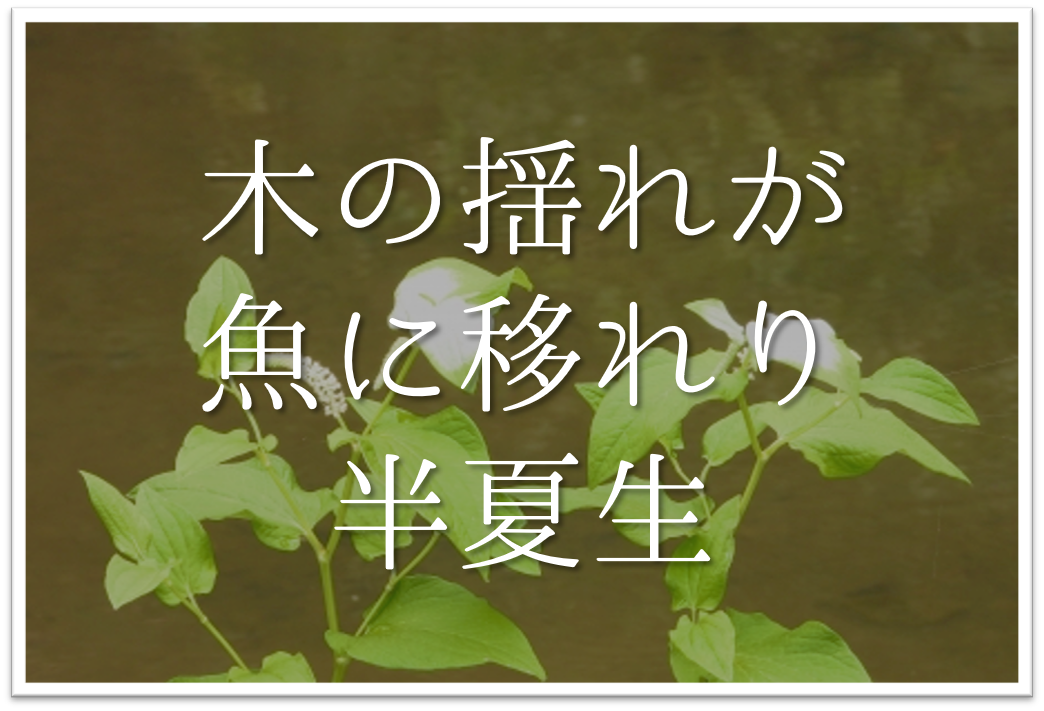
昭和から今もなお活躍している俳人「大木あまり」。
彼女は鋭敏な感性と豊かな抒情が魅力の優れた女性俳人です。
今回は数多くある名句の中でも特に人気のある「木の揺れが魚に移れり半夏生」という句を紹介していきます。
今日の一句
木の揺れが魚に移れり半夏生
大木あまり季語:半夏生#俳句 #季語 pic.twitter.com/ZqlPvt6blu
— 浅乃み雪 (@Asano_Miyuki) July 1, 2024
本記事では、「木の揺れが魚に移れり半夏生」の季語や意味・表現技法・鑑賞文・作者など徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「木の揺れが魚に移れり半夏生」の季語や意味・詠まれた背景

木の揺れが 魚に移れり 半夏生
(読み方:きのゆれが うおにうつれり はんげしょう)
この句の作者は「大木あまり」です。
大木あまりは、現在もなお活躍している女性俳人です。詩人・大木惇夫の実娘であり、本業は画家ですが、母親に勧められて俳句を始め、「河」で角川源義に師事しています。
その後、「人」「夏至」「古志」などを経て、現在は無所属。 石田郷子らと同人誌「星の木」を立ち上げて、主にそこを発表の場としています。
季語
この句の季語は「半夏生」で季節は「夏」を示します。
「半夏生」とは、夏至(6月21日ごろ)から数えて11日目の7月2日頃から七夕(7月7日)頃までの5日間のことで、この頃から梅雨が明けていきます。
また、一説では・・・半夏生はハンゲショウ(カタシログサ)という草の葉が、名前の通り半分白くなって化粧をしているような姿になる時期を意味しているとも言われています。

どちらにしても時期は同じであり、本格的に夏を迎える頃であることがわかります。
意味
この句を現代語訳すると・・・
『枝が揺れると池の中の小さな魚の群れも日陰を求めて動く。暑い盛りは人と同じように水中の魚も日陰を求めるのだ』
という意味になります。
梅雨が過ぎ本格的な夏が到来。木の枝が揺れる度に、水面に映る影もゆらゆらと揺れており、小さな魚の群れは木陰を求めて動いています。

夏の暑さを感じるのは人も魚も同じで、一見涼しげな池の住人も暑さから逃れたいのです。
詠まれた背景
「大木あまり」の詠む句には、彼女の思念や見たものが、生き生きと句の中に吹き込まれている特徴があります。
俳句の定型を守り、季語を使うなどの俳句のルールを守りながらも、一つ一つの句が自然に仕上がっているのです。
この句も一見すると普通の風景に見えますが、彼女の自然かつ高度な技術によって生き生きと描かれています。
「木の揺れが魚に移れり半夏生」の表現技法

(ハンゲショウの花と葉 出典:Wikipedia)
二句切れ
句切れとは、意味や内容、調子の切れ目のことを指します。
ここでは「魚に移れり」が句切れ(意味上の切れ目)となり、二句目で切れているので「二句切れ」の句となります。
つまり、「枝が揺れると池の中の魚の群れも日陰を求めて動く。」で一つの情景となっているのです。
体言止め「半夏生」
体言止めとは下五語を名詞や代名詞で締め括る技法のことで、ここでは「半夏生」がそれにあたります。
ここで半夏生と持ってくることで、この句は池の中の魚の動きだけではなく、夏の暑い盛りだからこその光景であると印象付けることができます。
「木の揺れが魚に移れり半夏生」の鑑賞文

【木の揺れが魚に移れり半夏生】は、梅雨が明け、爽やかな青が一面に広がるなか、燦々と輝く太陽が生命に元気を与えている様子が伝わってくる句です・
目の前には緑に包まれた枝の生い茂る木と、日の光を反射している池の水面が、キラキラと輝きを放っています。
風や鳥たちによって枝が揺れる度、水面の影も動いています。そして、ふと池の中を見ると魚たちが暑さから逃れるように、影を求めて動いています。
また、この句を少しだけ風景の色を添えることができます。
それは、「半夏生=ハンゲショウの葉が半分白くなる時期」とみること。
魚たちの住む池上にはハンゲショウの草の葉が半分だけ化粧しているように白くなっています。

半化粧した姿が、初々しさを表し、暑い夏の始まりもどこか若々しい雰囲気を醸し出しています。
「木の揺れが魚に移れり半夏生」の補足情報

(ハンゲショウの花と葉 出典:Wikipedia)
植物としての「ハンゲショウ」
植物としてのハンゲショウは、ドクダミ科の多年草です。水辺や湿地に生える草で、高さ1メートルに達します。
夏に小さな花が集まった細長い総状花序をつけ、その周囲の葉が白く変色するのが特徴です。
半夏生の季節に白い葉になるため「半夏生」と呼ばれるようになったほか、葉の一部を残して白く変化する様子から「半化粧」と呼ばれるようになったという説があります。

また、葉の片面だけが白くなることから、カタシログサ(片白草)とも呼ばれています。
七十二候としての「半夏生」
季節としての半夏生は「半夏生(はんげしょうず)」と読み、かつては夏至から数えて11日目としていました。
現在では天球上の黄経100度の点を太陽が通過する日となっていて、毎年7月2日頃にあたります。
この「半夏(はんげ)」は上述のハンゲショウではなく、「カラスビシャク」のことです。
少々分かりにくいですが、「半夏」と呼ばれるカラスビシャクが生える頃のことを「半夏生」と呼び、その時期に葉の色が変わることから上述の植物が「ハンゲショウ」と呼ばれるようになりました。
農家にとっては大事な節目の日で、この日までに「畑仕事を終える」「水稲の田植えを終える」目安で、この日から5日間は休みとする地方もあります。

この日は天から毒気が降ると言われていて、井戸に蓋をして毒気を防いだり、この日に採った野菜は食べてはいけないとされたりしています。
「半夏」は生薬として利用されている
半夏はカラスビシャクのことですが、主に漢方薬で使われる生薬としての「半夏」としてよく知られています。
薬効として去痰を促し、胃の水分代謝を調え、鎮嘔、鎮吐、鎮静などに使われる生薬です。
喉に不快感がある人や不眠症に使われる半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)、吐き気や下痢に効く半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)が市販薬としても売られています。
古くから使われている薬草で、中国の漢の時代に書かれた『神農本草経』にも登場している程で、現在でもさまざまな漢方薬に使われる生薬です。
原産地は中国と言われていますが、薬草として用いられたことから日本に根付き、現在では全国でよく見られます。

そのため、大切な薬草である「半夏」が生える季節が暦の一部となり、「半夏生(はんげしょう)」と呼ばれるようになったのでしょう。
作者「大木あまり」の生涯を簡単にご紹介!

「大木あまり」は1941年に東京都で生まれました。
「大木あまり」の本名を章栄(ふみえ)といい、三姉妹の末っ子として生まれたことから、あまりもので「あまり」としたそうです。
母の薦めで俳句の道へと進んでいき、優れた感性と高度な技術で奥深い俳句を詠み、現在でも活躍している俳人です。
そんな彼女ですが、以外とお酒が強い女性であるという噂があります。
また、猫が大好きで家の近くに出没した狸のこともかわいくて仕方ないと話していました。現在は横浜俳話会の顧問をしています。著書も多く、その俳句は多くの人々を魅了しています。
大木あまりのそのほかの俳句

- 逝く猫に小さきハンカチ持たせやる
- 助手席の犬が舌出す文化の日
- 鳥籠に青き菜をたし春の風邪
- 寝ころべば鳥の腹みえ秋の風
- たべのこすパセリのあをき祭かな
- わが死後は空蝉守になりたしよ
- 汝が好きな葛の嵐となりにけり
- 柿むいて今の青空あるばかり
- 手の切れるやうな紙幣あり種物屋
- 花こぶし汽笛はムンクの叫びかな
- 夜の川を馬が歩けり盆の靄
- 秋風や酔ひざめに似し鯉の泡















