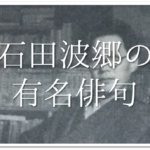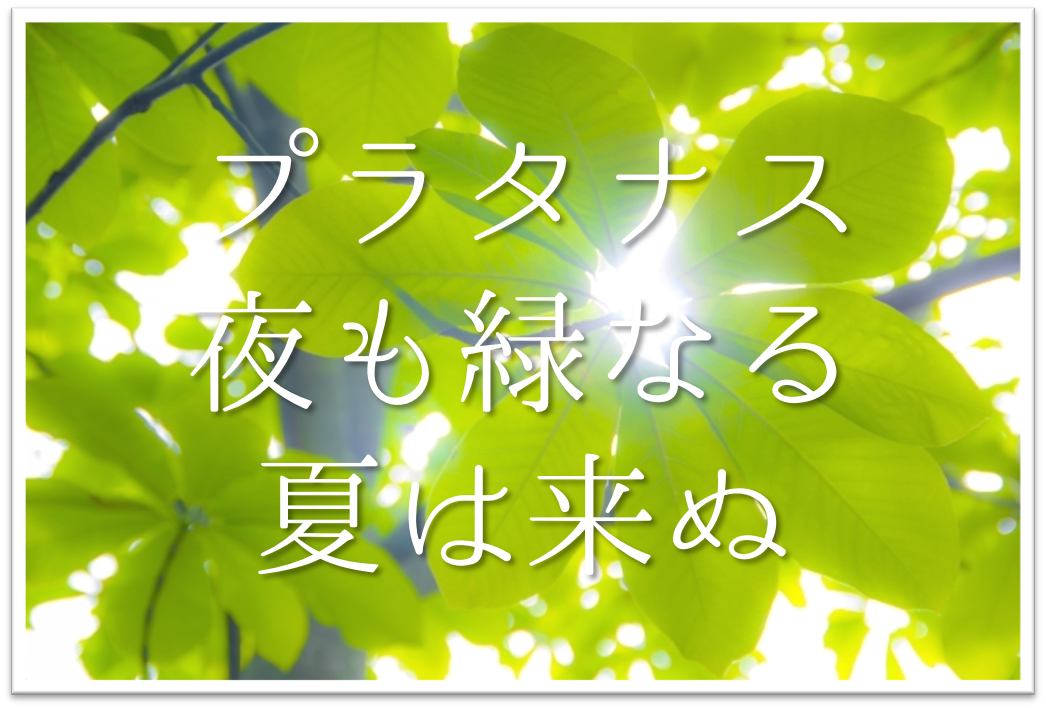
五七五の3句17音から成る定型詩「俳句」。
日本の伝統芸能の一つで、国内外を問わず人気があります。
今回は、数ある名句の中から石田波郷の「プラタナス夜も緑なる夏は来ぬ」という句を紹介していきます。
おはやよ!(o^-^o)
今日の花はプラタナス
花言葉は「天才」「好奇心」プラタナス 夜も緑なる 夏は来ぬ pic.twitter.com/bGNpqKrF72
— やよい🍑 (@841_yayoyayo) December 20, 2018
プラタナス夜も緑なる夏は来ぬ
という句を思い出す pic.twitter.com/1juZ6Ro7gT
— るーしー (@57577ariharasio) June 15, 2016
本記事では、「プラタナス夜も緑なる夏は来ぬ」の季語や意味・表現技法・鑑賞などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「プラタナス夜も緑なる夏は来ぬ」の季語や意味・詠まれた背景

(プラタナス 出典:Wikipedia)
プラタナス 夜も緑なる 夏は来ぬ
(読み方:ぷらたなす よもみどりなる なつはきぬ)
この句の作者は、「石田波郷(いしだはきょう)」です。
石田波郷は愛媛県出身、昭和時代に活躍した俳人の一人です。
石田波郷は人生や生活に根ざした内容の句を得意とし、のびやかな抒情性に溢れた作風が印象的な俳人として知られています。同時に、芭蕉を学び、古典的格調の高い句を残しています。
季語
こちらの句の季語は「夏は来ぬ」で、季節は「初夏」を表しています。
この他「立夏」「夏立つ」「夏に入(い)る」「夏来る」「夏かけて」「今朝の夏」なども初夏の季語になります。

「プラタナス」という冬の北海道を連想させる植物が出てきますが、季語は「夏は来ぬ」となりますので、気を付けましょう。
意味
この句を現代語訳すると・・・
「昼は強い日差しに照らされた街路樹のプラタナスの葉が緑に輝き、夜になるとプラタナスの緑が映ったかのように夜空も緑に染まる、いよいよ夏が来た。」
といった意味になります。
プラタナスとは、和名で「スズカケノキ」。街路樹・庭園樹として広く用いられている樹木です。

夜になっても色鮮やかな若葉の緑を表現することで、夏の到来を詠っている一句です。
この句が詠まれた背景
この句は昭和7年(1932年)に「石田波郷」が詠んだもので、句集『鶴の眼』に収録されています。
石田波郷は19歳になるこの年の2月に上京。初夏にこの句を詠んでいます。
夜になっても緑鮮やかなプラタナスの木々の葉を用いて初夏の感覚を表現していますが、波郷の関心は「プラタナス」そのものにあるのではないかと思われます。

「プラタナス」という外国語の名前を使うことで、都会生活へのあこがれが、にじみ出ています。
「プラタナス夜も緑なる夏は来ぬ」の表現技法

切れ字「ぬ」
「切れ字」は俳句で使われる技法の一つで、感動の中心を表す言葉のことです。
この句の切れ字は「夏は来ぬ」の「ぬ」(完了の助動詞の終止形)です。
夏の到来を心待ちにしていた様子を「ぬ」を用いることで強調しています。
「プラタナス」という切り出し
「プラタナス」という名詞で切り出すことによって句全体にリズム感を持たせています。
また、「鈴懸の木」ではなく、「プラタナス」という外国語の学名をあえて用いているところもこの句を印象的なものにさせています。
初句切れ
句切れとは、意味やリズムの切れ目のことです。
句切れは「や」「かな」「けり」などの切れ字や言い切りの表現が含まれる句で、どこになるかが決まります。
この句の場合、初句(五・七・五の最初の五)に、「プラタナス」の名詞で区切ることができるため、初句切れの句となります。
「プラタナス夜も緑なる夏は来ぬ」の鑑賞文

この句は、街路樹のプラタナスが外灯の灯りに照らされ漆黒の夜に浮かびあがっている様子を詠んでいます。
水原秋桜子の知遇を得た石田波郷は、この年にはじめて上京します。
当時19歳であった石田波郷は都会暮らしへのあこがれが強く、その気持ちは出だしの「プラタナス」という言葉に現れています。
いかにも都会らしく洗練されたイメージを持つ「プラタナス」で切り出し、そして「夜も緑なる」と、生命の力がみなぎる初夏の情景を描き、さいごに「夏は来ぬ」でしめくくっています。
みずみずしい抒情性を詠んだ句で、代表的な青春俳句といえます。

暗闇の中、外灯の灯りで浮かび上がるプラタナスのつややかな緑色の若葉に、みなぎる生命の力と都会暮らしへのあこがれを感じる一句です。
「プラタナス夜も緑なる夏は来ぬ」の補足情報

プラタナスは明治時代に初めて輸入された
プラタナスは葉が大きい落葉樹であるため、「日差しが強い夏は影を作ること」「冬は陽を遮らないこと」「虫がつきにくく下に毛虫が落ちてこないこと」から、街路樹に適している樹です。
そのため、海外では古くから街路樹に使われていて、日本には明治初期に輸入されています。
明治40年に東京市の都市計画の中で街路樹として初めて採用され、明治43年に当時の芝区桜田本郷町に十数本が植えられたのが街路樹としての最初です。
翌44年には神田御徒町に397本、日本橋に63本が植えられ、以後全国に普及していきました。
そのため、この句が詠まれた時点では日本でもまだめずらしい街路樹であったことがわかるでしょう。
作者が上京してきたのは昭和9年で、大学は御茶ノ水にある明治大学です。
彼が見た「プラタナス」は、大学の近くにある神田御徒町に植えられたものなのかもしれませんね。

なお、現在でもJR神田駅の近くには青々とした葉をつけるプラタナスの街路樹が見られるので、作者と同じ体験がしてみたい人は行ってみるとよいでしょう。
プラタナスは「ヨーロッパの象徴」だった
プラタナスが街路樹や公園樹に使われた歴史はとても古く、古代ローマの都市で用いられたり、古代ギリシアでも植えられていたりしています。
ヨーロッパでは樹齢1000年から1500年と伝えられるものもあり、直径が10~15メートルになる大木があるほど付き合いの長い木であり、ヨーロッパの象徴とも言えます。
ただ、イギリスにプラタナスが植えられたのは比較的遅く、1636年頃と伝えられています。

当時のロンドンでは産業革命による煙に悩まされていて、プラタナスは大気汚染に最も強い樹種として採用されていました。
また、プラタナスは耐寒性もあることから、寒冷な地方でも成育します。
プラタナスの花粉や葉の化石は、シベリアやグリーンランド、アイスランドなど寒いところでも多く発見されていて、雪の多い日本の北海道でも育つほどです。
プラタナスは痩せた土地や乾燥した土地でも育ち、大気汚染にも強いことから都市環境にも適応できるため、日本全国で街路樹に選ばれやすくなっています。

現在では「ヨーロッパの象徴」ではなく日本の日常に溶け込んでいるプラタナスですが、作者が都心に出てきた昭和初期では「ヨーロッパという都会」の象徴だったため、特に印象に残ってこの句を詠んだのかもしれませんね。
作者「石田波郷」の生涯を簡単にご紹介!
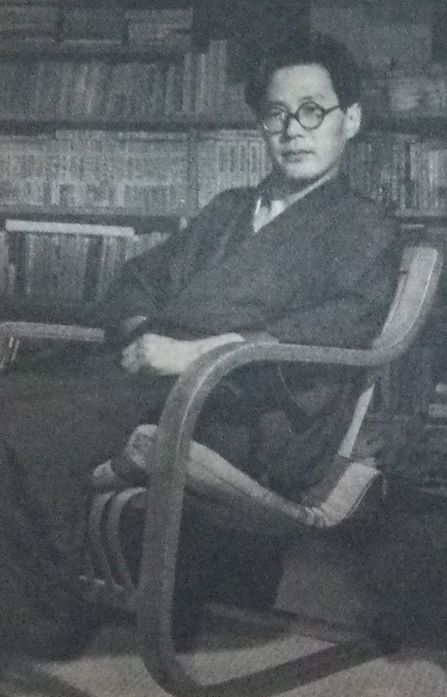
(石田波郷 出典:Wikipedia)
石田波郷(1913年~1969年)は愛媛県出身の俳人で、本名を哲大(てつお)といいます。
少年時代は農家で育ち、子どもの頃から俳句に親しんできました。
県立松山中学校4年生になると本格的に句作を始め、17歳の頃に水原秋桜子門の五十崎古郷(いかざきこきょう)と出会います。
古郷は波郷の才能を認め、自らが師事する東京の秋桜子の元へ波郷を送りだします。
その後、波郷は明治大学文芸科入学を機に最年少で「馬酔木(あしび)」編集に関わることになります。
その後波郷は昭和18年(1943年)の応召で中国に送られることとなりますが、肺結核を発病。手術は数回に及ぶこととなり、その度重なる療養生活を通して波郷が詠む俳句は一層陰影が濃いものになったといわれています。
昭和44年(1969年)11月、亨年56で心臓衰弱のため逝去しました。
石田波郷のそのほかの俳句

- バスを待ち大路の春をうたがはず
- 吹きおこる秋風鶴をあゆましむ
- 初蝶や吾が三十の袖袂
- 霜柱俳句は切字響きけり
- 雁やのこるものみな美しき
- 霜の墓抱起されしとき見たり
- 雪はしづかにゆたかにはやし屍室(かばねしつ)
- 泉への道遅れゆく安けさよ
- 今生は病む生なりき烏頭(とりかぶと)