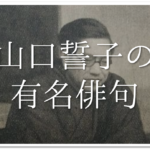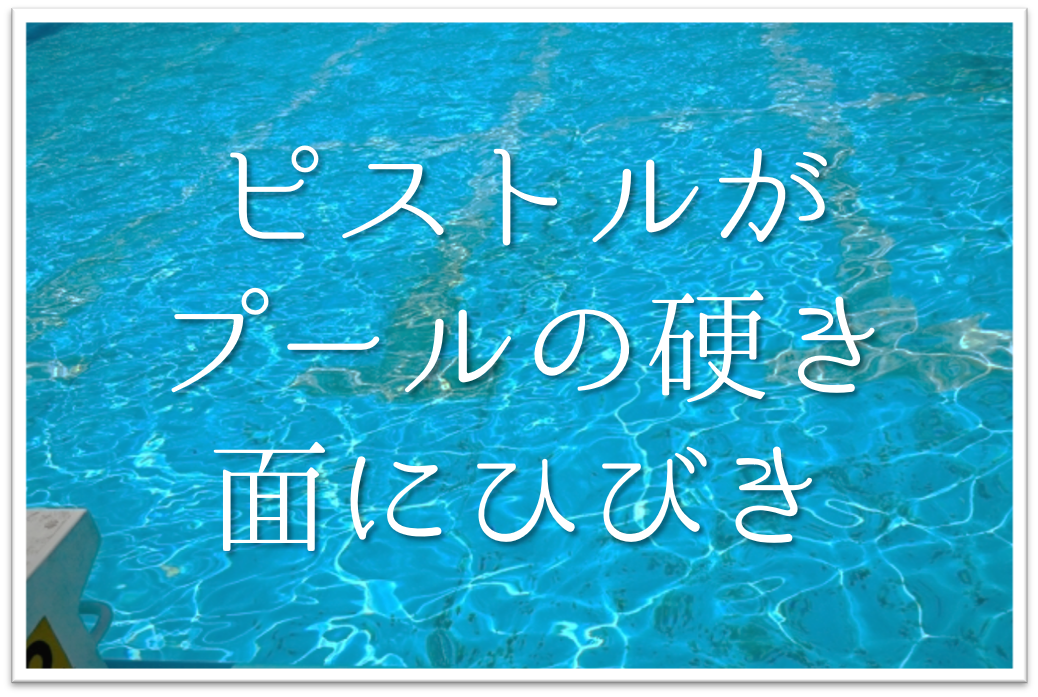
俳句はうつろう四季の美しさ、自然の見せる絶景、日々の心の揺らぎなどを短い言葉で詠み込みます。
数多くの句が詠まれ、鑑賞され、愛されていますが、名句と呼ばれる句は文学としても非常に優れた価値を持っています。
今回はそんな数ある俳句の中でも有名な「ピストルがプールの硬き面にひびき」という山口誓子の句を紹介していきます。
ピストルが
プールの硬き
面にひびき 山口誓子 pic.twitter.com/tUDAvjKysD
— 桃花 笑子 (@nanohanasakiko) June 24, 2014
本記事では、「ピストルがプールの硬き面にひびき」の季語や意味・表現技法・鑑賞などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「ピストルがプールの硬き面にひびき」の作者や季語・意味・詠まれた背景

ピストルが プールの硬き 面にひびき
(読み方:ぴすとるが ぷーるのかたき もにひびき)
この句の作者は「山口誓子」です。
この句は1936年の夏に詠まれた句です。1938年に発行された句集「炎昼」に収録されています。
季語
こちらの句の季語は「プール」で、季節は「夏」です
プールの指す夏は、正確には「晩夏」を指します。
晩夏とは小暑から立秋の前日までを指し、日付で言えば7月7日頃から8月6日頃になります。
ただし、俳句の暦は旧暦という現在とは異なるカレンダーでしたので、現在に置き換えると1か月から1か月半ほど加算して考える必要があります。
そのため、現在の暦ではおよそ8月中旬から8月下旬に換算されます。

また今回の句は戦前に詠まれたこともあり、プールは屋外だったことも注目したい点の一つです。
意味
この句を現代語訳すると・・・
「競泳会場でスタートを固唾をのんで見ていると、スタートを告げるピストルの音が響き渡った。」
という意味になります。
この句が詠まれた背景
この句は1936年の夏に「山口誓子」が詠んだものになります。
まずは、1936年の水泳事情からみていきましょう。
この年は8月1日から夏季オリンピックがベルリンで開かれ、日本は競泳部門で4つの金メダルを取るなど、めざましい活躍が見られた年でもありました。
ただし、誓子の注釈では単に水泳を見に行った話と書かれており、ベルリンオリンピックを見に行ったものではないことが分かります。
オリンピックを直接詠んだものではないのですが、この句が詠まれた1936年は、それだけ水泳は日本の中では非常に明るい話題であり、競泳に盛り上がりが見られた年でもありました。
そして現在のプールとの違いにも注目したい点があります。当時は基本的に屋外プールで、硬いプールサイドや水面からの照り返しが厳しいものでした。
さらに当時は屋外であるため、聞こえやすいように音を出す専用のピストルを使っていました。
現在の大会を見ると、試合会場が周囲の影響を受けにくい屋内のため「ビッ」と鳴る電子音に変更されています。

つまり、この句が詠まれた情景は環境も人々も熱気で溢れているものであったことがわかります。
「ピストルがプールの硬き面にひびき」の表現技法と鑑賞

句切れなし
この句には句中に意味が切れる場所がないため、「句切れなし」と呼びます。
さらに文末も「ひびく」でなはく「ひびき」となっているため、文末も切れていません。
句切れなしに特別な技法があるわけではありませんが、今回の句は少し様子が違います。
この句のピストルの音の様子に着目してください。
「ピストルの音がひびく」と完了せず、「ひびき」と継続している様子になっています。
ピストルの音は破裂音のため、いつまでも反響するものではありません。
しかし継続させることによって、ピストルで開始の音が鳴ったとたんに緊張の様子がとけて掛け声や飛び込みの音などがはじけたように聞こえます。

つまり、句切れなしにすることによって緊張感とそれがはじけた様子が強調されています。
比喩表現の「硬き面」
プールの水面が硬いかと問われると、どちらともとらえる方がいるかと思います。
全身を水で打つようなことがあった方からすれば硬いと答えますし、手ですくえば柔らかいものです。
ポイントはこのような読み手の受け取り方にあります。
誓子は観客席で競泳を見ながら、プールの面(水面のこと)を硬いと表現しています。
今から飛び込むのに硬いというのは比喩表現を使っていると考えられます。
水面を直接的に何か硬いものに例えるのではなく、水自体が硬い性質を持っているという表現になっていることがわかります。
このような直接的な比喩表現を暗喩と呼び、この表現を用いることで誓子の音と水の捉え方が感じられるようになっています。

つまり、句の読み手に音と同時に触覚または視覚で硬さを感じられる奥行き深さをつくっています。
「ピストルがプールの硬き面にひびき」の鑑賞文

この句は競技が始まる直前までの緊張感と、始まった直後のはじけた様子を巧みに表現しています。
競技が始まる直前、つまりピストルの音が鳴った様子を切り取っています。
そこはプールの水面にピストルの「パーン」という破裂音が跳ね返るほど緊張感があふれています。
硬いという言葉遣いが緊張感の高まりを感じさせます。
しかし、一瞬で場面は変わり、水面にピストルが響きわたると選手は飛び込んでバシャバシャと音を立て始めます。そして観客は歓声を上げ、掛け声をかけ大声が響き渡ります。
夏の暑い時期に、選手と観客の熱気で会場は一瞬で沸騰するような様子が伝わります。
ピストルの音という一点を切り取ることで、静けさと熱気という相反するものを表現し、目の前で見ているような臨場感を味わえる句になっています。
「ピストルがプールの硬き面にひびき」の補足情報

日本での近代的な水泳
日本では1918年(大正7年)に大阪市南区の小学校が連合して、堺市の海岸で約4000人に水泳訓練を始めたのが最初とされています。
本格的な普及はもう少し後のことで、1955年に発生した紫雲丸事故及び橋北中学校水難事件で多くの児童生徒が溺死したことから、水泳教育の必要性が説かれて水泳の授業が普及していきました。
現在では、9年間の義務教育課程である小学校および中学校で、水泳教育が適切な水泳場を確保できない場合を除き必修化され「体育」の授業で水泳が行われています。

この句は戦前に詠まれたとのことなので、ここまでの整備が行き届いていない状態の屋外プールでの競技を詠んだものでしょう。
作者が聞いたピストルの音
このような競技の開始を告げるものを「スタートピストル」と呼び、単発式・双発式・電子式の3種類の方式があります。
【単発式】雷管を一発ずつ装填、破裂させる方式。汎用性も高く入手しやすいが、号砲発射の度に雷管を詰め替える必要があるため、1発ずつになる。
【双発式】雷管を二発装填、二発破裂させる方式。この音は微妙にずれがあり、「パパン」という音がする。
【電子式】火薬を用いず、「ピッ」という合成された電子音をスタート音として用いる方式。複数のスピーカーボックスを置いて一斉にスタート音を鳴らすこともできる。近年ではこちらが主流になっている。
作者はこの句を戦前に詠んだとしています。また、音が響くとあるので電子式ではありません。
一方で、双発式の「パパン」という音がしたなら、俳句の中に詠んでいるでしょう。
そうなると、単発式の1発だけのスタートピストルの音を聞いた可能性が高いでしょう。

高らかに鳴る一発のピストルの音とともに飛び込んでいく選手たちを見た、作者の感動が表れている一句です。
作者「山口誓子」の生涯を簡単にご紹介!
(山口誓子 出典:Wikipedia)
山口誓子(1901~1994年)。誓子は「せいし」と読み、本名は新比古(ちかひこ)。京都府出身です。
ペンネームの由来は本名の「ちかひこ」から「誓い子」と漢字を当てたものです。
虚子が主催する「ホトトギス」で四S(しえす)の一人として有名になります。しかし、俳句は叙情的であるべきと論を唱え、虚子とは離反します。
35歳頃に水原秋桜子の俳誌「馬酔木」へ移ってからは、新興俳句運動の中心として活動します。戦後も俳壇で活躍し、1992年には文化功労者に選ばれています。
基本的な現実をそのまま写し取る「写生」の立場ですが、そこに自分の思いを込めた「叙情」の部分を強めた作風をとっています。
山口誓子のそのほかの俳句

( 摂津峡にある句碑 出典:Wikipedia)
- 学問のさびしさに堪へ炭をつぐ
- かりかりと蟷螂蜂の皃(かほ)を食む
- ほのかなる少女のひげの汗ばめる
- 夏草に機缶車の車輪来て止まる
- 海に出て木枯らし帰るところなし
- 夏の河赤き鉄鎖のはし浸る
- 炎天の遠き帆やわがこころの帆