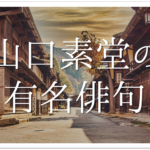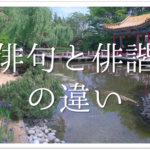江戸時代から続く日本の文学「俳句」。
俳句には純粋に美しい情景を切り取ったものもあれば、読み手に様々な感覚を思わせるものもあります。
今回ご紹介することわざにもなっている「目には青葉山ホトトギス初鰹」は後者のタイプとして知られる句です。
青紅葉♪
目に青葉 山ほととぎす 初がつお(山口素堂)、とつい口をついて出てくるような新緑。気持ちいい〜♪ pic.twitter.com/PaxbUgvGxV— fumiヽ( * ~ * )ノ (@fumi_585) May 7, 2014
この俳句はなぜ様々な感覚を呼び起こさせる力があるのでしょうか?
本記事では、「目には青葉山ホトトギス初鰹」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「目には青葉山ほととぎす初鰹」の作者や季語・意味・詠まれた背景

目には青葉 山ほととぎす 初鰹
(読み方:めにはあおば やまほととぎす はつがつお)
この句の作者は「山口素堂(やまぐち そどう)」です。
素堂は江戸時代前期に活躍した俳人の一人です。多くの漢籍や古典、芸能を身につけた教養人であり、素堂の句は漢籍や古典、芸能などの知識を遺憾無く発揮されています。
季語
こちらの句は「青葉」「ほととぎす」「初鰹」の三つが季語として成立しています。
季節はすべて「夏」になります。
- 青葉・・・落葉樹が青く茂っている様子を指します。よく見られる木ですと、桜を想像すると分かりやすいのではないでしょうか?桜の花が散ると、最初は新緑の若葉が生えますが、夏頃になると濃い緑色の葉に成長します。つまり、当初より青みが増した葉がたくさん茂っている様子を思い起こさせる言葉です。
- ホトトギス・・・和歌の時代から詠み継がれてきた季語の一つです。ホトトギスは夏鳥で5月頃に日本へやってきて、秋冬頃には去っていきます。林や草原に暮らし、ウグイスの巣に卵を産み、育ててもらう托卵の習性があります。鳴き声が「特許許可局」や「テッペンカケタカ」のように聞こえることで有名です。初夏に「キョッキョッキョッ」と鳴いて飛来するため、田植えを知らせる鳥として古くから知られていました。
- 初鰹・・・鰹は回遊魚で、春になると黒潮に乗って北上し、初夏になると伊豆や房総半島沖へやってきます。江戸時代に「初物を食べると七十五日長生きできる」という言い伝えがありました。初物とはその年初めて収穫されたもので、初鰹は初夏を知らせるものとして珍重されました。特に初鰹は江戸っ子からの人気が高く、非常に高値であっても競って購入することが粋だとされていました。
意味
この句を現代語訳すると・・・
「目には初夏の青葉がさわやかに映り、耳にはホトトギスのさわやかな声が届き、口では初物の鰹を味わえる素晴らしい夏だ。」
という意味になります。

現代の私たちが詠んでも季節感を五感で感じることのできる素晴らしい俳句となっています。
この句が詠まれた背景
この句は、山口素堂が35歳頃に鎌倉で詠んだものです。
1678年に池西言水によって発行された俳句集「江戸新道」に収められています。
この句は特に江戸周辺で注目を集めた点が重要です。
江戸っ子をほめるのに「粋でいなせ」という言葉があります。【見た目は派手ではないが、手の込んだものをさりげなく使い、威勢やきっぷの良い様子】を指します。
「粋でいなせ」に生きることが格好良く、そこに季節感が加わることで格好良さに深みが増します。季節を正確に受け取るためには惜しむことなく行動し、それをさりげなく生活に取り入れることが粋である証拠でした。

今回の句には、夏になり青葉が茂っていることを知っていたり、いち早く夏到来を知らせるホトトギスに気づいたりことは粋であり、江戸っ子の共感を得る出来事でした。
そして、最大の共感を得られたのは初鰹を食べることです。
当時の言葉に「初鰹は女房子供を質に置いてでも食え」とあるほど人気がありました。
現在の価格に直せば、初鰹は30万円以上したと言われています。
鰹という響きが「勝つ男」に通じると、江戸時代を通じて人気があった初鰹。料亭八百膳の仕入値が初鰹3本10両(およそ100万)だったという記録も。少し待てば安くなるしさらに美味しくなるのに…こういうときの謎の気っぷのよさが江戸っ子らしさ☆ pic.twitter.com/U73yexe3LH
— 堀口茉純 (@Hoollii) May 2, 2015

非常に高価でも食べるほど、江戸っ子が夢中になっていたことがわかります。
「目には青葉山ほととぎす初鰹」の表現技法

(ホトトギス 出典:Wikipedia)
季重なり
一つの句に季語が二つ以上入っていることを季重なりと呼びます。
季重なりは詠んだ内容がぼやけるため禁じ手とされています。
今回の句は青葉、ホトトギス、初鰹の三種類が入り、句の大半が季語で締められる異常な作風です。
それでもこの句が成立するのは、初夏の新鮮さが五感で伝わるからです。

目の青葉、耳のホトトギス、口の初鰹と全身で夏に好まれるものを受け止め、その幸せが効果的に表現されているため良しとされています。
体言止めによる三段切れ
この句は三回にわたり体言止めを使っています。
体言止めとは、句の最後を名詞で締めること。つまり、句の意味を切っっているのです。
句を/(スラッシュ)で切ると「目には青葉/山ホトトギス/初鰹/」になります。
このように三回切れることを三段切れとよびます。しかし、こちらは句が細かく切れると主題や意味が分散しまとまりがなくなるため、禁じ手の一つになります。
しかし、この句においては句を切ることでリズム感が生まれ、フレッシュ感のある初夏の様子が伝わるよう働いており、問題ないとされています。

また名詞によって端的に述べられることで、「江戸っ子が大好きな夏のものといえば?」という印象を際立てています。
字余りの助詞「は」の効果
初句の「目には青葉」は一文字多く、これを「字余り」と呼びます。
字を余らせないよう記載するならば「目に青葉」で言葉としては足りています。
しかし「は」という言葉を付け加えることで、ほかの体の部位を連想させる効果が発生します。
「目には青葉、耳には山ホトトギス、口には初鰹」のように各部位に対比するように、各々にふさわしいものがあることを示すことができます。

「は」がないと、意味としては平坦になり、今回のような新鮮味がなくなります。
「目には青葉山ほととぎす初鰹」の鑑賞文

【目には青葉山ほととぎす初鰹】の句は、何百年たった今でも季節感を五感で感じることのできる非常に優れた俳句となっています。
たった十七音で季節感を味わおうとすると、目と耳をフル活用することが多いですが、これはすべてを活用することに成功した句です。
俳句では禁じ手とされる技法を多用しており、俳句の決まりに対して厳格な人であれば絶対に詠むことのない句です。
そのような句は逆に鮮烈な印象を読み手に残します。
そして、この句の主題は季重なりで見えにくくはなっていますが、初鰹であることに気づかされます。
目で見て、耳で聞いて、最後に初物の鰹を口で味わったという順であるからです。
平たく言えば「初物の鰹を味わえたぞ!夏に万歳!」という鰹へありがたみの気持ちが隠れています。
それだけ夏の始まりを存分に味わっていることが伝わってきます。

多くの人に愛され、ことわざにもなっているのは、夏が到来する喜びを新鮮で強烈かつ的確に表現できている数少ない句だからではないでしょうか。
「目には青葉山ほととぎす初鰹」の補足情報

前詞と徒然草
この句の前詞は「かまくらにて」となっています。
初鰹が珍重されるのは江戸ですが、前詞は別の場所でこの句が詠まれたことを示しているのです。
これは、鎌倉時代初期に書かれた兼好法師の『徒然草』第119段が関係しています。第119段は、鎌倉の鰹の話をしている箇所です。
「鎌倉の海に、鰹と言ふ魚は、かの境ひには、さうなきものにて、この比もてなすものなり。
それも、鎌倉の年寄の申し侍りしは、
「この魚、己れら若かりし世までは、はかばかしき人の前へ出づる事侍らざりき。頭は、下部も食はず、切りて捨て侍りしものなり」
と申しき。
かやうの物も、世の末になれば、上ざままでも入りたつわざにこそ侍れ」
(訳:鎌倉の海で獲れたかつおという魚は、あ の地域においては最近になって最高のものともてはやされている魚だ。
それでも鎌倉に住む年寄りが申すことには、
「この魚は我々が若かった頃は偉い人の前ではお出しするものではなかった。頭は下々のものも食べず切って捨てるものだった」
と言っていた。
こんなものでも世の末であれば、上流階級までがこんな魚を食うようになってしまった。これも末世のゆえだというから面白い。)
『徒然草』が書かれた鎌倉時代初期には、すでに鰹は上流階級から下々のものまで喜ばれていたのがわかる一幕です。

また、松尾芭蕉が「鎌倉を 生きて出でけむ 初鰹」と詠んでいるように、江戸時代でも一大産地だったこともわかります。
西行法師との関係
この句は「青葉」「ほととぎす」「初鰹」と3つの季語が入っていることで有名ですが、「青葉」と「ほととぎす」の組み合わせは西行法師も使っています。
「ほととぎす きくをりにこそ 夏山の 青葉は花に おとらざりけり」
(訳:ほととぎすの声を聞く頃には、夏山の青葉は花に劣らないものだと感じる)
上記の和歌を元に「目には青葉」の句を詠んだと言われています。
「夏といえばほととぎすに青葉」という和歌の伝統に初鰹という味覚を加えることで、伝統を踏まえつつ滑稽さも演出する「俳諧」として成立しているのです。
前述の通り、鰹は鎌倉時代以前では食べていなかったため、西行法師は初鰹の味を知らなかったのかもしれません。

素堂は「今は鎌倉産の初鰹も食べられるのだ」と彼にとっての「現代」を当意即妙に言い表したため、この句は人口に膾炙したのでしょう。
作者「山口素堂」の生涯を簡単にご紹介!

(山口素堂の歌碑 出典:Wikipedia)
山口素堂(そどう)は1642年生まれ1716年没。本名は信章(しんしょう)。甲斐国(現在の山梨県)の出身です。
実家は酒造を営んでいましたが、20歳頃に江戸へ漢学を学びに出ます。
そこで才能を認められ、仕官していた時期もありました。漢学を学んだことで漢詩への造詣が深く、俳句でもその知識を生かしたとされています。
他にも儒学や能楽などにも理解があるため、当時でも珍しい教養深い人であったとされています。
江戸の三大俳人である松尾芭蕉の親友でもあり、芭蕉の作風「蕉風」の成立にも関わっています。
山口素堂のそのほかの俳句

- 富士山や遠近人の汗拭ひ
- 梅の風俳諧國にさかむなり
- 海苔若和布汐干のけふぞ草のはら
- 夕哉月を咲分はなのくも
- 初鰹またじとおもへば蓼の露
- 富士山やかのこ白むく土用干
- 鬼灯や入日をひたす水のもの
- 茶の花や利休が目にはよしの山
- 凩も筆捨にけり松のいろ
- 小僧来り上野は谷中の初櫻
- 六月やおはり初物ふじの雪
- 武蔵野やそれ釋尊の胸の月
- 夕立や虹のから橋月は山
- 廻廊や紅葉の燭鹿の番
- 入船やいなさそよぎて秋の風
- 宿の春何もなきこそ何もあれ
- 市に入てしばし心を師走哉
- 春もはや山吹しろく苣苦し
- 芭蕉いづれ根笹に霜の花盛