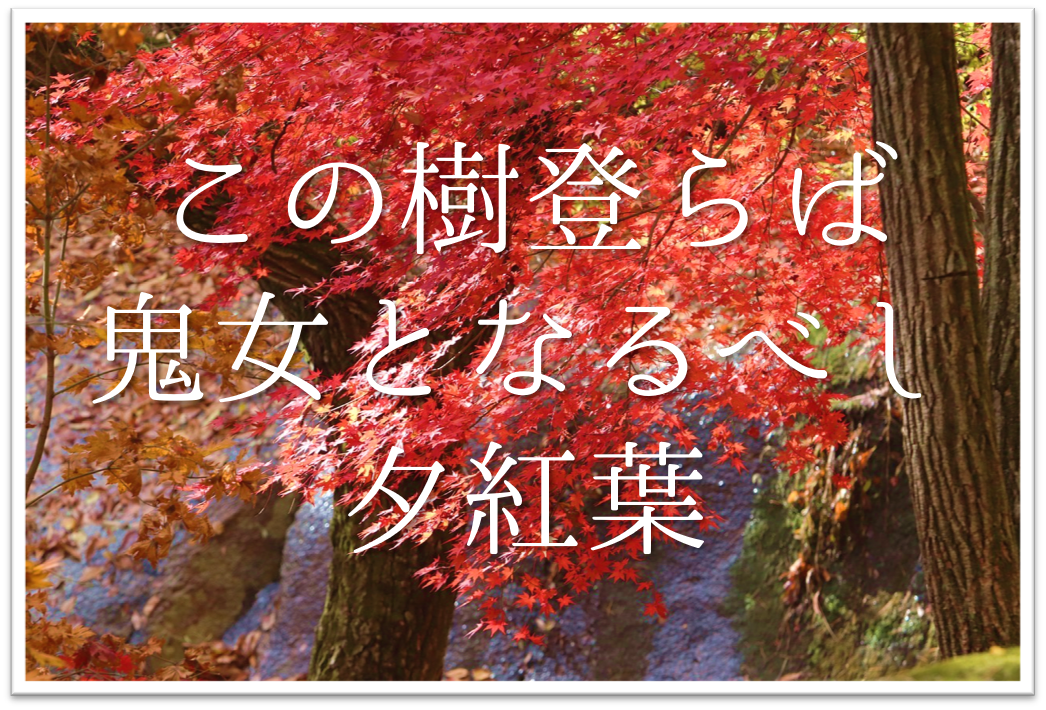
俳句は、五・七・五の十七音からなる日本語の伝統的な短形詩のひとつです。
口ずさみやすく覚えやすい調子、短い言葉で楽しめる気軽さから多くの人に親しまれています。名のある俳人はとくに芸術性の高い句を多く残しています。
今回は数ある名句の中から女性の俳人・三橋鷹女の句、「この樹登らば鬼女となるべし夕紅葉」を紹介していきます。
きょうは境内に立ち寄り、紅葉を見ました。
この樹登らば鬼女となるべし夕紅葉
(三橋鷹女) pic.twitter.com/RTZjJVU6lI— 翡翠 (@Alcyone_viola) November 2, 2014
本記事では、「この樹登らば鬼女となるべし夕紅葉」の季語や意味・表現技法・作者について徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「この樹登らば鬼女となるべし夕紅葉」の作者や季語・意味

この樹登らば 鬼女となるべし 夕紅葉
(読み方:このきのぼらば きじょとなるべし ゆうもみじ)
こちらの句の作者は「三橋鷹女(みつはしたかじょ)」です。
昭和期に活躍した女性俳人の中の代表的な一人です。
季語
この句の季語は「紅葉(もみじ)」で、季節は「秋」を表します。
落葉樹の葉が、秋に赤や黄色に色づくことを紅葉(こうよう)といいます。その中でも特に、楓の葉が赤くなる様子がもてはやされました。

「もみじ」というと主に楓の木のことを指します。
意味
こちらの句を現代語訳すると・・・
「夕日に照り映える美しい紅葉の木にのぼったら、あの有名な鬼女紅葉伝説のように、私も鬼女になってしまうにちがいない。」
という意味になります。
この句は、「鬼女紅葉伝説」を下敷きに、凄みすら感じる紅葉の美しさを詠んだ句になります。

「鬼女となるべし」は、「鬼女になってしまうにちがいない」と訳します。
「この樹登らば鬼女となるべし夕紅葉」が生まれた背景

(鬼女紅葉伝説 出典:Wikipedia)
この句は、長野県の戸隠(とがくし)に伝わる鬼女紅葉伝説を理解していないと解釈しにくい句です。
鬼女紅葉伝説とは、平安時代、平維茂(たいらのこれもち)が戸隠に棲む紅葉(もみじ)と言う名の鬼女を退治したという伝説です。
この伝説がもとになって、中世以降、能や浄瑠璃や歌舞伎などで「紅葉狩(もみじがり)」という演目が上演されるようになりました。「紅葉狩」は、戸隠の山に狩りに来た平維茂が、場にそぐわない身分の高そうな女性たちの紅葉狩の宴に誘われつつも、その正体が鬼であることを見抜き、八幡神の加護を得て退治するというものです。
明治時代には「戸隠山鬼女紅葉退治之伝」(とがくしやまきじょもみじたいじのでん)という、鬼女紅葉伝説をまとめた本が刊行されました。

(戸隠山鬼女紅葉退治之伝 出典:Wikipedia)
それによると、平安時代に子どもに恵まれない没落貴族が第六天の魔王に子宝を祈願、女児を得ます。女児は成長し、紅葉(もみじ)と名乗り、源経基(みなもとのつねもと)に見染められて側室となります。
しかし、野心を持った紅葉は正室を呪い殺そうとして露見。信濃国(現在の長野県)戸隠に流されてしまいます。
紅葉は盗賊らを束ねて自ら首領となり、悪事を重ねます。これを憂えた天皇が紅葉退治の命令を平維茂に下し、死闘の末に紅葉が退治されるという筋になっています。

「この樹登らば鬼女となるべし夕紅葉」の句は、これら鬼女紅葉伝説をベースに、狂おしいまでに美しい紅葉への感動を詠みこんでいるのです。
「この樹登らば鬼女となるべし夕紅葉」の表現技法

こちらの句で用いられている表現技法は・・・
- 「この樹登らば」の字余り
- 「鬼女となるべし」での二句切れ
- 「夕紅葉」の体言止め
- 暗喩
になります。
「この樹登らば」の字余り
俳句は、五音・七音・五音の組み合わせが原則です。
しかし、この句は、初句が七音になっており、七音・七音・五音の律音となっています。このように、字数が多い句を字余りと言います。
あえてリズムを崩すことで印象を強めています。
「鬼女となるべし」での二句切れ
一句の中で、意味の上、リズムの上で大きく切れるところを句切れと呼びます。普通の文でいえば句点「。」がつくところで切れます。
この句は二句の「鬼女となるべし」(鬼女となってしまうにちがいない)で、句点「。」がつきますので、「二句切れ」の句です。
「夕紅葉」の体言止め
体言止めとは、句末に名詞や代名詞などを用いる技法です。余韻を持たせたり、印象を強めたりする働きがあります。
この句は「夕紅葉」という体言で終わる体言止めの句です。
夕日に照り映える紅葉の美しさを余韻を持たせて表現しています。
隠喩(暗喩)
「隠喩(暗喩)」は、「~のような」「~のごとし」といったような比喩言葉を使わずに物事を例える表現技法のことです。
例えば、「北風が冷たい刃になって突き刺さる」という言い方は暗喩です。
(※暗喩に対して、「~のような」「~のごとく」などの言葉を用いたたとえ表現を直喩と言います。例えば、「北風は冷たい刃のようになって、まるで私の体に突き刺さるかのように吹いてくる」という言い方は直喩です)
暗喩の方が言葉の数が少なく、より印象的に表現できるので俳句ではよく用いられる表現技法です。
この句では、紅葉の美しさを「鬼女となるべし」(鬼女になってしまうにちがいない)とたとえています。
これは・・・つまり「まるで鬼女になってしまうに違いないと思わせるような」ということになります。

たとえである言葉を用いずに言い切ることで紅葉の美しさに覚えた感動をより強烈に伝えています。
「この樹登らば鬼女となるべし夕紅葉」の鑑賞文

【この樹登らば鬼女となるべし夕紅葉】の句は、すさまじいまでに美しい紅葉の様子を詠みこんだ句です。
紅葉の美しさをストレートな言葉で称えるのではなく、鬼女紅葉伝説を引き合いに出して、狂おしいまでの凄絶な美しさを詠みこんでいることがこの句の大きな特徴です。
作者はただ漫然ともみじをながめているのではありません。「この樹登らば」(もし、この樹に登ったとしたら)、と想像をふくらめています。
紅葉の美しさを鑑賞するのに、木登りはふつうに考えれば行き過ぎです。
しかし、単に見事な樹をながめる以上のアクションを想像し、「鬼女となるべし」(鬼女となってしまうにちがいない)と強い口調で言い切ります。ここに、女の情念のような激しさ、強烈なイメージがあります。
「夕紅葉」という結句から、美しい紅葉の樹は、夕日に照り映えていることが分かります。赤い紅葉の樹が夕日によってより色濃く赤く輝いているのです。

色彩イメージも強烈です。なんともいえない妖艶な雰囲気を持つ句です。
「この樹登らば鬼女となるべし夕紅葉」の補足情報

この句の世界観
この句には、後ろに2つの句が連続して詠まれています。
「紅葉雨 鎧の武者の とほき世を」
(訳:紅葉に雨が降っている。鎧の武者がいた遠い世のことがしのばれる。)
「幻影は 弓矢を負へり 夕紅葉」
(訳:そんな鎧武者の幻影が、弓矢を負っているようにみえる夕暮れに照らされた紅葉だ。)
これらは前述の鬼女紅葉伝説を元にして詠まれていることは明白でしょう。
最初に「鬼女紅葉」を示唆し、鬼女を対峙する鎧武者の「とほき世」「幻影」を見る、昔話の世界です。
伝説の中で鬼女紅葉は、子を失い火炎をまとった姿で「弓矢を構えた鎧武者」である平維茂に襲いかかり、矢を射かけられています。
これら3句はまさに、怒り狂った紅葉が鬼女となり、鎧武者が現れ、矢を射るという一連の伝説のとおりに詠まれているのです。
夕紅葉から連想された一連の伝説の情景は、3句目で再び現実の夕紅葉へと戻ってきます。

この句の苛烈さをもって作者の気質の苛烈さを表すととらえるだけでなく、同時にどのような順番で句を詠んでいたかを考える必要があります。
鬼無里村と鬼女紅葉
鬼無里(きなさ)村は、鬼女紅葉伝説において、戸隠山以外で決着が着いたとされている場所の一つです。
現在の長野県長野市にあり、決戦の舞台となった荒倉山も鬼無里村の近くに存在しています。
村では紅葉は村人の病を癒し、男には読み書きや算術を、娘には裁縫を教え、京の文化を伝える貴女として村民に敬愛されていましたが、貴人の子の懐妊を巡る騒動で「紅葉狩」と同じく討伐されました。
鬼女紅葉伝説は10世紀頃の話とされていて、「水無瀬(みなせ)」という名前を「鬼無里(きなさ)」と改めたのもこの頃とされています。

村には紅葉の墓が残されていて、「紅葉狩」とはまた違った鬼女紅葉伝説が味わえます。
鬼女紅葉伝説は江戸-明治時代に成立
前述の通り、鬼女紅葉と平維茂の決戦は10世紀中頃の話とされています。
しかし、実際に文献にこの伝説が言い伝えとして登場するのは江戸時代に入ってからです。
平維茂が戸隠山(荒倉山)で鬼退治したとする書物は、江戸時代以降では『大日本史』や『和漢三才図会』に記述があります。
また信濃の地誌である『信府統記』『善光寺道名所図会』などにも記述があり、伝説としてのストーリーは謡曲『紅葉狩』に沿ったものが有名です。

鬼無里村での決着を描いた『北向山霊験記戸隠山鬼女紅葉退治之傳全』が書かれたのは明治時代なので、こちらは伝承としては比較的新しい鬼女紅葉伝説と言えるでしょう。
作者「三橋鷹女」の生涯を簡単にご紹介!
三橋鷹女は本名「三橋たか子」、千葉県生まれの俳人です。生年は明治32年、没年は(1899年)没年は昭和47年(1972年)です。
三橋鷹女 好きだ pic.twitter.com/A7Rat2kGEa
— 佐藤哲朗(nāgita) (@naagita) May 18, 2014
兄が歌人の若山牧水や与謝野晶子に師事していた縁から作歌もしましたが、俳人であり歯科医師であった東謙三と結婚、俳句を詠むようになります。
夫とともに、ホトトギス派の俳人、原石鼎に師事しますが、のちにホトトギス派から離れ、前衛的な句を詠むようになりました。
写生的な手法に頼らず、口語表現を駆使したり、女性の情念を前面に出した句を詠んだりするなど、独特で激しい作風の俳人として活躍しました。
昭和期の女性俳人として、中村汀女・星野立子・橋本多佳子らとともに、四Tと称されました。
三橋鷹女全集第二集より。ドキリ、とさせられる句が多く、御本人も妖しい美しさ。よき家庭人であったと何かで読みました。短歌や俳句には詳しくないので、目次に並ぶかたは大岡信氏と馬場あき子氏のみしか知らないです。大切に読もう。 pic.twitter.com/WrjtHktwWk
— 野宮ゆり (@w06220212k) April 14, 2018
三橋鷹女のそのほかの俳句

- ひるがほに電流かよひゐはせぬか
- みんな夢雪割草が咲いたのね
- 夏痩せて嫌ひなものは嫌ひなり
- 白露や死んでゆく日も帯締めて
- 鞦韆(しゅうせん)は漕ぐべし愛は奪うべし















