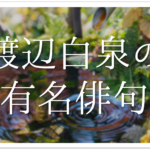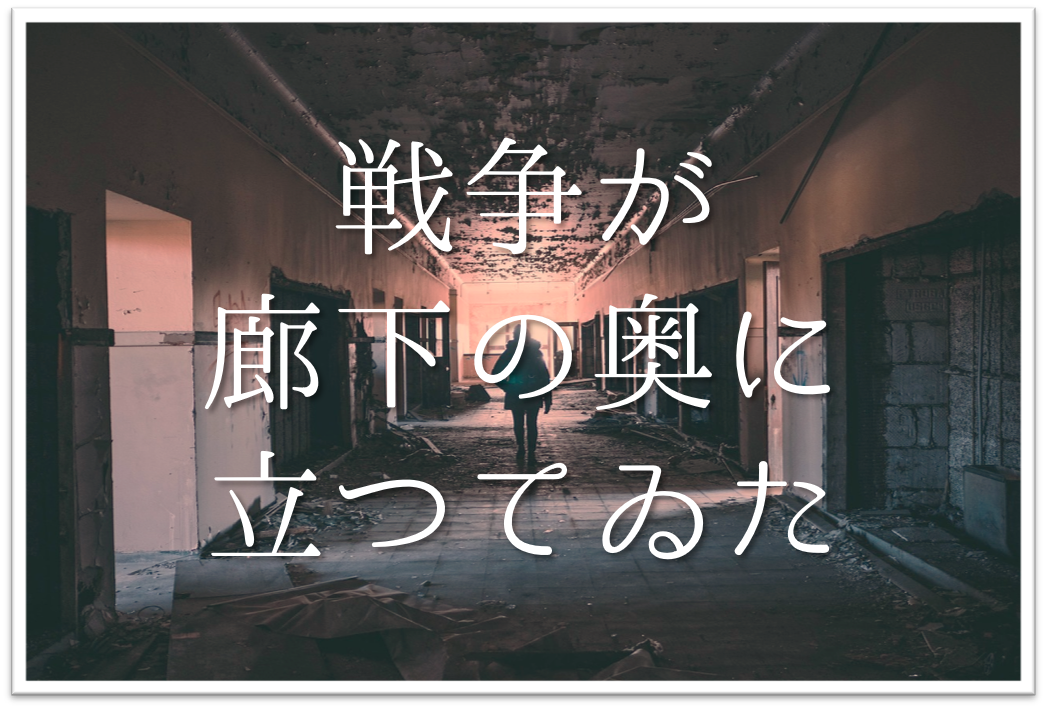
俳句は詠まれた時代を表現していると言われています。
なかでも戦争を題材にした銃後俳句というジャンルがあるのをご存知の方はいらっしゃるでしょうか。
その銃後俳句の中に「戦争が廊下の奥に立つてゐた」という有名な句があります。
【 戦争が廊下の奥に立つてゐた by 渡辺白泉 (1939) 】...こういう感覚を詠むには、無季の方が引き立つのかもしれない。 pic.twitter.com/agtIFQwh9J
— takanori oishi (@t_oishi) November 22, 2013
率直に詠み上げられた句ですが、どういった背景で有名になったのでしょうか?
本記事では「戦争が廊下の奥に立つてゐた」の季語や意味・表現技法・鑑賞・作者などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「戦争が廊下の奥に立つてゐた」の季語や意味・詠まれた背景

戦争が 廊下の奥に 立つてゐた
(読み方:せんそうが ろうかのおくに たっていた)
この句の作者は「渡辺白泉(わたなべはくせん)」です。
作者である白泉は、昭和期に活躍した新興俳句運動の中心となった俳人の一人です。
(※新興俳句運動…昭和初期に始まった新俳句運動のこと。従来の俳句で扱われなかったテーマや表現方法を取り入れた俳句革新運動である)

渡辺氏は戦争の本質を鋭く突いた「銃後俳句」と呼ばれる無季俳句を得意としていました。
季語
こちらの句には季語はありません。
白泉は句作において超季派という立場をとっていました。
超季派は季語で俳句を作るのではなく、季語がなくても俳句が詩として成立することを大切とした考えです。
今回の句は、銃後俳句のため季語がありません。銃後俳句は主題が戦争の俳句で季語によって主題がぼやけるのを避けています。
意味
この句を現代語訳すると・・・
「気がつくと戦争が廊下の奥に立っているように待ち構えていた。」
という意味です。
この句が詠まれた背景
この句は白泉が1939年に詠んだもので、「渡辺白泉全句集」に収録されています
1939年の日本は日中戦争の最中で、第二次世界大戦に参加する2年前でした。
1938年にヨーロッパで世界大戦が始まりますが、まだ日本は対岸の火事であった時でもあります。
そして当時の日本は戦争に対して、少しずつ準備をしていく時期でもありました。つまり、いつ戦争が大きくなってもおかしくはない土台ができていたことになります。

白泉はその様子に皮肉を込めて句作しました。
「戦争が廊下の奥に立つてゐた」の表現技法

銃後俳句
銃後俳句とは、戦争を主題にした俳句を指します。銃後は戦地の後方を意味し、特に戦争に直接関わっていない場所や一般人を指します。
そのため、この句は戦地ではない場所で詠まれた、戦争の空気感を伝える句です。
(※一方、実際の戦地で詠まれた句は「前線俳句」と言います。)
銃後俳句は戦争を主題とするため、主題となり得る季語はありません。
擬人法
擬人法とは物事が人間の動きをしているように表現する技法です。
今回の句では、戦争という物事がまるで廊下に立っているように白泉は詠んでいます。このように表現することで、戦争が待ち構えている様子を表現しています。
また、今回の句は白泉の視点から見て、立っていたことに注目します。
白泉と戦争は同じ廊下におり、戦争は奥に立っています。つまり白泉側は廊下を歩いており、いずれ戦争に出会います。
ぶつかる他にはないことを意味しています。
「戦争が廊下の奥に立つてゐた」の鑑賞文

【戦争が廊下の奥に立つてゐた】は、白泉が感じた大規模戦争への前触れを率直に表現した句です。
当時の日本で、大規模戦争に突入すると予想した人が何人くらいいたでしょうか?
日本は日中戦争で長期化の様子を見せていましたが、第二次世界大戦に参加する2年前です。
世界中を巻き込んだ戦争になると考えた人は日中戦争当初は少なかったと言われています。そういった状況を考えると、大戦が始まると考えた人は決して多くはないことが考えられます。
その中で、白泉は遠くない将来に大規模戦争が起こると考えました。
少しずつ戦争の色が濃くなる様子を白泉は「立つてゐた」と詠み、気がつくと待ち構えていたような表現をしました。
待ち構えている様子が恐怖を感じさせます。
また、廊下の奥と表現することで、一本道で逃げられず、段々と暗くなり戦争へと突入する様子を描いています。暗い様子はぼんやりであっても戦争の姿形が分かるやりきれない気持ちも感じ取れます。
また、気づかないうちに大規模戦争になるという警戒感と回避できない無力感が伝わってきます。

この句は戦争を直接知らなくても恐怖感がひしひしと伝わってくる句となっています。
作者「渡辺白泉」の生涯を簡単にご紹介!
「戦争が廊下の奥に立つていた」
この句を詠んだ渡辺白泉は、昭和15年、治安維持法違反で投獄された。彼は俳句を詠んだだけである。
現政権はこの道を突き進んでいる。 pic.twitter.com/yJJ397NKTd— celelegone (@bottom0202) June 26, 2016
渡辺白泉(わたなべ はくせん)1913年生まれ1969年没。本名は威徳(たけのり)。東京都出身です。
白泉は呉服店の長男として生まれ、慶應義塾大学を卒業します。
大学時代に水原秋桜子に影響を受け、秋桜子が代表する句誌「馬酔木」に投句。これ以降、無季俳句を研究するなど新興俳句の一人として認知されます。
その途中で戦争に対する皮肉を込めた銃後俳句を句作しました。
しかし、治安維持法に基づく「新興俳句弾圧事件」で執筆活動停止を命じられると、表立った活動はなくなります。

亡くなった後に遺品から句をまとめたものが見つかり、弟子であった三橋敏雄たちが白泉の句集を発行します。
「戦争が廊下の奥に立つてゐた」の補足情報

新興俳句運動の旗手「渡辺白泉」
1931年(昭和6年)、水原秋桜子が「自然の真と文芸上の真」を発表し、高浜虚子率いる「ホトトギス」の客観写生・花鳥諷詠の理念から離脱したことをきっかけに、俳句の近代化を目指す「新興俳句運動」が本格化します。
この運動は、季語の制約から自由になろうとする「無季俳句」や、都市のモダンな生活、社会問題、個人の内面などを題材とする新しい表現を追求しました。
東京出身で慶應義塾大学に学んだ作者は、この新興俳句運動の新鋭として頭角を現し、特に無季俳句の分野で才能を発揮しました。
中でも「戦争が」の句は、忍び寄る戦争の不気味な気配を、日常の情景の中に鮮烈に描き出した傑作として知られています。
この句は、直接的な反戦の言葉を用いることなく、戦争という巨大な存在が日常と地続きにあるという本質を鋭く突き、読む者に静かな衝撃を与えます。

作者は「句と評論」や、西東三鬼らと関わった「京大俳句」といった舞台で、こうした新しい感覚の俳句を次々と発表し、新興俳句運動の重要な担い手となりました。
新興俳句弾圧事件と渡辺白泉
しかし、日中戦争から太平洋戦争へと突き進む軍国主義の時代は、こうした自由な文芸活動を許しませんでした。
政府や軍部を批判したり、厭戦的な思想を表現したりすることは厳しく禁じられ、その波は俳句の世界にも及びます。
1940年(昭和15年)、特高警察は「作風と批判の自由」を掲げていた俳誌「京大俳句」に目をつけ、治安維持法違反の容疑で関係者を一斉に検挙しました。
これが「京大俳句事件」であり、新興俳句弾圧事件の始まりです。
弾圧は「京大俳句」に留まらず、など他の新興俳句系の結社にも広がり、多くの俳人が逮捕・投獄され、俳誌は廃刊に追い込まれました。
罪状とされたのは、共産主義への共鳴という容疑でしたが、その実態は、彼らの反戦的、自由主義的な作風が体制に危険視されたことによる理不尽な言論弾圧でした。
「京大俳句」の会員であった渡辺白泉も、この弾圧の標的となりました。
1940年5月に検挙され、4ヶ月以上勾留された末、起訴猶予処分となったものの、執筆活動の停止を命じられました。
この事件は、白泉の俳人としての活動に大きな断絶をもたらします。
戦後、作者は俳壇には戻らず、高校教師として静かに暮らし、1969年に55歳で亡くなりました。
渡辺白泉の生涯と、彼が巻き込まれた新興俳句弾圧事件は、俳句という短い詩の世界ですら、国家権力がその表現の自由をいかに容易に蹂躙しうるかという恐ろしい事実を物語っています。

白泉が遺した句の数々は、弾圧によって沈黙させられた才能の大きさと、時代を射抜くその鋭い感性を、現代の私たちに力強く伝えているのです。
渡辺白泉のそのほかの俳句

- 街燈は夜霧にぬれるためにある
- 鶏(とり)たちにカンナは見えぬかもしれぬ
- 戦争が廊下の奥に立つてゐた
- 銃後といふ不思議な町を丘で見た
- 玉音を理解せし者前に出よ