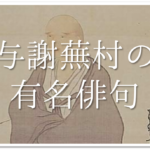五・七・五の十七音に、心情や見た風景を綴り詠む「俳句」。
季語を使い、たった十七音で表現される俳句ですが、その短い言葉から作者の思いを感じることができます。
今回は、与謝蕪村の有名な句の一つ「四五人に月落ちかかるをどりかな」という句をご紹介します。
「四五人に 月落ちかかる おどり哉(蕪村)」。英一蝶の画に賛望まれてと、断わりの有る一句です。ググッてみる限り、どの絵なのか判りませんでしたが、この句だけで夜中に月明かりで踊る人々に、月の光が射している風景が、鮮明に浮かんで来ますね。
— H.Watanabe (@previn_mania) October 3, 2013
本記事では、「四五人に月落ちかかるをどりかな」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。
目次
「四五人に月落ちかかるをどりかな」の俳句の季語や意味・詠まれた背景

四五人に 月落ちかかる をどりかな
(読み方 :しごにんに つきおちかかる をどりかな)
この句の作者は、「与謝蕪村(よさぶそん)」です。
江戸中期に活躍した俳諧師です。松尾芭蕉や小林一茶とともに、「江戸時代の三大巨匠」と言われています。画家でもあり、俳句と絵画を織り交ぜた「俳画」の創始者です。
季語
この句の季語は「踊り(おどり)」、季節は「秋」です。
俳諧で「踊り」といえば、盆踊りのことです。
盆踊りはお盆に帰ってきた先祖の霊を慰めるための踊りで、8月13日から16日にかけて寺社の境内や町の広場などで行われます。櫓(やぐら)が設けられ、笛や太鼓に合わせて輪になったり、行列を作ったりして踊ります。
意味
こちらの句を現代語訳すると…
「宵のうちは賑やかだった盆踊りも、夜が更ける頃にはわずか、四、五人が踊り続けるのみ。傾いた月がその上に落ちかかるようだ。」
という意味です。
この句は、盆踊りを夜通し踊っている様子を詠んでいます。
「賑やかだった盆踊りも気が付けば四、五人が踊るのみとなり、空を見上げれば月がもう西に傾いている。その様子は、月が踊り続ける四、五人の上に落ちかかるようだ」と句に詠んでいます。
この句が詠まれた背景
この句は、『蕪村句集』に収められています。
句の前書には「英一蝶(はなぶさいってふ)が画に賛望まれて」と書かれています。
つまり、英一蝶の描いた画に、賛を請われて蕪村がこの句を作ったということが表されています。写生の句ではありませんが、情景がものすごくハッキリと感じられる句です。

(画家・英一蝶 出典:Wikipedia)
「四五人に月落ちかかるをどりかな」の表現技法

「をどりかな」の「かな」の切れ字
切れ字は「や」「かな」「けり」などが代表とされ、作者が感動を表すとき、強調したいときに使います。
この句は「をどりかな」の「かな」が切れ字にあたります。
俳句の切れは、文章だと句読点で句切りのつく部分にあたります。
「かな」で終わりにすることで、作者が「あんなに賑やかだった踊りを踊っている人も、もう四、五人だなぁ」と、しみじみ眺めている様子が表現されています。
また、五・七・五の最後の句(結句)に切れ字があるので、「句切れなし」となります。
「踊り」と「月」の季重なり
こちらの句には秋の季語「踊り」と「月」の2つが使われています。
このように、一つの句の中に二つ季語が入っていることを「季重なり」と言います。
今回は、切れ字の「かな」が付いている「踊り」が季語とされています。
「四五人に月落ちかかるをどりかな」の鑑賞文

この句からは夕方に東の空から上がってきた月が西に傾く頃、つまり明け方近くまで踊っている様子がわかります。「月落ちかかる」ということは、まだ夜は明けておらず、明るくはなっていないのではないかと想像できます。
「四、五人」と表現しているところに、大勢いた人がどんどん減って、数人になってしまったという様子が浮かび、少し寂しさが感じられます。
また、蕪村は、盆踊りを踊り続ける四、五人を照らし続ける月、その月で時間の経過を表現したかったのではないでしょうか。
実際にはあり得ない「月が落ちかかる」という表現で、月の存在が強調されているように思います。
この句は画賛の句ですので、蕪村が英一蝶の画を見て詠んだ句になります。
写生の句のように、目に見えた事実を詠んでいるかのように情景が目に浮かびます。画家でもあり、俳諧師でもある蕪村だからこそ詠める句だと感じられます。
作者「与謝蕪村」の生涯を簡単にご紹介!

(与謝蕪村 出典:Wikipedia)
与謝蕪村は、享保元年(1716年)摂津国東成郡毛馬村、現在の大阪市都島区毛馬町に生まれました。本名は谷口(または「谷」)信章(のぶあき)と言います。
与謝蕪村は20歳頃に江戸で俳諧や画を学び、22歳頃に早野巴人(はやのはじん)に師事。
27歳の時、師事していた巴人が亡くなり、以後10年は放浪生活を送りました。放浪生活中は、絵を宿代の替わりに置き、敬い慕う松尾芭蕉ゆかりの地(北関東など)を巡りました。「蕪村」と名乗り始めたのは、29歳頃と言われています。
36歳頃には京に行き、42歳頃には京都での定住を始め、画業に専念しました。この頃から「与謝」と名乗り始めたと言われています。
55歳の時、若い頃に師事していた巴人が名乗っていた「夜半亭」の二世を継ぎ、本格的に俳諧に打ち込み始めました。画業においても、俳諧においてもその才能が認められ、当時、画業、俳諧ともに一流の存在だったと考えられます。
蕪村は、古典や歴史に俳諧の素材や構想を求めました。また、画家でもあるので、俳風は写実的で絵画的な印象の句が多いと言われています。
そして蕪村は、俳句に絵を入れる独自の形「俳画」を確立させました。『奥の細道図巻』はとても代表的なもので、松尾芭蕉の『奥の細道』を書き写し、挿絵を入れたものです。
蕪村の死後、百十数年後に正岡子規が「俳人蕪村」を連載し、高く評価したことから再び与謝蕪村が注目されるようになりました。このような評価があったため、松尾芭蕉や小林一茶と並ぶ江戸俳諧の三代巨匠と言われるようになったのです。
与謝蕪村のそのほかの俳句

(与謝蕪村の生誕地・句碑 出典:Wikipedia)
- 夕立や草葉をつかむむら雀
- 寒月や門なき寺の天高し
- 菜の花や月は東に日は西に
- 春の海終日(ひねもす)のたりのたりかな
- 夏河を越すうれしさよ手に草履
- 斧入れて香におどろくや冬立木
- 五月雨や大河を前に家二軒
- うつくしや野分のあとのとうがらし
- 山は暮れて野は黄昏の芒かな
- ゆく春やおもたき琵琶の抱心
- 花いばら故郷の路に似たるかな
- 笛の音に波もよりくる須磨の秋
- 涼しさや鐘をはなるゝかねの声
- 稲妻や波もてゆへる秋津しま
- 不二ひとつうづみのこして若葉かな
- 御火焚や霜うつくしき京の町
- 古庭に茶筌花さく椿かな
- ちりて後おもかげにたつぼたん哉
- あま酒の地獄もちかし箱根山